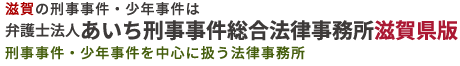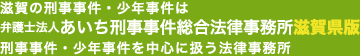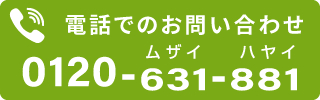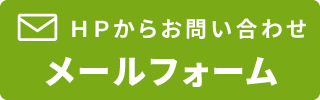Author Archive
大津市の児童買春で逮捕 同種の前科がある場合の弁護活動
大津市の児童買春で逮捕 同種の前科がある場合の弁護活動
大津市で児童買春の容疑で逮捕された方に、同種の前科がある場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
児童買春の容疑で逮捕
数年前に児童買春の罪で罰金刑を受けた前科のあるAさんは、再びSNSで知り合った17歳の女子高生に対して、性交の対償として5万円を支払うことを約し、大津市内のラブホテルで性交しました。
女子高生と性交渉してから数カ月後、Aさんは、自宅を訪ねて来た警察官に児童買春の容疑で逮捕されました。
Aさんには以前も児童買春事件を起こし、罰金刑を受けた過去があるため、今後のことが非常に不安です。
(フィクションです)
児童買春について解説
児童買春行為につき有罪判決が確定すると、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)。
「児童買春」とは
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者
に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます(同法第2条2項)。
この法律でいう児童とは18歳未満の男女です。
つまりAさんは、児童に当たる女子高生に、性交の対償として5万円を供与することを約束して性交しているので、児童買春の罪を構成すると考えて間違いないでしょう。
逮捕直後の弁護活動
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
身体拘束が長期化すれば、会社や学校を長期間にわたって無断欠勤・欠席することになってしまいます。
早期に弁護士を依頼し、より早く外に出られるように活動してもらうことが必要です。
起訴された場合
初犯であっても、児童買春事件が起訴される可能性は高く、同じ前科があるAさんが起訴される可能性は極めて高いでしょう。
児童買春事件を起こしたのが初めてであり、被害者が1人程度であれば、略式手続により罰金刑を受けて事件が終了することが多いと思われます。
しかし、同種前科を有するAさんについては、略式手続ではなく、「公判請求」という形式で起訴される可能性があります。
児童買春事件において公判請求がなされる場合とは、前科がある、犯行態様が悪質である、被害者が多数存在するなどの理由で、検察官がAさんにつき懲役刑を相当と思料しているケースです(略式手続では懲役刑に処することはできません)。
公判請求がなされた場合は、公開の法廷に立って裁判を受けることになります。
また、前述の通り、略式手続で懲役刑が言い渡されることは法律上ありえませんが、公判請求がなされた場合は、懲役刑を言い渡される可能性があります。
懲役刑に処せられ、執行猶予がつかなければ、刑務所に入らなければならなくなります。
このような場合は、執行猶予付き判決を獲得し、刑務所での服役を回避することが極めて重要となります。
逮捕されてからの手続きの流れについては
執行猶予付き判決の獲得を目指す弁護活動
まずは、被害者と示談を成立させることが非常に重要です。
示談が成立すれば、Aさんにとって有利な事情として考慮されることが期待できます。
また、Aさんが児童買春事件を繰り返してしまった背景には、医学的、心理学的に説明されるべき問題が潜んでいるかもしれません。
精神科や心療内科において、専門的な治療、カウンセリングを受け、再犯防止に努めていることを裁判官にアピールすることも考えられます。
児童買春事件を繰り返してしまい、逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が児童買春事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県で逮捕されたら 釈放を早める弁護士
滋賀県で逮捕されたら 釈放を早める弁護士
滋賀県で逮捕された方の釈放を早める活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
滋賀県で家族が逮捕されたら
ご家族が、何か刑事事件を犯してしまい警察に逮捕されてしまったら・・・
そのことを知った方は「何をしたの?」「新聞等に実名報道されるの?」「いつ釈放されるの?」「処分はどうなるの?」等と、色々な不安が脳裏をよぎるでしょう。
そんなご家族の不安を少しでも解消できるのが弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件で不安を感じておられる方のお役に立ちたくて、刑事事件を専門に扱っている全国でも数少ない法律事務所です。
滋賀県の警察署に逮捕されている方のもとへ、弁護士を派遣する初回接見サービスを年通無休で承っておりますので、まずは
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
釈放を早めることはできるの?
ご家族が警察に逮捕された方からよくされる質問の一つが
「釈放を早めることはできるのですか?」
ですが、その答えは「イエス」です。
当然、絶対とは言えませんが、早期に弁護士を選任することによって釈放の時期が早まる可能性は十分にあります。
まず逮捕されてからの手続きの流れと共に、釈放に向けての弁護士の活動について説明します。
(1)逮捕から48時間以内
警察が逮捕した犯人を身体拘束できるのは、まずは48時間です。
この48時間以内に警察は犯人を釈放するか、検察庁に送致するかを判断しなければなりません。
そこで弁護士は、その判断をする警察署に対して逮捕された方の釈放を要請することができます。
警察署宛てに書類を提出したり、担当の捜査員と交渉したりする方法で釈放要請をすることによって、逮捕から48時間以内に釈放されることがあります。
このタイミングで釈放されるのが逮捕から最短の釈放となります。
(2)裁判所に勾留請求されるまで(逮捕から72時間以内)
逮捕から48時間以内に検察庁に送致されると、今度は検察官が犯人の勾留を請求するかどうかを判断します。
勾留の請求は検察官が裁判官に対して行うのですが、検察官が、この判断を下すのに許されている時間は送致を受けてから24時間以内です。
つまり逮捕された方は、逮捕から起算すると72時間以内に勾留を請求されるかどうかが決まります。
弁護士は、裁判官に対して勾留を請求するかどうか判断する検察官に対して、逮捕された方の釈放を要請することができます。
検察官に書類を提出したり、担当の捜査員と交渉したりする方法で釈放要請をすることによって、逮捕から72時間以内に釈放されることがあります。
(3)裁判官が勾留を決定するまで
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、逮捕された犯人を勾留するかどうかを判断します。
勾留の期間は10日から20日と法律で決まっています。
最初の勾留決定で10日間の勾留が決まり、その後、必用に応じて10日間まで延長されることがありますが、延長の際は再度裁判官の許可が必要となります。
そこで弁護士は勾留を決定する裁判官に対して、勾留を決定しないように求めることができます。
裁判官が、検察官の勾留請求を退けた場合、その時点で釈放を決定します。
ここまでが逮捕から勾留が決定するまでの流れで、それぞれのタイミングで弁護士が釈放を求めることができるので、早期に弁護士を選任するメリットは十分に感じていただけるのではないでしょうか。
国選弁護人は付かない
裁判官が勾留を決定するまで国選弁護人は付きません。
つまり上記したタイミングでの早期釈放を望むのであれば、それに向けた活動ができるのは私選の弁護人に限られます。
私選の弁護士を選任するとなれば、弁護士費用でお悩みの方も多いかと思いますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では明朗会計を心掛けていますので、弁護費用でお悩みの方は一度ご相談ください。
釈放を早める弁護士のご用命は
滋賀県の警察署に逮捕された方の釈放を早めれるのは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に特化した弁護士です。
刑事事件専門の弁護士のご用命は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
電車内での痴漢事件…条例違反?強制わいせつ罪?
電車内での痴漢事件…条例違反?強制わいせつ罪?
電車内での痴漢事件が条例違反なのか強制わいせつ罪なのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県草津市を通る電車内で、利用客の女性Vさんに対し、服の中に手を入れ、胸や陰部を触る痴漢行為をしました。
Aさんは、Vさんから何も言われなかったことをいいことに、翌日もVさんを電車で見かけると、Vさんに対して先日と同様の痴漢行為をしました。
すると、周囲を警戒していた滋賀県草津警察署の警察官が、Aさんの痴漢行為を現認し、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、「電車内の痴漢は都道府県の迷惑条例違反」と聞いたことがありましたが、自分の逮捕容疑が強制わいせつ罪と聞いて驚いています。
Aさんの家族は、滋賀県草津警察署から、Aさんを逮捕したという連絡を受け、刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・電車内痴漢事件と条例違反
痴漢事件は、今回の事例のように、電車内や商業施設、といった場所で起こることも多く、比較的身近な刑事事件であるといえます。
しかし、痴漢行為がどのような犯罪に当てはまるかという点については実際の刑事事件の詳細な事情を検討しなければならず、実は複雑な犯罪です。
よく言われているのは、「電車内や駅といった公共の場所で起こった痴漢事件は都道府県の迷惑防止条例違反となる」ということです。
今回の事例のAさんも、電車内の痴漢事件は迷惑防止条例違反になると聞いたことがあったようです。
これは、各都道府県で制定されているいわゆる迷惑防止条例が禁止している痴漢行為が、いわゆる「公共の場所」での痴漢行為に限定されていることが多いということが1つの要因だと考えられます。
実際に滋賀県の迷惑防止条例を見てみましょう。
滋賀県迷惑行為等防止条例3条
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
このように、滋賀県の迷惑防止条例では「公共の場所」「公共の乗物」で起きた痴漢行為の禁止を規定しています。
つまり、これらの場所以外で起きた痴漢行為については、迷惑防止条例の対象外となります。
しかし、今回のAさんは電車内=「公共の乗物」で痴漢行為をしています。
それでも迷惑防止条例違反とならない場合もあるのでしょうか。
・電車内痴漢事件と強制わいせつ罪
痴漢事件でよく問題となる犯罪としては、迷惑防止条例違反のほかに刑法上の強制わいせつ罪があります。
強制わいせつ罪は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」(刑法176条)と規定されている犯罪です。
痴漢事件と一口にいっても、その犯行態様は様々です。
服の上から身体を軽く触る痴漢行為から、服の中に手を入れて直接体を触る痴漢行為まで、すべて「痴漢事件」であるからです。
そうした場合、この犯行態様の違いによって、たとえ「公共の場所」で起こった痴漢事件でも迷惑防止条例違反とはならず、強制わいせつ罪となる場合があります。
強制わいせつ罪の「暴行」と「わいせつな行為」は、同じ行為でもよいとされています。
例えば、抱き着く行為などは、それ自体が「暴行」であり「わいせつな行為」であると考えられます。
こうしたことから、犯行態様が悪質な痴漢行為の場合は、強制わいせつ罪として検挙されることがあるのです。
・痴漢事件と弁護活動
痴漢事件は今回のVさんのような被害者が存在します。
ですから、弁護活動としてはまず被害者の方への謝罪や弁償が思いつかれることでしょう。
しかし、痴漢事件の場合、お互いがお互いの連絡先を知らないことがほとんどですから、被害者の方へ謝罪しようにも簡単に連絡を取ることはできません。
では警察などの捜査機関に聞いてみるとしても、被害者にとっては痴漢の加害者と直接連絡を取るということは抵抗の大きいことです。
こうしたことから、なかなか当事者だけで痴漢事件の示談交渉をすることは難しいといえるでしょう。
だからこそ、まずは弁護士に相談・依頼し、被害者対応を開始することが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で24時間いつでも専門スタッフがサービスをご案内いたします。
電車内での痴漢事件でお困りの際は、まずはお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
保険金の水増し請求で詐欺罪に
保険金の水増し請求で詐欺罪に
保険金の水増し請求で詐欺罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県大津市で整骨院を経営していました。
Aさんは、交通事故に遭って治療のためにやってきた患者Bさんと共謀して、Bさんの通院日数や治療内容を偽造し、保険会社に保険金を水増しして請求しました。
しかし、保険会社の調査が入り、AさんとBさんが共謀して保険金を水増し請求をしていたことが発覚。
保険会社は滋賀県大津北警察署に通報し、滋賀県草津警察署は捜査を開始しました。
その結果、AさんとBさんは、詐欺未遂罪の容疑で、滋賀県大津北警察署に逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・保険金の水増し請求で詐欺罪に
実際には行っていない治療や入院、通院を偽造して保険会社へ保険金を水増し請求し、水増しされた保険金を受け取れば、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺事件というと最近ではオレオレ詐欺などに代表される振り込め詐欺が有名ですが、こうした水増し請求による詐欺事件も、詐欺事件の典型例です。
保険会社としては、請求された分の治療や入院・通院があることを基にして、その分の保険金を支払っています。
ですが、実はその治療等が存在しない水増し請求であったとなれば、保険会社から水増し分の保険金をだまし取っている=「人を欺いて」保険金を得ているので、詐欺罪が成立しうるということになります。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪にいう「人を欺く」行為とは、その財物を交付する際に交付の判断を左右するような重要な事実を偽ることであるとされています。
今回の事例のような保険金の水増し請求の事例では、保険会社がその保険金額を支払う根拠となる通院日数や入院日数、治療内容といった部分に嘘があるということになりますから、詐欺罪のいう「人を欺」くことに該当するのです。
そして、今回の事例では、保険金が支払われる前に保険会社が保険金の水増し請求に気づいていますが、こうした場合でも、水増し請求を行った時点で詐欺未遂罪が成立します。
保険金の水増し請求による詐欺事件では、今回の事例のように、客や整骨院・病院の従業員が一緒になって詐欺行為をする手口が取られやすいです。
すなわち、詐欺事件の事件関係者が複数人存在するということになるため、捜査機関や裁判所は、口裏合わせなどによって証拠隠滅されるのではないかと懸念することが予想されます。
こうしたことから、逮捕や勾留によって身体拘束されたうえで捜査されることも充分考えられます。
また、余罪があるのではないかと疑われることや、余罪が存在する場合は再逮捕が繰り返されて長期間の身体拘束となることも考えられます。
早めに弁護士に相談・依頼することで、このような事態にも迅速に対応してもらえることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、保険金の水増し請求による詐欺事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
突然の逮捕にお困りの方、水増し請求による詐欺事件にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
集団暴走で高校生の子どもが逮捕されてしまった!
集団暴走で高校生の子どもが逮捕されてしまった!
集団暴走で高校生の子どもが逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県高島市に住んでいる18歳の高校生です。
Aさんは、大晦日の夜に、友人のXさんら6人でバイク3台に分乗すると、滋賀県高島市内の道路を蛇行運転したり信号無視をしたりといった集団暴走をしました。
Aさんらがパトロール中の滋賀県高島警察署の警察官らの前でバイクを空ぶかしさせたり爆竹を鳴らしたりしたことから警察官らがAさんらを追跡。
最終的に、Aさんたちは滋賀県高島警察署に集団暴走による道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの母親Bさんは、帰宅しないAさんを心配して滋賀県高島警察署に相談したところ、逮捕され留置されていることが判明しました。
警察官から、「本日から明日は会えないと思う。詳しいことも話せない」と伝えられたBさんは困ってしまい、少年事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※令和3年12月7日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・集団暴走で子どもが逮捕された!
今回の事例のAさんは、友人のXさんらと一緒に3台のバイクに乗り、一緒になって蛇行運転や信号無視をする集団暴走をしています。
こうした集団暴走行為は、交通事故を誘発する可能性のある、非常に危険な行為です。
そのため、集団暴走行為は「共同危険行為」として道路交通法によって禁止されています。
道路交通法第68条(共同危険行為)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
道路交通法第117条の3
第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
集団暴走という単語からは、暴走した人数や自動車・バイクなどの数が多くなければ犯罪にならないように思えますが、道路交通法にある通り、人数は「二人以上」、自動車・バイクなどの数は「二台以上」であればよいため、例えば2人が2台のバイクや自動車などに分乗して暴走行為をしても集団暴走、「共同危険行為」として道路交通法違反という犯罪になります。
道路交通法での「共同危険行為」とは、このように複数人が複数の自動車やバイクなどを連ねて又は並べて道路を運転する際、一緒に著しい道路上の危険や他人への迷惑を発生させることが該当の条件となっています。
今回のAさんらの集団暴走行為では、蛇行運転や信号無視といった行為が行われています。
先ほども触れたように、蛇行運転や信号無視は交通事故を引き起こし得る、非常に危険な行為であることに間違いありませんから、Aさんらは複数人・複数台で「共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ」たと考えられるでしょう。
こうしたことから、Aさんらは集団暴走行為をしたことによる道路交通法違反(共同危険行為)と判断され、逮捕されたのでしょう。
さて、今回の事例のAさんは、滋賀県高島警察署に逮捕されています。
集団暴走行為によって刑事事件・少年事件となった場合、逮捕によって身体拘束されてしまうケースも珍しくありません。
集団暴走行為は当然複数人で行われるものですから、事件関係者が複数人存在することになります。
そうなると、口裏合わせなどによって証拠隠滅されてしまうおそれがあるとして、逮捕によって身体拘束をした上で捜査を進めるという判断がされる場合が出てくるのです。
さらに、今回の事例のAさんのように、少年事件である場合には、捜査が終了した後も、更生のためには集団暴走行為をする環境から切り離すべきと判断される可能性もあります。
そういった場合、当事者が予想していたよりも長期間に渡って身体拘束が続いてしまい、身体的・精神的負担が大きくなってしまうことも心配されます。
弁護士などの専門家の力を借りることで、釈放を求めたり、逮捕などによる身体拘束中の負担を減らすべくサポートをしたりすることができます。
まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、集団暴走によって子どもが逮捕されてしまったというお悩みにも迅速に対応できるよう、お問い合わせ用フリーダイヤルを設置しています。
まずはお気軽に問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
覚醒剤所持事件で保釈請求を相談
覚醒剤所持事件で保釈請求を相談
覚醒剤所持事件で保釈請求を相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市に住むAさんは、SNSを利用して、以前から興味を持っていた覚醒剤を入手しました。
そしてAさんは、自宅で覚醒剤を使用していたのですが、Aさんの挙動がおかしいことに気づいた近隣住民が滋賀県木之本警察署に相談。
そこから捜査が開始され、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは勾留され、覚醒剤取締法違反の容疑で起訴されることも決まりました。
Aさんの家族は、長らくAさんが身体拘束されている状況に不安を感じ、どうにかAさんの身体拘束を解くことはできないかと、保釈について弁護士に相談することにしました。
相談後、Aさんの家族は弁護活動を依頼することにし、弁護士はAさんに速やかに接見を行い、保釈請求をするための準備を始めました。
(※この事例はフィクションです。)
・保釈請求と刑事事件
保釈とは、起訴後、保釈保証金の納付を条件に、被告人の身体拘束を解く制度のことを言います。
保釈は起訴後に可能となる制度であるため、逮捕された段階であったり、逮捕に引き続いて行われる被疑者段階での勾留では、保釈の制度を利用することはできません。
ですから、保釈請求をしたいという場合には、今回のAさんのように起訴される段階になってようやく請求が可能になるということになります。
保釈の際に納付する保釈保証金とは、いわゆる保釈金のことです。
保釈金の額は、事件の内容や被告人の環境・資力などによって変動します。
多くの場合、150万円~300万円の間で設定されるケースが見られます。
保釈金は、保釈中に逃亡したり証拠隠滅をしたりしないようにするための担保とされるもので、それらの条件を破ってしまった場合に一部または全部没収されることになります。
もちろん、保釈中の約束事を守って過ごしていれば、最終的に保釈金は全額戻ってくるということになります。
こうしたことから、その人が没収されてしまったら困るという額が保釈金とされるのです。
ですから、例えば芸能人や政治家など、一般の人に比べて多くの資産を持っていると想定される人が被告人となっている場合には、「没収されてしまうと困る」という額にするために、先ほど挙げたような150万円~300万円といった額よりも高額な金額が設定される場合もあります。
そして、保釈金はあくまで担保としてのお金であるため、保釈金が払えれば保釈されるというわけではありませんし、保釈金を多く準備できればよいというわけでもありません。
では、保釈請求をして保釈許可をもらうためには、どういった準備が必要になってくるのでしょうか。
保釈が認められるためには、逃亡や証拠隠滅等のおそれがないと認められる必要があります。
保釈が認められる際の条件としても、裁判への出頭をすることや、事件関係者へ接触しないことなどが定められることが多いです。
ですから、例えば、家族などが身元引受人として被告人の行動を監督する環境を作ることで、被告人が逃亡・証拠隠滅といったことができないようにする、そういった環境にあることを家族から聴取し、まとめて証拠とするといった準備をした上で保釈請求をするといったことが考えられます。
保釈請求に回数は制限されていないため、1回保釈請求が却下されたとしても、もう1度保釈請求をすることができます。
そのため、たとえ1度保釈請求をして保釈が叶わなかったとしても、環境を改善させながら粘り強く請求をしていくことが重要です。
特に、Aさんのような覚醒剤取締法違反事件では、薬物自体が証拠隠滅しやすい物であることや、売買に関する事件関係者が多く予想されることなどから、逮捕・勾留による身体拘束をされやすく、さらに身体拘束を解くことが容易でない事件であることが多いです。
粘り強い保釈請求のためには、弁護士の刑事事件への知見や、ご本人・ご家族とのこまめなコンタクトが求められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、覚醒剤取締法違反事件や保釈に関連したご相談をお受けしています。
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
怨恨からつきまとってストーカー規制法違反に
怨恨からつきまとってストーカー規制法違反に
怨恨からつきまとってストーカー規制法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市にある会社Xに勤務しているAさんは、同僚のVさんに対して好意を抱いており、Vさんにアタックするようになりました。
しかし、VさんはAさんに対して断りを入れ、Aさんは振られた形となりました。
Aさんは、Vさんが自分の好意に対して応えてくれなかったことを恨み、Vさんに対してメッセージアプリでメッセージを連続して送ったり、Vさんが帰宅する後をつけたりするようになりました。
Vさんは、Aさんにつきまといをやめるよう伝えたのですが、Aさんは意に介さず、さらにしつこくメッセージの送信やつきまといをするようになりました。
Aさんの行為に恐怖を感じるようになったVさんは、滋賀県長浜警察署に相談。
その結果、Aさんは滋賀県長浜警察署にストーカー規制法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・怨恨をきっかけにしたストーカー事件
ストーカーというと、被害者に好意を持った人が被害者につきまとうといった内容が思い浮かびやすいのではないでしょうか。
たしかに、ストーカー行為を規制しているストーカー規制法(正式名称「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)でも、ストーカー行為を定義する際、恋愛感情や好意による「つきまとい等」を繰り返すことであるとしています。
ストーカー規制法第2条第4項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。
ストーカー規制法第2条第1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
第1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
第2号 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
第3号 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
第4号 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
第5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
第6号 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
第7号 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
ストーカー規制法第2条第1項にもある通り、ストーカー行為につながる「つきまとい等」は、恋愛感情や好意に基づいたものである必要があることが定められています。
それに加えて、そういった恋愛感情や好意が「満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行われる「つきまとい等」も、反復して行うことでストーカー行為となることが定められています。
つまり、単に被害者のことを好きだということでストーカー行為をすることだけでなく、例えば「振られた」ということによって逆恨みしてストーカー行為をするといった場合にも、ストーカー規制法違反となることになります。
・ストーカー規制法違反と逮捕
今回のAさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されています。
ストーカー事件の場合、加害者側が被害者の連絡先や自宅を知っている場合が多く、加害者と被害者の接触を避けるなどのために逮捕や勾留によって身体拘束をした上で捜査されるというケースも少なくありません。
逮捕されてしまった場合、誰に相談することもできず取調べなどに対応することになりますから、不安や精神的負担が大きくなってしまうと予想されます。
逮捕直後から弁護士に相談し、逮捕された被疑者と面会しアドバイスをしてもらうことで、刑事手続きを知らないということによる不安を払拭することが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスなどを通じ、逮捕されてしまった被疑者へのサポートも迅速に行っています。
怨恨から発展したストーカー規制法違反事件にお困りの方、逮捕にお悩みの方は、お早めにご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
パートタイマーでもインサイダー取引になる?
パートタイマーでもインサイダー取引になる?
パートタイマーでもインサイダー取引になるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県米原市に本社を構えるV社で、清掃員のパートタイマーとして働いていました。
ある日、AさんがV社の社内を清掃していた最中に目についた資料から、V社が翌月に独自の技術を使った新製品を発表することを知りました。
Aさんは、新製品が発表されればV社の株価が値上がりするだろうと考え、新製品の発表前にV社の株式の買い付けを行いました。
そして、Aさんは、V社が新製品を発表した後に値上がりしたV社の株式を売却し、多額の利益を得ることになりました。
しかしその後、Aさんがインサイダー取引を行ったことが発覚。
Aさんは滋賀県米原警察署に金商法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「ただのパートタイマーだったのにインサイダー取引になるのか」と疑問に思い、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・インサイダー取引とは?
インサイダー取引とは、会社関係者が上場会社等の業務等に関わる「重要事実」を、その職務に関して知りながら、その「重要事実」の公表前にその会社の株等の売買等を行うことを指します。
大まかには、会社関係者が株価に重大な影響を与えるような事実を公表前に知りながら株式の売買を行うことがインサイダー取引になるというイメージです。
インサイダー取引は、日本語で内部者取引とも呼ばれます。
・パートタイマーでもインサイダー取引に?
このインサイダー取引については、金商法(正式名称「金融商品取引法」)という法律で禁止されています。
金商法第166条第1項
次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第5号から第8号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第167条の2第1項、第175条の2第1項及び第197条の2第14号において「売買等」という。)をしてはならない。
当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後1年以内のものについても、同様とする。
第1号 当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社並びに当該上場会社等が上場投資法人等である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。
金商法第166条第1項では、「会社関係者」が「上場会社等に係る業務等に関する重要事実」を知った場合、その「重要事実」が公表された後でなければ、該当する会社等の株式の売買等をしてはいけないとされています。
つまり、「会社関係者」が「重要事実」公表前に該当する会社等の株式を売買することがインサイダー取引となり、この金商法第166条第1項に違反する犯罪となるということです。
では、その対象となる「会社関係者」とはどういった人を指しているのか、「重要事実」を知るとはどういった状況を指しているのかというと、続く第1号~第5号に記載があります。
第1号では、「会社関係者」について、「当該上場会社等(中略)の役員(中略)、代理人、使用人その他の従業者」としています。
会社の「使用人その他従業者」となっていることから、この「会社関係者」の中には、会社のいわゆる正社員だけでなく、Aさんのようなパートタイマーやアルバイトの従業員も含まれていることが分かります。
さらに、その「使用人その他従業員」について、どのような業務についているのかといった制限もされていませんから、Aさんのような清掃員であっても「会社関係者」となり得ることが分かります。
インサイダー取引というと、会社の役員や上役など、会社の中心にいる人が関わる犯罪というイメージが強いかもしれませんが、Aさんのようなパートタイマーであってもインサイダー取引の対象となる可能性があるのです。
そして、金商法第166条第1項第1号では、こうした「使用人その他従業者」などの人が「その者の職務に関し」重要事実を「知ったとき」に、その「重要事実」公表前に当該会社等の株式の売買等をしてはいけないということを定めています。
例えば今回の事例のAさんは、自身の職務である、V社内の清掃中に、V社の新製品についての情報を知っています。
その後、AさんはV社の新製品についての情報が公表される前にV社の株式の売買をしていることから、Aさんには金商法第166条第1項第1号に違反するインサイダー取引の疑いがあるということになるのです。
金商法第166条第1項第1号に違反するインサイダー取引をしてしまった場合の刑罰は、以下のとおりです。
金商法第197条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第13号 第157条、(中略)又は第166条第1項若しくは第3項若しくは第167条第1項若しくは第3項の規定に違反した者
さらに、インサイダー取引で得た財産については没収されます。
金商法第198条の2第1項
次に掲げる財産は、没収する。
ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
第1号 第197条第1項第5号若しくは第6号若しくは第2項又は第197条の2第13号の罪の犯罪行為により得た財産
インサイダー取引というと、日常生活とは関わりの薄い犯罪のように思えますが、実は誰でも関わり得る犯罪です。
そして、インサイダー取引による金商法違反は、上述の通り、とても重い刑罰が設定されています。
だからこそ、インサイダー取引事件の当事者となってしまった場合には、早期に弁護士に相談・依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、事件の始まりから終わりまでフルサポートします。
インサイダー取引を含む刑事事件にお困りの際は、お早めに弊所弁護士までご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
飲酒運転で刑事裁判に発展してしまったら
飲酒運転で刑事裁判に発展してしまったら
飲酒運転で刑事裁判に発展してしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県彦根市に住んでいる会社員です。
Aさんは、通勤に自動車を利用していたのですが、ある日、会社帰りに居酒屋で飲食した際、飲酒していたにもかかわらず、「いつも通っている道なのだから大丈夫だろう」と自動車を運転して帰路につきました。
しかし、その道中、滋賀県彦根警察署の警察官が飲酒検問をしており、Aさんの飲酒運転が発覚しました。
Aさんは過去に飲酒運転で罰金となったことがありましたが、「事故を起こしたわけでもないのだから交通違反程度のことだろう。今回も罰金を支払って終わりだろう」と考えていました。
そのAさんの考えに反し、Aさんは取調べのために訪れた検察庁で、「起訴して刑事裁判になる」という話を聞きました。
驚いたAさんは、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒運転でも刑事裁判になる
多くの方がご存知の通り、飲酒運転は犯罪です。
道路交通法では、飲酒運転を「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けて禁止しています。
道路交通法第65条第1項(注:酒気帯び運転)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法第117条の2の2(注:酒気帯び運転の刑罰)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
道路交通法第117条の2(注:酒酔い運転とその刑罰)
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
このうち、道路交通法第65条第1項のものが「酒気帯び運転」、道路交通法第117条の2第1号のものが「酒酔い運転」と言われる飲酒運転です。
酒気帯び運転は基準値以上のアルコールが検出された場合(呼気1リットルあたり0.15mg以上)に当てはまる飲酒運転であり、そのうち酒に酔っている程度が強いもの(例:千鳥足になっている、ろれつがまわっていないなど)は酒酔い運転となるイメージです。
飲酒運転と聞くと、単なる交通違反のイメージがある方もいらっしゃるかもしれませんが、刑罰を見ると懲役刑なども設定されていることが分かります。
・飲酒運転は単なる交通違反ではない?
交通違反のうち、軽微な交通違反は反則金制度(交通反則通告制度)の対象とされています。
反則金制度とは、簡単に言えば、軽微な交通違反の場合に反則金を納めることで、刑事手続・少年保護手続を受けないようにするという制度で、反則金を納めれば、出頭する必要もなくなります。
こうした反則金制度もあってか、交通違反と刑事事件、刑事裁判が結びつきにくい方も多いでしょう。
しかし、この反則金制度は、全ての交通違反について適用されるというわけではありません。
今回の事例のAさんの飲酒運転も、反則金制度の対象外となる交通違反です。
そのため、飲酒運転をしてしまえば、反則金を納める納めないにかかわらず、刑事事件化してしまいます。
飲酒運転の他にも、無免許運転などが反則金制度の対象外となる交通違反として挙げられます。
先ほども触れたように、飲酒運転には懲役刑=刑務所へ行く刑罰も定められているため、繰り返してしまったり態様が悪質だったりすれば、起訴されて正式な刑事裁判となります。
刑事裁判には入念な準備をもって臨む必要がありますし、そうでなくても刑事事件には一般の方が把握できていない権利や手続き、注意点があります。
飲酒運転事件にお困りの際は、弁護士にお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転事件を含めた交通に関わる刑事事件も取り扱っています。
お気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
少年事件の試験観察とは?
少年事件の試験観察とは?
少年事件の試験観察とはどういったものなのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県東近江市に住んでいる高校1年生のAさんは、学校から自宅へ帰る道中に、別の高校に通う生徒と口論の末に喧嘩となり、相手の生徒を殴って骨折などの大けがを負わせてしまいました。
喧嘩を目撃していた通行人が滋賀県東近江警察署に通報したことで警察官が現場に駆け付け、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、たびたびこうした暴行・傷害事件を起こしており、中学生の時にも逮捕され、保護観察処分となった経緯がありました。
そういった経緯から、今回は少年院送致となるかもしれないと聞いたAさんの両親は、少年事件に対応している弁護士に相談。
そこでAさんの両親は、少年事件には試験観察という制度があると聞き、弁護士に試験観察について詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の終局処分
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、少年事件の手続や処分には、成人の刑事事件と異なるものが多くあります。
未成年の者は可塑性が高い=矯正教育などをすることで更生できる可能性が高いとされているため、少年事件では少年の更生を重視した手続・処分が取られることとなっているのです。
少年事件では、基本的には家庭裁判所での調査を経た上で家庭裁判所で開かれる審判を受けることになります。
少年事件では全件送致主義という主義に基づいて、警察などの捜査機関での捜査が終わった事件については、基本的にすべての事件が家庭裁判所へ送られるためです。
こうして少年事件の専門家の調査を受け、審判によって処分が決められるのです。
家庭裁判所の審判で下される処分は、成人の刑事事件で処される刑罰とは異なり、あくまで少年の更生のための処分(保護処分)という扱いです。
ですから、例えば少年院送致のように、特定の施設に収容されるような処分であっても、その非行をしたことによる罰というわけではありません。
少年院送致も少年の更生のために行われる処分であり、少年院内では矯正教育やその後の自立のための職業訓練などが行われています。
・試験観察とは?
しかし、少年院送致が少年のための処分であったとしても、少年院に入っている間は社会から切り離されて生活することになります。
通っていた学校に通えなくなってしまったり、働いていた会社で働けなくなってしまったりというデメリットがあることもまた事実です。
一度社会から離れてしまうことによるデメリットを避けるために、少年院送致を回避したい、社会内で更生を目指したいと考える方ももちろんいらっしゃいます。
こうした少年事件においては、試験観察を目指すという付添人活動をおこなう場合があります。
試験観察とは、文字通り、試験的に観察する期間を設ける処分を指します。
試験観察は、審判の場で少年の処分をどういったものにするのかすぐに決められない場合に取られます。
試験観察となった場合、決められた期間を家庭裁判所の観察のもと過ごし、その期間中の少年の生活態度や様子などによって最終的な処分が決められることになります。
この試験観察期間は、少年の自宅で過ごす場合もあれば、民間の協力者や専門施設に指導を委ねてその指定された場所で過ごす場合(補導委託)もあります。
今回のAさんの事例では、Aさんは以前にも同じような傷害事件を起こして家庭裁判所から保護処分を受けているにも関わらず、Aさんは同様の少年事件を起こしているという状況です。
社会内での更生を目指す保護観察処分を経てもまた同じことを繰り返してしまっていますから、前回同様の処分だけでは公正に不十分と考えられ、少年院で矯正教育を受けながらの生活が必要と判断される可能性も十分あると考えられます。
ですから、まずは前回よりもより具体的な手段を示して、社会内での更生が可能であることや、そのためにAさん本人やその周囲の家族が具体的に行動し続けられることを示していく必要があると考えられます。
そのために、弁護士と共にAさんやその家族で更生のための環境づくりを行うと共に、その成果を家庭裁判所に示して判断をしてもらえるよう試験観察を目指していく活動が有効であると考えられるのです。
ただし、試験観察はあくまでその期間中試験的に少年やその周囲を観察し、その様子によって最終的な処分を決めるものです。
試験観察を目指すことを最終目的としてしまうのではなく、さらにその先も見据えながら、更生できる環境を整えることが重要です。
そのためには、少年事件の専門知識がある弁護士のサポートを受けることが効果的です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく少年事件の取り扱いも行っております。
滋賀県の少年事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。