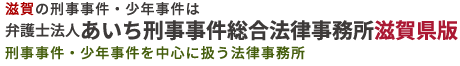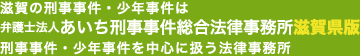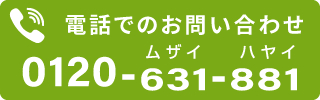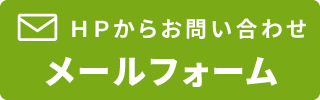Author Archive
成人式で新成人が暴行事件
成人式で新成人が暴行事件
成人式で新成人が暴行事件を起こしてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさん(20歳)は、滋賀県大津市で開かれる成人式に参加する新成人でした。
Aさんは、成人式の前から同級生たちと飲酒しており、酔っぱらって気が大きくなっていました。
すると、成人式の参加者である新成人Vさんと肩がぶつかったことがきっかけで口論となり、AさんはVさんを突き飛ばすなどの暴行を加えてしまいました。
周囲の人が通報し、Aさんは滋賀県大津警察署に暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はAさんが成人式の会場でAさんが暴行事件を起こし逮捕されたと滋賀県大津警察署から連絡を受けました。
そこで、Aさんの家族は速やかに接見に向かってくれる弁護士を探し、逮捕されているAさんのもとへ行ってもらうことにしました。
(※令和2年1月13日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・成人式で暴行事件を起こしてしまった…
1月13日は成人の日でした。
この記事を読んでいる方の中にも、成人式に参加した新成人の方や新成人のご家族・ご友人がいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の事例は、そんな新成人を祝う成人式での刑事事件です。
成人となればお酒も飲むことができますし、さまざまな制約がなくなります。
しかし、それと同時に、成人すればそれだけの責任も負うことになります。
20歳となって成人すると、犯罪をしてしまった時に少年事件ではなく刑事事件として取り扱われることとなります。
ですから、新成人のうちすでに20歳になっている人たちについては、成人式で犯罪を起こしてしまえば刑事事件として取り扱われることになります(成人式時点でまだ19歳の新成人もいるかと思いますが、その場合は少年事件として取り扱われます。ただし、20歳を過ぎてしまえば刑事事件として取り扱われることとなるため、注意が必要です。)。
少年事件と刑事事件の具体的な違いとしては、少年事件では原則として刑罰を受けることはなく、少年の更生のための処分(保護処分)を受けますが、刑事事件では有罪になれば刑罰を受けることになることとなり、それは前科となること等が挙げられます。
さらに、刑事事件の場合、事件の内容によっては報道機関によって実名報道がなされる場合もあります。
Aさんのように、成人式の新成人同士の喧嘩で暴行を振るってしまった場合、刑法の暴行罪が成立することになるでしょう。
刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
さらに、暴行の結果、相手が怪我を負ってしまったような場合には、刑法の傷害罪が成立します。
刑法204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回の事例のAさんは暴行罪の容疑で逮捕されていますが、Vさんの怪我が判明し診断書が出たような場合には、容疑が暴行罪から傷害罪へと切り替わることも考えられます。
なお、Aさんの暴行相手が警備中の警察官等、職務中の公務員であった場合には、刑法の公務執行妨害罪が成立することになることにも注意が必要です。
刑法95条(公務執行妨害罪)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
・暴行事件と弁護活動
暴行事件には、Vさんのような被害者がいます。
暴行事件の弁護活動としては、まずは被害者への謝罪やその被害の弁償をし、示談交渉をすることが考えられるでしょう。
Vさんがすでに成人済の新成人であれば、弁護士はVさんと示談交渉をすることになりますし、仮にVさんがまだ19歳の新成人であれば、Vさんの保護者である両親等と示談交渉をすることになるでしょう。
知人同士で連絡先が分かっている間柄であれば謝罪をしやすいかもしれませんが、成人式でたまたま顔を合わせただけの関係であれば、謝罪をしようにも連絡の取りようがありません。
通常、警察等の捜査機関は被害者の同意なしに被害者の個人情報を加害者側に教えることはしませんから、弁護士を通じて示談交渉ができないか打診していくことが望ましいでしょう。
また、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまっています。
刑事事件の捜査段階では、逮捕を含めて最長23日間の身体拘束がなされる可能性があります。
それだけの期間身体拘束されてしまうことは、就学先や就職先に迷惑をかけてしまうだけでなく、就学先・就職先に居られなくなってしまう可能性も出てきてしまうことになります。
だからこそ、早い段階で弁護士に釈放を求める活動を始めてもらう必要があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に迅速に対応できるよう、お問い合わせを24時間いつでも受け付けています。
土日祝日も変わらずお問い合わせいただけますので、刑事事件にお困りの際はお気軽に、お早めにご連絡ください。
(フリーダイヤル:0120-631-881)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
裁判員裁判と公判前整理手続
裁判員裁判と公判前整理手続
裁判員裁判と公判前整理手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市に住むAさんは、自宅近くで起きた殺人事件の被疑者として、滋賀県木之本警察署に逮捕されました。
その後起訴され、裁判員裁判を受けることになったAさんですが、自身の弁護人としてついている弁護士から、裁判員裁判の前に、公判前整理手続という手続きがあることを説明されました。
AさんもAさんの家族も、公判前整理手続という聞きなれない言葉に不安を感じたため、弁護士に詳しく話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・公判前整理手続とは
裁判員裁判が行われる際、その裁判期日の前に必ず実施されるのが、公判前整理手続と呼ばれる手続きです。
公判前整理手続とは、裁判そのものではなく、裁判のために、争点や証拠を整理し、裁判の計画を立てるための手続です。
通常の裁判では、公判前整理手続が行われることも行われないこともあります。
事件の内容が複雑であったり、被告人が容疑を否認していたり、証拠や証人の数が多くなったりしている刑事事件の場合、公判前整理手続が開かれることも珍しくはありません。
一方、被告人が容疑を認めていたり、特に複雑な事情がなかったりすれば、公判前整理手続が取られずに裁判が行われていくことも多いです。
しかし、裁判員裁判では、一般の方が裁判員として参加することになります。
裁判員として参加するのは一般の方であるため、法律的な争いがわかりづらく、さらに裁判員裁判は公判が集中的に開かれるため、1週間以上毎日公判がある、ということもあります。
そのような裁判員として裁判に参加する方々の負担を軽減するため、また、そのために連日裁判が行われることを可能にするため、この公判前整理手続が必ず行われることとなっているのです。
では、公判前整理手続では具体的にどのようなことを行うのでしょうか。
公判前整理手続では、裁判所と検察官、弁護士が、前述のように、審理計画を立てるために証拠や争点を整理し、絞り込みます。
被告人自身が公判前整理手続に出席するか否かは、弁護士と相談して決めることとなります。
公判前整理手続の場では、本当に裁判で争うべきポイントはどこなのか、どの証拠を裁判で調べるべきなのか等が議論されます。
どういった争点や証拠が裁判で争われるのかは、被告人の処分に大きく影響します。
ですから、裁判員裁判となる場合、公判前整理手続にもきちんと対応できる弁護士に相談・依頼することが重要なのです。
裁判員裁判になる刑事事件は重大な犯罪であることが多いため、そういった意味でも弁護士への相談が重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、刑事弁護活動を行います。
もちろん、裁判員裁判や公判前整理手続についても、対応が可能です。
刑事事件専門だからこその知識と経験を活かし、依頼者様の利益を守るために活動いたします。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県長浜市の名誉毀損事件
滋賀県長浜市の名誉毀損事件
滋賀県長浜市の名誉棄損事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
Aさんは,滋賀県長浜市の居酒屋で開かれた会社の飲み会に参加しました。
飲み会の終盤で,上司のVさんが店員と揉めだし,その店員を殴り全治2週間の怪我を負わせました。
日頃からVさんによるパワハラに耐えかねていたAさんは,この事実を記載しVさんは乱暴者だという内容のビラを社内の掲示板に貼り出しました。
Vさんが滋賀県長浜警察署に相談したことで,名誉毀損罪による立件を念頭に,滋賀県長浜警察署が捜査を始めました。
その噂を聞いたAさんは,自身が名誉毀損罪の容疑で逮捕されるのかもしれないと怖くなり,弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【名誉毀損罪】
人の名誉を傷つけたり,人を侮辱することはそれぞれ名誉毀損罪や侮辱罪などによって処罰の対象となります。
事実の適示によらず,単に軽蔑の価値判断を示すことによって名誉を害した場合には侮辱罪の適用が考えられますが,今回はVさんによる店員への暴行(傷害)行為という事実を示しているので,名誉毀損罪の適用が最も濃厚といえます。
刑法第230条第1項
公然と事実を適示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪における名誉とは,人に対する社会的評価を意味します。
例えば,ある人が特定の女性と親密に交際しているという事実は,それを公表することによってその人の社会的評価を下げるものではないですが,その関係がいわゆる不倫であると示すときは倫理的・道徳的非難を含むことになり名誉毀損行為となる場合があります。
今回の事件のように,被害者が過去に犯した犯罪の事実についても,それが公になると被害者の社会的評価は下がるものと考えられますので,名誉棄損行為に当たるとされる場合が多いです。
名誉棄損罪の成立において,示された事実は,それが真実であることを要しません。
つまり,本当にあったことでなくとも,あるいは本当であったことでも,その事実を述べることにより被害者の社会的評価が害される危険を持つものであれば名誉棄損罪の処罰の対象となり得るということです。
また,名誉棄損罪の成立の際,実際に被害者の名誉が害される必要はありません。
それは,名誉を害するような行為があったとしても,その行為によって被害者の社会的評価が低下したことを確認するのはほとんど不可能だからです。
そこで,名誉毀損罪が成立するためには名誉が実際に侵害されたことは必要とされず,侵害の危険が生じたことで十分とされています。
加えて,社会的評価を下げるのに適した行為をすることで侵害の危険が生じたものとされ,実際に具体的な侵害の危険が生じることは必要とされません。
一方,名誉毀損罪の成立要件となる行為には公然性が必要とされています。
公然とは,不特定または多数の人が知ることのできる状態をいいます。
ただし,判例によれば,事実を示した相手が特定かつ少数人に止まる場合であっても,そこから他の人に伝播し最終的に不特定多数者が認識し得る可能性があれば公然性が認められるとされています(最判昭和34・5・7刑集13巻5号641頁)。
加えて,名誉棄損罪の成立には事実を適示されることによって社会的評価が害される人物が特定されていることも必要です。
つまり,「日本人」や「滋賀県民」などといった漠然とした表示では特定性を欠くことになり,被害者の氏名やその者とはっきりと分かる属性が示されていなければ名誉毀損罪は成立しません。
さて,今回のAさんはVさんの店員に対する暴行を示しています。
暴行行為は暴行罪等で処罰される犯罪にあたりうるので,この事実を示されたVさんの社会的評価は害されたものといえます。
AさんはVさんの暴行行為に関するビラを社内の掲示板のみに貼っており,公然性が問題になり得ますが,会社には社外の人間も多く出入りし,さらには判例の理論に則れば,ビラを見た人物が周囲の人物に拡散してしまう可能性も否定できず公然性も認められるでしょう。
したがって,Aさんの行為は名誉毀損罪に当たり得るものといえます。
【真実性の証明】
刑法第230条の2は第1項で「前条(230条)第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない」と定めています。
同条第2項によって,公訴前の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなされるので,Aさんが起訴された場合はこの規定を利用することにより名誉毀損罪の成立を回避することが考えられます。
ただし,主たる目的が公益を図るところになければならないため,Aさんが既にパワハラへの報復目的であったことを示している場合は真実性を証明することによる処罰回避は難しくなります。
【活動の方針】
名誉毀損罪は親告罪なので,Vさんの告訴がなければ起訴されません。
Vさんは既に滋賀県長浜警察署へ相談していますが,告訴されているかは不明です。
さらには,起訴される前であれば告訴を取り消すことができるので,Vさんと早めに示談をして告訴しない(あるいは取り下げる)ようにすることができれば起訴を回避することができます。
示談交渉を当事者のみで行う場合,成立までにかかる時間やその内容などで多くの負担を要します。
また,被害者が加害者と接触することを拒み,交渉を開始することができないケースも多いです。
お早めに弁護士に依頼していただくことで,そういった負担を軽減し,依頼者様により有利な内容で示談を成立させる可能性を飛躍的に高めることができます。
名誉毀損罪の被疑者となってしまった方,滋賀県長浜警察署で取調べを受けることになってしまった方はお早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
「卑わいな言動」で迷惑防止条例違反
「卑わいな言動」で迷惑防止条例違反
「卑わいな言動」で迷惑防止条例違反となったケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県米原市のAさんは,滋賀県米原市内の路上を走行中のバス車内で,後ろに座っていた20代の女性客であるVさんに対し,「1万円でパンツを売ってください」という文面を表示させたスマートフォンの画面を見せました。
Vさんが嫌がっているにも関わらずAさんがそうした行為を続けたため,Vさんはバスの運転手に被害を申し出ました。
バスの運転手が滋賀県米原警察署に通報し,Aさんは滋賀県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)で滋賀県米原警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~迷惑防止条例違反(卑わいな言動)~
迷惑防止条例は,各都道府県が定めている条例で,市民に迷惑を与える様々な行為を禁止し,罰則を定めたものです。
滋賀県の場合,滋賀県迷惑行為等防止条例という迷惑防止条例が定められています。
この迷惑防止条例では,性犯罪についても規定があります。
迷惑防止条例で取り締まられている性犯罪の代表的なものは痴漢や盗撮などですが,都道府県によっては,迷惑防止条例で痴漢や盗撮以外の性犯罪として,公共の場所での「卑わいな言動」を禁止し,罰則を設けているところもあります。
滋賀県の場合,公共の場所での卑わいな言動を行った場合,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます(滋賀県迷惑防止条例3条1項3号,同条例11条1項1号)。
なお,常習として「卑わいな言動」行った場合には,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(滋賀県迷惑防止条例11条2項)。
滋賀県迷惑防止条例3条1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
2号 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
滋賀県迷惑防止条例11条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
1号 第3条の規定に違反した者
滋賀県迷惑防止条例11条2項
常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
この迷惑防止条例に定められている「卑わいな言動」についてですが,ある言動が「卑わいな」ものといえるか否かは,行為者の主観的意図によらず,その言動を客観的に見て,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらなものといえるかどうかにより決すべきと解されています。
このような観点から今回のAさんの行為について見ると,「1万円でパンツを売ってください」と表示された画面をしつこくVさんに見せることは,卑わいな言動に当たるといえそうです。
迷惑防止条例違反というと,痴漢や盗撮のイメージが強いかもしれませんが,このような「卑わいな言動」でも迷惑防止条例違反として刑事事件になりうるのです。
卑わいな言動による迷惑防止条例違反事件の依頼を受けた弁護士の活動としては,卑わいな言動をしてしまったことについて争いがない場合には,被害者に謝罪と賠償を行い,示談交渉をしていくことが考えられます。
弁護士が被害者と交渉し早期に示談が成立すれば,不起訴処分によって前科がつかずに済む可能性もあります。
性犯罪事件では,被害者の処罰感情や恐怖が強いことも多く,当事者が直接謝罪や示談交渉をすることが難しいです。
第三者であり専門家である弁護士に依頼し,示談交渉をするのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,卑わいな言動による迷惑防止条例違反事件のご相談も受け付けています。
そもそも自分の言動が「卑わいな言動」に当たるのかどうか,当たるとしてどういった弁護活動が可能なのか,弁護士に相談してみましょう。
お問い合わせは0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
宝くじの当たりくじ偽造で詐欺・有価証券偽造等事件④
宝くじの当たりくじ偽造で詐欺・有価証券偽造等事件④
宝くじの当たりくじ偽造で詐欺・有価証券偽造等事件となったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、年末に抽選の行われる宝くじを購入しました。
そして当選番号の発表日、Aさんが当選番号を確認すると、自分の購入した外れの宝くじと3等の当たりくじの番号が1つだけ違っていました。
そこでAさんは、「当選番号をごまかせれば当たりくじということにして当選金をもらえるかもしれない」と思いつき、自分の持っている宝くじの番号部分を当選番号に書き換え、X銀行へ持っていくと当選金への換金を要求しました。
しかし、受け付けた銀行員が宝くじの番号部分が通常の宝くじと異なっていることに気づき、滋賀県彦根警察署に通報。
駆け付けた警察官により、Aさんは有価証券偽造等・同行使罪と詐欺未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・牽連犯
ここで、前回までの記事で取り上げていた有価証券偽造罪もしくは有価証券変造罪、ここまで見てきた偽造有価証券行使罪もしくは変造有価証券行使罪、詐欺未遂罪の関係について考えてみましょう。
Aさんは、先述したように外れの宝くじを当たりくじのように改ざんし、当たりくじであると思わせることで当選金を受け取ろうと考えていました。
ですから、有価証券偽造罪もしくは有価証券変造罪にあたる行為=外れの宝くじを当たりくじのように改ざんする行為は、偽造有価証券行使罪もしくは変造有価証券行使罪にあたる行為=改ざんした宝くじを銀行に当選金との交換で引き渡すために使用するための行為であるといえます。
さらに、偽造有価証券行使罪もしくは変造有価証券行使罪にあたる行為は、詐欺未遂罪にあたる行為=銀行に当たりくじだと偽って当選金をだまし取ろうとする行為のための行為であるといえます。
つまり、Aさんの事例では、有価証券偽造罪もしくは有価証券変造罪は、偽造有価証券行使罪もしくは変造有価証券行使罪を犯すための手段であり、偽造有価証券行使罪もしくは変造有価証券行使罪は詐欺未遂罪を犯すための手段であるといえるのです。
このように、複数の犯罪にあたる行為をしたとき、それぞれが手段と目的の関係に立っていることがあります。
こうした場合、「牽連犯」という考え方によって下される刑罰の重さが決まります。
牽連犯については、刑法54条後段に規定があります。
刑法54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
今回のAさんの事例で考えると、それぞれの犯罪の法定刑は以下のようになります。
有価証券偽造罪もしくは有価証券変造罪:3月以上10年以下の懲役
偽造有価証券行使罪もしくは変造有価行使罪:3月以上10年以下の懲役
詐欺未遂罪:10年以下の懲役
これらを比較すると、「3月以上10年以下の懲役」が最も重い刑罰となるため、Aさんがこれらの犯罪で有罪となった場合には、この範囲で刑罰が決められるということになるでしょう。
宝くじ改ざんによる刑事事件では、このように複数の犯罪の絡む事態となりかねません。
複数の犯罪が成立する場合、それらがどのような関係にあるのか、どういった事情で起こったものなのか等を検討しなければ、見通しを立てたり対策したりすることも難しくなってしまいます。
その検討を一般の方だけで行うのは困難だと思いますので、複数の犯罪が成立する刑事事件に関わってしまった時にはすぐに弁護士に相談し、見通しを聞いてみることをおすすめいたします。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お申込みを受け付けております。
専門スタッフが丁寧に案内いたしますので、まずは遠慮なくお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
宝くじの当たりくじ偽造で詐欺・有価証券偽造等事件③
宝くじの当たりくじ偽造で詐欺・有価証券偽造等事件③
宝くじの当たりくじ偽造で詐欺・有価証券偽造等事件となったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、年末に抽選の行われる宝くじを購入しました。
そして当選番号の発表日、Aさんが当選番号を確認すると、自分の購入した外れの宝くじと3等の当たりくじの番号が1つだけ違っていました。
そこでAさんは、「当選番号をごまかせれば当たりくじということにして当選金をもらえるかもしれない」と思いつき、自分の持っている宝くじの番号部分を当選番号に書き換え、X銀行へ持っていくと当選金への換金を要求しました。
しかし、受け付けた銀行員が宝くじの番号部分が通常の宝くじと異なっていることに気づき、滋賀県彦根警察署に通報。
駆け付けた警察官により、Aさんは有価証券偽造等・同行使罪と詐欺未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・偽造・変造した宝くじを使うと…
今回のAさんは、偽造もしくは変造した宝くじを換金しようと考えており、実際に銀行に当たりくじであるとして当選金と交換するよう要求しています。
これは、偽造もしくは変造した宝くじを使用していることになると考えられるため、Aさんには偽造有価証券行使罪もしくは変造有価証券行使罪が成立すると考えられます。
・偽造・変造した宝くじで当選金を要求すると…
さらに、Aさんはその改ざんした宝くじを利用して、いうなれば当選金をだまし取ろうと考えていたわけですから、この行為に詐欺罪が成立すると考えられます(ただし、今回の事例ではAさんのたくらみは途中で発覚してしまっており、当選金をだまし取るまではいかなかったので、詐欺未遂罪が成立することになります。)。
刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法250条(未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
詐欺罪のいう「人を欺いて」とは、財物を引き渡させる際にその物を引き渡すかどうか判断するための重要な事項を偽ることであるとされています。
すなわち、その事項が嘘であったなら相手は財物を引き渡さなかった、という事項を偽ることで詐欺罪の「人を欺」くことになるのです。
これを偽って相手をだまし、相手がその嘘を信じたことで財物を引き渡す判断を行い、財物を引き渡す(=「財物を交付させた」)ことで詐欺罪が成立します。
そして詐欺罪には刑法250条に未遂罪の規定がありますから、詐欺罪の実行に取り掛かっていたものの最終的に財物を引き渡させるまではいかなかった場合には、詐欺未遂罪が成立します。
一般に、詐欺罪の実行に取り掛かったといえるタイミングは、「人を欺」く行為を始めたタイミングであるとされています。
今回のAさんは、自分で改ざんした本当は外れくじである宝くじを当たりくじであると偽って銀行に当選金を要求しています。
当然、銀行としては当たりくじであるから当選金という財物を相手に渡すわけですから、本来外れの宝くじであるはずのくじであると分かっていれば当選金を相手に引き渡すことはしないでしょう。
ですから、Aさんの改ざんした宝くじを当たりくじであると偽って当選金を要求する行為は、詐欺罪の「人を欺」く行為であると考えられます。
しかし、Aさんのケースでは、銀行員が宝くじの改ざんに気づいたことから、当選金をだまし取ることなくAさんの逮捕に至っています。
このことから、Aさんには詐欺未遂罪が成立すると考えられるのです。
宝くじの改ざん行為だけでなく、その改ざんした宝くじを使用した行為や、宝くじを使用して当選金をだまし取ろうとした行為にも、それぞれ犯罪が成立してしまうことがわかっていただけたと思います。
刑事事件では、このようにそれぞれの犯罪のことをそれぞれ意図していなくても複数の犯罪が成立する場合もあります。
刑事事件の被疑者となってしまった、ご家族が何らかの刑事事件で逮捕されてしまった、という場合には、速やかに弁護士に相談し、どういった犯罪が成立しうるのか、どういった見通しになるのか相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間いつでも弊所弁護士によるサービスのお問い合わせ・お申込みが可能ですから、まずはお気軽にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
宝くじの当たりくじ偽造で詐欺・有価証券偽造等事件②
宝くじの当たりくじ偽造で詐欺・有価証券偽造等事件②
宝くじの当たりくじ偽造で詐欺・有価証券偽造等事件となったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、年末に抽選の行われる宝くじを購入しました。
そして当選番号の発表日、Aさんが当選番号を確認すると、自分の購入した外れの宝くじと3等の当たりくじの番号が1つだけ違っていました。
そこでAさんは、「当選番号をごまかせれば当たりくじということにして当選金をもらえるかもしれない」と思いつき、自分の持っている宝くじの番号部分を当選番号に書き換え、X銀行へ持っていくと当選金への換金を要求しました。
しかし、受け付けた銀行員が宝くじの番号部分が通常の宝くじと異なっていることに気づき、滋賀県彦根警察署に通報。
駆け付けた警察官により、Aさんは有価証券偽造等・同行使罪と詐欺未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・宝くじの「偽造」と「変造」
前回の記事では、Aさんの宝くじ改ざん行為が有価証券偽造等罪にあたる可能性があること、宝くじが有価証券偽造等罪の「有価証券」であることに触れました。
刑法162条1項(有価証券偽造等罪)
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
今回の記事では、まず、有価証券偽造罪の「偽造」がどういった行為を指すのか確認しましょう。
一般に「偽造」という言葉は「偽物を作る」という意味合いでとらえられますが、有価証券偽造罪の「偽造」といえるためには、実は細かい条件があります。
有価証券偽造罪の「偽造」は、その有価証券を作成する権限のない者が他人の作成名義を無断で不正に使用し、正しい有価証券のような証券を作ることを指します。
また、「偽造」は外観上一般人に正しい有価証券であると信じさせる程度である必要があります。
ですから、一目見て偽物の有価証券であると分かるようなものを作っても、有価証券偽造罪の「偽造」をしたことにはなりません。
つまり、単に偽物を作ったからといって必ずしも有価証券偽造罪のいう「偽造」になるとは限らないのです。
さらに、有価証券偽造行為と同じく、刑法162条で禁止されている行為として、有価証券の「変造」行為が挙げられます。
「変造」とは、正しく成立している他人名義の有価証券に、権限がないにも関わらず変更を加えることを指します。
ただし、このうち、変更を加えたことでその有価証券の本質的部分に変動が生じ、その同一性が失われた時には「変造」ではなく「偽造」であると判断されます。
有価証券を「変造」した場合も、有価証券変造罪として有価証券偽造罪と同様に罰せられることになります。
今回のAさんの宝くじに関して考えてみましょう。
今回のAさんは、自分が購入した外れの宝くじの番号を変えることで、外れくじを当たりくじに見せかけています。
Aさんが番号を書き換えた宝くじ自体は、元々購入した宝くじですから、宝くじを販売している銀行が発行した物であり、名義もその銀行のものでしょう。
したがって、Aさんが書き換えた宝くじ自体は、正しく成立している他人名義の有価証券であるということになるでしょう。
ですから、Aさんはその正しく成立している他人名義の有価証券に、権限がないにもかかわらず番号の書き換えという変更を加えたことになります。
このことから、Aさんは少なくともAさんは宝くじ=有価証券の変造は行っているだろうと考えられます。
後はこの番号の書き換えによって外れくじを当たりくじとしたことが、宝くじの本質的部分に変動が生じてその同一性が失われたと判断されるかどうかによって、有価証券偽造罪となるか有価証券変造罪となるかが決まるということになるでしょう。
過去の裁判例では、8等の当たりくじを1等の当選番号に改ざんした行為は有価証券変造行為であると認められた事例も見られますが、今回のように外れくじを当たりくじに改ざんした場合どのような判断になるのかは、事例に即し、これまでの裁判例などを検討しながら考えることになるでしょう。
「偽造」や「変造」など、刑事事件では専門用語も多く使われています。
さらにその言葉について法律の条文に詳しく書いてあるわけではなく、それまでの裁判例等から解釈がされていますから、刑事事件については専門家である弁護士に相談することが望ましいといえるでしょう。
滋賀県の刑事事件にお困りの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
宝くじの当たりくじ偽造で詐欺・有価証券偽造等事件①
宝くじの当たりくじ偽造で詐欺・有価証券偽造等事件①
宝くじの当たりくじ偽造で詐欺・有価証券偽造等事件となったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、年末に抽選の行われる宝くじを購入しました。
そして当選番号の発表日、Aさんが当選番号を確認すると、自分の購入した外れの宝くじと3等の当たりくじの番号が1つだけ違っていました。
そこでAさんは、「当選番号をごまかせれば当たりくじということにして当選金をもらえるかもしれない」と思いつき、自分の持っている宝くじの番号部分を当選番号に書き換え、X銀行へ持っていくと当選金への換金を要求しました。
しかし、受け付けた銀行員が宝くじの番号部分が通常の宝くじと異なっていることに気づき、滋賀県彦根警察署に通報。
駆け付けた警察官により、Aさんは有価証券偽造等・同行使罪と詐欺未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・宝くじは「有価証券」
本日は大晦日です。
まさに年の瀬、年末といった時期ですが、この時期、高額当選を夢見て宝くじを購入したという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の事例は、その宝くじに関わる刑事事件です。
Aさんの行為がそれぞれどういったことから有価証券偽造等・同行使罪・詐欺未遂罪に問われることになるのか、詳しく見ていきましょう。
今回の事例のAさんは、自分の購入した宝くじと当たりくじの番号が近いことをいいことに、自分の購入した外れの宝くじの番号部分を書き換え、当たりくじのようにしています。
まず、この行為が刑法の有価証券偽造等罪となる可能性があります。
有価証券偽造等罪は刑法162条に規定されており、さらにその偽造された有価証券を使った場合には、刑法163条に規定されている偽造有価証券行使等罪が成立することになります。
刑法162条1項(有価証券偽造等罪)
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
刑法163条1項(偽造有価証券行使等罪)
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
まず、有価証券偽造等罪のいう「行使の目的で」とは、文字通りその偽造した有価証券を使う目的で、ということです。
つまり、使う目的なく有価証券を偽造したとしても、有価証券偽造等罪には当たらないということになります。
今回のAさんで考えれば、宝くじを当たりくじに見せかけて換金しようとしていますから、当たりくじのように改ざんした宝くじを当たりくじのように使用する目的があったということになるでしょう。
では、有価証券偽造等罪の客体である「有価証券」とはどういったものを指すのでしょうか。
条文上では、「公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券」とされていますが、「公債証書、官庁の証券、会社の株券」についてはあくまで「有価証券」の例示であり、これに当てはまらないからといって「有価証券」ではないということではありません。
「その他の有価証券」については法律で具体的に決められているわけではなく、解釈にゆだねられています。
過去の判例では、「有価証券」は「財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につきその証券の占有を必要とするものでなければならない」と解釈されています(最判昭和32.7.25)。
ここで、宝くじが有価証券偽造等罪のいう「有価証券」にあたるのかどうか考えてみましょう。
宝くじは、当たっていれば当選金を受け取ることができ、宝くじにはその旨が記載されています。
当選金を受け取れる(請求できる)権利は「財産上の権利」ですから、宝くじには「財産上の権利が証券に表示され」ていることになります。
そして、宝くじの当選金を受け取る権利の行使をするためには、その宝くじを自分が支配・管理=占有していなければいけません。
つまり、宝くじは「財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につきその証券の占有を必要とするもの」であるといえることから、有価証券偽造等罪のいう「有価証券」にあたると考えられるのです。
過去の判例でも、宝くじは有価証券偽造等罪の「有価証券」にあたると解されています(最決昭和33.1.16)。
「有価証券」という言葉と宝くじはなかなか結び付きにくいところですが、このように「有価証券」にあたると考えられているのです。
このように、刑事事件では、法律に決められている言葉に実際の物が該当するのかどうか判断するにも、知識や経験が要求されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
複雑な犯罪や刑事事件にお困りの際にも、刑事事件・少年事件専門の弁護士だからこそ安心してご相談いただけます。
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
被害者をだましたのに窃盗事件?③
被害者をだましたのに窃盗事件?③
被害者をだましたのに窃盗事件として検挙されたケースで、特に家庭裁判所に進んでからの釈放を求める活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県東近江市に住んでいる高校生のAくん(17歳)は、高校が冬休みに入ることから、冬休みに稼げるアルバイトはないかとアルバイトを探していました。
すると高校の先輩であるBさんから、「簡単に稼げるアルバイトがある」と伝えられ、Bさんの伝手でそのアルバイトをすることになりました。
Aさんがそのアルバイトの詳細を聞いたところ、お年寄りの家に行って銀行員を装い、キャッシュカードと暗証番号を封筒に入れさせたうえでその封筒と自分の用意した偽物の封筒を隙を見てすり替え、すり替えたキャッシュカードと暗証番号を使用して金を引き出すというものでした。
Aさんは、「よくニュースで見る犯罪だ」と思ったものの、「冬休みの短い間だけで何十回もやるわけではないからばれないだろう」と考え、そのアルバイトをすることにしました。
しかしアルバイトをしてから数日後、滋賀県東近江警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、警察官から「窃盗罪の容疑で息子さんを逮捕します」としか聞かせてもらえず、困って弁護士に相談しました。
その後、弁護士から事件のあらましを聞いたAさんの両親は、「被害者の方をだましているのに窃盗罪なのはどうしてなのか」と疑問に重い、弁護士に詳しい説明を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年の窃盗・詐欺事件で釈放を求める~家裁に進んでから
捜査が終了した少年事件は、原則としてすべての少年事件が家庭裁判所へ送られます。
逮捕・勾留による身体拘束を受けている少年は、身体拘束されたまま家庭裁判所に事件とともに送られることになります。
そしてその後、観護措置という手続きを取るかどうか家庭裁判所が判断し、観護措置を取るべきであると判断された場合にはさらに引き続いて身体拘束を受けることになります。
観護措置は、少年鑑別所に少年を収容したうえで少年の資質や環境などを専門家が調べるという少年事件特有の手続きです。
この観護措置は、事件が家庭裁判所に送致されてからとられる手続きであり、成人の刑事事件には存在しない手続きです。
逮捕・勾留を伴う少年事件では、家庭裁判所に送致されそのまま観護措置が取られるということも多いです。
今回のAさんの場合、知人たちと一緒になって詐欺まがいの窃盗事件を起こしてしまっていることから、Aさんの素行や環境に問題がなかったか調査する必要性があると判断されることも考えられます。
観護措置は通常4週間程度とられることか多く、最大で8週間も少年鑑別所に入ることになる可能性もあります。
先述したように、少年事件の原因や対策に必要な調査をする手続きであるため、少年にとって全くマイナスな手続きであるわけではありませんが、それでも4週間身体拘束されるとなれば学校や就業先に大きな影響を及ぼしてしまいます。
こうした身体拘束からの釈放を目指す活動が、弁護士のできる活動の1つでしょう。
少年本人とそのご家族が、刑事事件・少年事件の専門家である弁護士と協力することによって、釈放の可能性を上げることができます。
もちろん、釈放を求める活動が必ず功を奏すとは限りません。
前回の記事で触れたように、詐欺まがいの窃盗事件は共犯がいたり計画性があったりすることから、なかなか釈放が難しい事件です。
そうであったとしても、釈放を求めていくと同時に、釈放されなかったとしても取調べや調査に不本意な対応をしてしまわないよう、最終的にその少年に適切な処分を獲得できるよう、随時アドバイスを受けることは大切ですから、弁護士への相談・依頼は重要なことであるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、逮捕・勾留を伴う少年事件のご相談・ご依頼にも対応しています。
子どもが窃盗事件・詐欺事件に関わってしまった、逮捕されたと聞いたがどうしたらいいのか分からない、という場合にもすぐにお問い合わせいただけます(0120-631-881)。
まずはお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
被害者をだましたのに窃盗事件?②
被害者をだましたのに窃盗事件?②
被害者をだましたのに窃盗事件として検挙されたケースで、特に捜査段階の釈放を求める活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県東近江市に住んでいる高校生のAくん(17歳)は、高校が冬休みに入ることから、冬休みに稼げるアルバイトはないかとアルバイトを探していました。
すると高校の先輩であるBさんから、「簡単に稼げるアルバイトがある」と伝えられ、Bさんの伝手でそのアルバイトをすることになりました。
Aさんがそのアルバイトの詳細を聞いたところ、お年寄りの家に行って銀行員を装い、キャッシュカードと暗証番号を封筒に入れさせたうえでその封筒と自分の用意した偽物の封筒を隙を見てすり替え、すり替えたキャッシュカードと暗証番号を使用して金を引き出すというものでした。
Aさんは、「よくニュースで見る犯罪だ」と思ったものの、「冬休みの短い間だけで何十回もやるわけではないからばれないだろう」と考え、そのアルバイトをすることにしました。
しかしアルバイトをしてから数日後、滋賀県東近江警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、警察官から「窃盗罪の容疑で息子さんを逮捕します」としか聞かせてもらえず、困って弁護士に相談しました。
その後、弁護士から事件のあらましを聞いたAさんの両親は、「被害者の方をだましているのに窃盗罪なのはどうしてなのか」と疑問に重い、弁護士に詳しい説明を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年の窃盗・詐欺事件で釈放を求める~捜査段階
今回のAさんが関わってしまったような詐欺まがいの窃盗事件や類似の詐欺事件では、Aさんのような学生がアルバイト感覚で関わってしまうケースも少なくありません。
冬休みや夏休みといった長期休暇でアルバイトに誘われ、軽い気持ちで関わってしまう少年もいます。
こうした窃盗事件・詐欺事件は組織的に行われていることも多く、逮捕されやすい被害者へ直接かかわる役割を学生のアルバイトに任せ、いわゆるとかげの尻尾切りのように利用している犯罪組織もあります。
こうしたアルバイトに関わらないことはもちろんですが、もしも関わってしまったら、弁護士にどのような活動をしてもらうことが考えられるのでしょうか。
まず、今回のAさんは逮捕されて滋賀県東近江警察署に留置されています。
少年事件の手続きが成人の刑事事件と異なると聞いたことのある方も多いかもしれませんが、捜査機関に捜査されるいわゆる被疑者の段階では、少年事件であっても成人の刑事事件と手続きが異なる点は多くありません。
少年事件であっても、逮捕されれば逮捕から48時間以内に釈放されるか検察官のもとへ送られるかが決められ、検察官へと送られる場合(いわゆる「送検」)には、そこからさらに24時間以内に勾留という逮捕より長期間の身体拘束をするよう請求するかどうかが決められます。
そして勾留を請求された場合、裁判所がその請求を認めれば、最大72時間に及ぶ逮捕から引き続いて、勾留というさらに長い期間の身体拘束がなされることになるのです。
勾留は、原則最大10日間であり、さらにそこから最大10日間の延長が認められています。
つまり、逮捕を伴う少年事件では、捜査段階において、逮捕から合わせると最大で23日間身体拘束される可能性があるということになります。
例えば、今回のAさんは、複数人で詐欺まがいの窃盗事件を起こしています。
前述したように、こうした手口の詐欺事件や窃盗事件では、役割分担が行われ、組織的に犯行が行われていることが多いです。
ニュース番組などでも「詐欺グループが逮捕された」というような報道が多くなされています。
このように複数人が関わる犯罪、いわゆる共犯者のいる犯罪では、仲間内での口裏合わせなどで証拠隠滅されるおそれがあると考えられて逮捕・勾留される可能性が高く、なかなか釈放されないケースが多いです。
さらに、複数件の詐欺事件や窃盗事件に関わっている場合には、理論上関わっている詐欺事件・窃盗事件の数だけ逮捕・勾留される可能性がありますから、被疑者として取調べられる捜査段階だけでも長期に渡る身体拘束を受ける可能性が高まってしまうのです。
捜査段階で釈放を求めていくためには、先ほど挙げた勾留までの流れの中で、勾留を求めるかどうか判断する検察官や勾留請求を認めるかどうか判断する裁判官に対し、釈放を主張していくことが考えられます。
しかし、読んでいただければわかるように、逮捕されてから勾留が決定されるまでは、最大でも72時間しか時間がありません。
事件の状況などにもよりますが、最大72時間とされているだけで、手続きの進行が早ければ、2日程度で逮捕から勾留までが決まってしまうこともあります。
勾留が決定してからでも不服申し立てをすることはできますが、この不服申し立ても1回の勾留につき1回しかできません。
釈放を求める機会を少しでも多く確保するためには、逮捕から早い段階で弁護士に釈放を求める活動をしてもらうことが重要です。
通常の成人の刑事事件であれば、この最大23日間の身体拘束ののち、起訴・不起訴が判断され、起訴されて勾留が続く場合には保釈という手続きを取ることができます。
しかし、少年事件の場合、ここから成人の刑事事件とは異なる手続きが入ってきます。
それが「観護措置」という手続きです。
こちらについては、次回の記事で取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕後から迅速に弁護士へご相談いただけるよう、初回接見サービスのお申込みを24時間いつでも行っています(0120-631-881)。
詐欺事件や窃盗事件でお子さんが逮捕されてしまった、子どもの逮捕の連絡に不安を感じている、という場合には、遠慮なくお早めにお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。