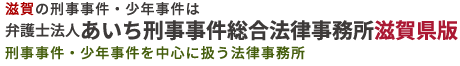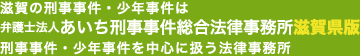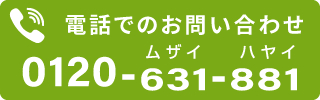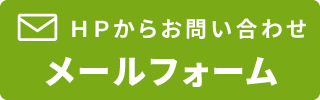Author Archive
加重収賄事件で逮捕・取調べ②冤罪・無罪を主張
加重収賄事件で逮捕・取調べ②冤罪・無罪を主張
加重収賄事件で逮捕・取調べを受けるケースで,特に冤罪・無罪を主張する場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県米原市在住のAさんは,滋賀県米原市役所で建設部参事をしていました。
ある日,Aさんは,滋賀県米原市役所の庁舎の改修工事を行う際,業者に設計価格を教えた見返りに賄賂を受けたとして,加重収賄罪の容疑で滋賀県米原警察署の警察官に逮捕されました。
しかし,Aさんには身に覚えがなく,取調べにどのように対応すべきか分からず困っています。
こうした現状を知ったAさんの家族は,どうにかAさんのサポートをすることはできないかと,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~加重収賄事件で冤罪・無罪を主張したい~
加重収賄罪で捜査を受け,刑事事件化した場合,弁護士に依頼して取調べの対応について助言をもらうべきです。
加重収賄事件では,刑事事件化した場合,被害者がいない上,第三者の供述証拠等も得にくいことから,捜査の中心は被疑者を取調べ,自白を獲得することが考えられます。
収賄をした側と贈賄をした側の当事者同士の供述が重要となりますから,仮にその当事者同士の供述で食い違い部分が出てくれば,その部分を厳しく追及されることになるでしょう。
冤罪や無罪を主張する否認事件の場合,捜査段階で自分の主張とは違う自白をしないようにすることが重要です。
加重収賄事件の弁護の依頼を受けた弁護士は,被疑者に対して取調べ対応について助言するとともに,こまめに接見し,取調べの様子を聞き取ることになるでしょう。
そうすることで,取調べの状況を把握し,より的確なアドバイスができるとともに,不本意な供述を証拠とされないよう注意して取調べに臨む手助けができます。
不本意な供述をしてしまったり,違法な捜査によって自白を取られてしまったりしても,裁判でその旨を主張することはできますが,その主張が認められることは非常に難しいため,特に冤罪や無罪を主張していく否認事件の場合には,捜査段階から弁護士のサポートを受けながら気を付けておくことが大切です。
なお,もしも自白を強要された場合,弁護士は,そのような自白調書は違法に収集した証拠であり,裁判では証拠にできないと主張していくことになるでしょう。
また,収賄事件の場合,贈賄をした側の事件関係者がいること等から,容疑をかけられた場合には逮捕・勾留される可能性が高いといえます。
冤罪や無罪を主張して容疑を否認している場合には,さらに証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されやすいとも言われていますから,こうした身体拘束からの釈放を目指す活動も重要となってくるでしょう。
弁護士は,捜査段階では勾留阻止等の釈放を目指す活動を,起訴後には保釈請求をすることで保釈を求める活動をすることになると考えられます。
自分のしたい主張をきちんとし続けるためにも,釈放され,ストレスの少ない状態で取調べや裁判に臨むことが望ましいでしょうから,こうした活動もまた重要なものとなります。
収賄事件は,前回の記事でも取り上げた通り,その態様によって成立する犯罪名が異なることもあり,非常に複雑です。
そうした刑事事件で逮捕されて身体拘束をされ,1人で冤罪や無罪を主張していくことは負担が大きいことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が逮捕直後から裁判までフルサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
加重収賄事件で逮捕・取調べ①収賄罪
加重収賄事件で逮捕・取調べ①収賄罪
加重収賄事件で逮捕・取調べを受けるケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県米原市在住のAさんは,滋賀県米原市役所で建設部参事をしていました。
ある日,Aさんは,滋賀県米原市役所の庁舎の改修工事を行う際,業者に設計価格を教えた見返りに賄賂を受けたとして,加重収賄罪の容疑で滋賀県米原警察署の警察官に逮捕されました。
しかし,Aさんには身に覚えがなく,取調べにどのように対応すべきか分からず困っています。
こうした現状を知ったAさんの家族は,どうにかAさんのサポートをすることはできないかと,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~加重収賄罪~
公務員が職務に関し,賄賂を収受し,又はその要求もしくは約束をした場合には,収賄罪(刑法197条1項)が成立します。
さらに,公務員が収賄罪を犯し,よって不正な行為をした場合には加重収賄罪(刑法197条の3第1項)が成立し,1年以上の有期懲役が科せられます。
刑法197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
1項 公務員が,その職務に関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,5年以下の懲役に処する。
この場合において,請託を受けたときは,7年以下の懲役に処する。
2項 公務員になろうとする者が,その担当すべき職務に関し,請託を受けて,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,公務員となった場合において,5年以下の懲役に処する。
刑法197条の3(加重収賄及び事後収賄)
1項 公務員が前二条の罪を犯し,よって不正な行為をし,又は相当の行為をしなかったときは,1年以上の有期懲役に処する。
2項 公務員が,その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し,賄賂を収受し,若しくはその要求若しくは約束をし,又は第三者にこれを供与させ,若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも,前項と同様とする。
3項 公務員であった者が,その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,5年以下の懲役に処する。
収賄罪の類型は,刑事事件の中でも重い部類です。
収賄罪の条文に書かれている「賄賂」とは,公務員の職務行為の対価として収受される不正な利益をいいます。
賄賂は,一定の職務に対する対価であれば足り,個別具体的な職務行為との間の対価関係までは不要と解されています。
賄賂の目的物は,財物に限らず,有形・無形を問わず,人の需要・欲望を満たすに足りる一切の利益を含みます。
つまり,現金を賄賂として受け取ることはもちろん,プレゼントをもらったり食事を奢ってもらったり,ということでも収賄罪のいう賄賂になりえます。
ですから,例えば今回の事例のAさんは,加重収賄罪の容疑に見に覚えがないとしていますが,これが「現金を受け取っていない」程度の認識であり,他の形で賄賂を受け取ってしまっており,実際には加重収賄罪を犯してしまっている可能性もあるということになります。
そして,収賄罪の条文にあるように,「職務に関し」といえるためには,公務員の職務行為と賄賂が対価関係に立つことが必要です。
賄賂と対価関係に立つべき職務とは,公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務いうと解されています。
公務員の職務は法令上認められるものですが,公務員がその任務達成のため公務員の立場で行う行為が含まれ,その範囲は法令全体の趣旨により決せられます。
また,収賄罪が成立するためには,職務と賄賂が対価関係に立つだけではなく,行為者にその認識が必要です。
さらに,加重収賄罪は公務員が収賄罪を犯し,「不正な行為」をしたときに成立しますが,この「不正な行為」とは,職務に反する一切の行為をいうとされています。
例えば,今回のAさんの事例で言えば,Aさんが職務上知り得た情報で,さらには守秘義務等で外部に漏らしてはいけないはずの設計価格という情報を漏らしたとされる行為が本当であれば,Aさんの職務上課される守秘義務等に違反する行為をしているといえます。
収賄行為をしてこの「不正な行為」をしていると考えられたために,今回Aさんは加重収賄罪の容疑をかけられているのでしょう。
こうした加重収賄罪の容疑で逮捕されてしまったら,見に覚えのない容疑で逮捕されてしまったら,どのような対応をしていけばよいのでしょうか。
次回の記事で詳しく取り上げていきます。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,加重収賄事件などの収賄事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
収賄事件は,世間の関心・注目度の高い刑事事件となることが多く,逮捕されてしまうとご本人だけでなくご家族も大きな不安を抱えることになります。
そんな時こそ,専門家である弁護士にサポートしてもらいましょう。
まずはお気軽に,お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
パパ活から児童買春事件に
パパ活から児童買春事件に
パパ活から児童買春事件になってしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県東近江市に住んでいるAさん(40代男性)は、マッチングアプリを利用し、「パパ活相手募集中」とプロフィールに書いていたVさん(16歳)と連絡を取り合い、直接会う仲になりました。
VさんのプロフィールにはVさんの年齢も書いてありましたが、Aさんは「ただ会って食事や買い物をするだけなのだから未成年でも問題ないだろう」と考えていました。
しかし、何度かVさんと会ううち、AさんはVさんに性交を打診するに至りました。
Vさんから「5万円でいいよ」と返事があったことから、それ以降、AさんはVさんと会った際には5万円を支払ってVさんと性交していました。
するとある日、Aさんの自宅に滋賀県東近江警察署の警察官がやってきて、Aさんは児童買春をした容疑で逮捕されてしまいました。
どうやら、Vさんが別のパパ活相手をパパ活をしているところを補導され、そこからAさんとの関係が発覚し、捜査の手が伸びたようでした。
(※この事例はフィクションです。)
・パパ活
パパ活とは、主に女性が男性と食事をしたりデートのようなことをしたりする代わりに、金銭やプレゼントなどをもらう行為のことを指しています。
パパ活の多くは、若い女性が経済的に余裕のある中高年層の男性を相手にしている活動であることから、「婚活」などに寄せて「パパ活」と呼ばれているということのようです。
基本的には、このパパ活自体は犯罪ではありません。
ただし、今回のAさんの事例などのように、パパ活は事情によっては犯罪になりうる、犯罪に巻き込まれうる行為でもあることに注意が必要です。
・パパ活と児童買春事件
先ほど触れたように、パパ活は若い女性が行っていることも多く、SNSやマッチングアプリを利用すれば未成年でもパパ活ができてしまいます。
こうしたことから、Vさんのような未成年者がパパ活をしていることもあります。
常識的な時間に食事をする程度であれば、何か問題が起こることはないかもしれませんが、対価を支払って性交をするとなると話は変わります。
「パパ活」の範囲内だと思っていたとしても、その行為は児童買春となってしまうからです。
児童買春は、児童買春・児童ポルノ禁止法(正式名称:「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)で規制されている犯罪行為です。
児童買春・児童ポルノ禁止法4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春・児童ポルノ禁止法では、「児童買春」は以下のように定義されています。
児童買春・児童ポルノ禁止法2条
1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
今回の事例では、Aさんは5万円を支払う約束で16歳=「児童」であるVさんと性交しているのですから、この児童買春に当たることになり、児童買春・児童ポルノ禁止法違反という犯罪になるのです。
今回の事例のように、パパ活の延長から児童買春事件に発展してしまう事例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件のご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
MDMA所持で逮捕されたら
MDMA所持で逮捕されたら
MDMA所持の容疑で逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県近江八幡市に住んでいるAさんは、報道番組で芸能人がMDMA所持の容疑で逮捕されたというニュースを見ました。
Aさんは、以前からMDMAに興味を持っていましたが、その報道内で、逮捕された芸能人がSNSを利用してMDMAを手に入れていたことを知ると、「自分もSNSを使えばMDMAを手に入れられるかもしれない。何回も繰り返さなければバレないだろう」と考え、SNSを通じてMDMAを譲り受けることにしました。
しかし、AさんがMDMAを購入して手に入れた矢先、MDMAを購入した先の売人が逮捕されたことでAさんにも捜査の手が伸び、Aさんの自宅に滋賀県近江八幡警察署の警察官が家宅捜索に訪れました。
その捜索によって、Aさんの所持していたMDMAが発見され、Aさんはそのまま逮捕されてしまいました。
Aさんは、「まだ使ってもいないのに逮捕されてしまうのか」と驚き、家族の依頼でやってきた弁護士に今後の対応を相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・MDMA
MDMAとは、合成麻薬の一種で、麻薬取締法で所持や使用が禁止されている違法薬物です。
最近では、MDMAの所持や使用による芸能人の逮捕も報道され、報道でMDMAという違法薬物の存在を知ったという方もいるかもしれません。
MDMAの見た目はカラフルでキャラクターなどが模されていることもある、かわいらしい錠剤になっています。
そうしたことから、一見してそれがMDMAという違法薬物であるということが分かりにくくなっています。
その見た目や、幸福感や社交性などが増幅され、いわゆる「ハイ」な状態になる効力などから、MDMAは若者の間で使われることが多いとも言われており、パーティードラッグとして流通しているとも言われています。
「痩せる薬」「疲労回復に効果がある」「眠くならない」といった効果をうたってMDMAを勧めてくる売人もいるようです。
ですが、MDMAの使用は、場合によっては死亡してしまうほどの重度の中毒症状を引き起こすこともある危険な行為であることに注意が必要です。
・MDMAは所持するだけでも犯罪
先ほど触れたように、MDMAは所持しているだけ、持っているだけでも犯罪となります。
Aさんのようにたとえ使用していなくとも犯罪になりますし、他人のMDMAをMDMAだと分かりながら預かっていたような場合にも犯罪になります。
MDMAの所持については、麻薬取締法(正式名称「麻薬及び向精神薬取締法」)で以下のように決められているのです。
麻薬取締法66条
1項 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。
麻薬取締法の条文で出てくる「ジアセチルモルヒネ」とは、いわゆる「ヘロイン」のことを指します。
つまり、この麻薬取締法66条では、ヘロイン以外の麻薬の所持等を規制しているということになり、MDMAはまさにそのヘロイン以外の麻薬ですから、この条文によって所持が規制されているのです。
条文を見てお分かりいただけるように、MDMAの所持と言っても、その目的が営利目的がどうかでも刑罰の重さは変わってきます。
今回のAさんは、自分の興味本位でMDMAを購入したようですから、営利目的であるとは考えにくいでしょう。
一方、誰かに売り渡そうと考えてMDMAを持っていたという場合には、営利目的であると判断され、より重い刑罰を受けることになると考えられます。
営利目的のMDMA所持なのかどうかは、所持していたMDMAの量や関係者とのやり取り等の事情を考慮され判断されます。
営利目的のMDMA所持とそうでないMDMA所持の場合では、先ほどの条文のように刑罰の重さも変わってきますから、もしも営利目的ではないのに営利目的でのMDMA所持を疑われてしまったら、その部分をきちんと否定していくための活動や対策も考えなければならないでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、MDMAに関連した刑事事件や逮捕についてのご相談も受け付けています。
逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスでは、逮捕直後から被疑者本人やそのご家族が弁護士のアドバイスを受けることが可能です。
ご家族・ご友人がMDMA所持で逮捕されてしまった、とお困りの際は、お早めにご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
名誉棄損事件で無料法律相談
名誉棄損事件で無料法律相談
名誉棄損事件で無料法律相談を受ける場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは,滋賀県甲賀市に本社があるV社の商品を購入するなど,そのサービスをよく受けていました。
しかし,ある日購入した商品が気に入らず,V社に問い合わせをしたAさんは,商品だけでなくV社の対応にも不満を持ち,「V社はひどい会社だ。ひどい仕打ちを受けたと広く知らしめてやりたい」と思うようになりました。
そこでAさんは,「V社の商品は欠陥品でそれを売りつけるV社はドロボーで詐欺師だ」「V社のいうことは嘘八百・でっちあげ」などと書いた看板を滋賀県甲賀市内のV社の近くの路上に多数設置しました。
それを見たV社は滋賀県甲賀警察署に通報し,被害届を出したことを公表しました。
Aさんは,報道でV社に対する名誉毀損事件の捜査が開始される見込みであることを知り,どうしてよいのか分からなくなり,ひとまず弁護士の無料法律相談を受けて今後の対応を考えてみることにしました。
(フィクションです。)
~名誉毀損罪~
公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した場合,名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立し,3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金が科せられます。
刑法230条1項
公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪の条文を見ると,その対象が「人」の名誉とされていることから,名誉毀損罪の被害者は個人でなければならないようにも見えます。
しかし,名誉毀損罪の被害者が個人でなく法人などの団体であっても名誉毀損罪は成立しますから(大判大正15年3月24日),今回のAさんの事例のような会社相手の名誉棄損事件も起こり得ることに注意が必要です。
名誉毀損罪のいう「公然」とは,摘示された事実を不特定又は多数の人が認識しうる状態をいいます(大判昭和6年6月19日)。
このうち,不特定とは,摘示の相手方が特殊な関係によって限定されていないことをいい,多数とは,単に複数であればよいのではなく,相当の多数であることをいいます。
そして,名誉毀損行為において摘示される事実は,それ自体として人の社会的名誉を低下させるような具体的事実であることが必要ですが,公知の事実でもよく,摘示された事実の真否も問いません。
また,摘示の方法は問わず,噂や風評・風聞の形をとっても構いません(大判昭和5年8月25日)。
なお,事実の公共性,目的の公共性,真実性の証明がなされた場合,免責が認められています(刑法230条の2)。
今回の事例のAさんは,滋賀県甲賀市内の路上に看板を設置し,通行する相当多数の者が看板を見られるようにしているので,公然と事実を摘示したといえるでしょう。
さらに,その看板の内容も,V社の商品やサービスを貶めるものであることから,V社の社会的名誉を低下させるような具体的事実であると判断される可能性があります。
名誉毀損罪の刑事事件として滋賀県甲賀警察署の警察官が捜査を開始するのも仕方がないといえるでしょう。
~名誉棄損事件を起こしてしまったら~
名誉毀損罪が成立することに争いがないのであれば,弁護士に依頼して示談をすべきでしょう。
弁護士は名誉棄損事件の依頼を受けた場合,被害者が告訴しないように,あるいは告訴を取り下げてもらうように交渉します。
名誉毀損罪は告訴がなければ起訴できない親告罪(刑法232条)だからです。
そして,被害者の方との間で示談が成立している,あるいは被害弁償も済んでいるという状態にできれば,その後の民事裁判(損害賠償請求訴訟など)も回避することができます。
名誉毀損罪の場合,裁判となれば,初犯であれば執行猶予判決が見込まれますが,その場合も前科となってしまいます。
前科をさけるためには,起訴される前に弁護士に依頼して示談をすることが有効です。
しかし,名誉毀損行為の態様等によっては,警察に逮捕されて取調べを受ける流れになることも考えられます。
今回のAさんの事件も,現在捜査が開始される見込みという段階のようですが,捜査が開始されれば逮捕されてしまう可能性も否定はできません。
逮捕されてしまえば弁護士に自由な時間に相談することはできませんし,自分の名誉毀損行為が刑事事件化している可能性があるのであれば,早い段階から弁護士に相談し,今後の対応について検討しておくべきといえるでしょう。
捜査機関へ自ら出頭することや,早期に被害者対応を開始することを含め,刑事事件の専門家に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件の初回無料法律相談を行っていますから,とりあえず弁護士の話を聞きたい,という方にもお気軽にご相談いただけます。
土日祝日も無料法律相談の受付を行っていますので,まずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
犯人隠避罪で逮捕されたら
犯人隠避罪で逮捕されたら
犯人隠避罪で逮捕されてしまったケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市に住んでいるAさんは,同棲している恋人であるBさんが滋賀県大津市の路上で飲酒運転をして事故を起こしたので,Bさんの身代わりに滋賀県大津警察署に出頭し,自分が交通事故を起こしたと述べました。
しかし,滋賀県大津警察署の捜査の結果,実際に交通事故を起こしたのはBさんであったことが発覚しました。
そして,Aさんのついていた嘘がばれ,Aさんはその場で犯人隠避罪の容疑で逮捕されました。
この逮捕を聞いたAさんの家族は,弁護士に相談し,ひとまず詳しい事情をAさんから聞いてもらうため,弁護士を派遣することにしました。
(フィクションです。)
~犯人隠避罪~
罰金以上の刑を犯した者を隠避させた場合,犯人隠避罪(刑法103条)が成立し,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑が科せられます。
刑法103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
犯人隠避罪は,刑法改正によって厳罰化された犯罪の1つです。
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金という軽くはない法定刑に加え,犯人を隠す等の行為をしていることから,逃亡・証拠隠滅のおそれがあると判断されて逮捕・勾留によって身体拘束をされての捜査となる可能性も高いです。
犯人隠避罪のいう「隠避」とは,官憲の発見・逮捕を免れるべき隠匿場を供給してかくまう方法以外の方法により官憲の発見・逮捕を免れさせる一切の行為をいいます(大判明治43.4.25)。
身代わり犯人として自首することは,本当の犯人を隠してしまうことにつながります。
すなわち,「官憲の発見・逮捕を免れるべき隠匿場を供給してかくまう方法以外の方法により官憲の発見・逮捕を免れさせる」行為にあたりますから,犯人隠避罪のいう「隠避」に当たります。
したがって,Bさんの身代わりに出頭したAさんの行為は,犯人隠避罪に該当すると考えられます。
ここで,犯人隠避罪には,犯人の親族が,犯人または逃走者の利益のために「隠避」を犯したときは,刑事事件化しても刑が免除されることがあるという規定が存在します。
刑法105条
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
これは,犯人の親族が犯人隠避罪を犯してしまうのは,自然の人情として当該行為を行わないことに対する期待可能性が少ないことに鑑みた規定です。
刑法105条で指す「親族」とは,民法上親族とされる者であり,親,子,配偶者,祖父母,孫等が該当します。
しかし,Aさんは犯人であるBさんの恋人ですから,この規定には該当しないということになります。
~犯人隠避事件と弁護活動~
前述のように,刑事事件で逮捕・勾留するかどうかは証拠隠滅や逃亡のおそれの有無で判断されるところ,犯人隠避罪は典型的な捜査妨害なので,逮捕・勾留を回避することは簡単ではありません。
しかし,仮に身体拘束されてしまったとしても,釈放を目指して弁護士に活動してもらうことはできます。
犯人隠避事件で釈放を目指す場合には,身元引受人の確保,帰住先の確保,犯人との接触を断つ対策等をして,裁判官へ釈放を主張していくことが考えられます。
さらに,犯人隠避事件の場合,被害者がいないため示談をすることがでない分,自首,贖罪寄付,家族など監督者の存在のアピールなどが必要になってきます。
どういった事情をどのように主張していくべきかは,刑事事件に強い弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,犯人隠避事件のような珍しい罪名の刑事事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽に,0120-631-881までお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
盗撮・建造物侵入事件で逮捕
盗撮・建造物侵入事件で逮捕
盗撮・建造物侵入事件で逮捕されてしまったケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市に住むAさんは,これまで何度も盗撮を行った常習犯で,以前にも盗撮をしたことで滋賀県の迷惑防止条例違反となり罰金刑を受けたこともある人物でした。
しかし,Aさんは盗撮をすることをやめることができず,滋賀県大津市にあるコンビニの女子トイレにこっそり入るとカメラを設置して,利用客であったVさんの排便の様子を盗撮しました。
Vさんがカメラに気づき,店員に相談。
そこから店員が滋賀県大津北警察署に通報しました。
防犯カメラの映像等から,Aさんが女子トイレに入って盗撮カメラを仕掛け盗撮をしたことが発覚し,Aさんは滋賀県大津北警察署の警察官に,盗撮による滋賀県の迷惑防止条例違反の容疑と建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
~滋賀県の迷惑防止条例違反(盗撮)~
公共の場で盗撮をした場合,各都道府県で定められた迷惑防止条例違反となり,処罰される可能性があります。
滋賀県の場合,「滋賀県迷惑行為等防止条例」という迷惑防止条例の3条で盗撮行為が禁止されています。
滋賀県迷惑行為等防止条例3条
1項 何人も,公共の場所または公共の乗物において,みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
2項 何人も,公共の場所,公共の乗物または集会所,事務所,学校その他の特定多数の者が集まり,もしくは利用する場所にいる人の下着等を見,またはその映像を記録する目的で,みだりに写真機,ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け,または設置してはならない。
3項 何人も,公衆または特定多数の者が利用することができる浴場,便所,更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において,当該状態にある人の姿態を見,またはその映像を記録する目的で,みだりに写真機等を人に向け,または設置してはならない。
この条文に違反して盗撮を行った場合,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます(滋賀県迷惑行為等防止条例11条1項1号)。
さらに,常習として盗撮行為を行ったと判断された場合は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(滋賀県迷惑行為等防止条例11条2項)。
なお,滋賀県の場合,撮影機器がうまく起動していなかったり角度的に下着等が映っていなかったりして実際に盗撮ができていなかった場合であっても,盗撮目的で撮影機器を差し向けたり設置しただけでも盗撮を行ったのと同様に処罰されうることに注意が必要です。
今回のAさんは,公共の場所であるコンビニのトイレで盗撮をしていることから,滋賀県迷惑行為等防止条例3条1項2号に該当し,迷惑防止条例違反(盗撮)が成立すると考えられます。
加えて,Aさんは盗撮目的でコンビニの女子トイレに入った行為には,コンビニの管理者の意思に反する侵入をしたとして,建造物侵入罪が成立する可能性があります。
~盗撮事件と弁護活動~
Aさんの場合,盗撮の初犯ではなく,過去に罰金刑を受けていることから,今回の盗撮事件が裁判になる可能性も否定できません。
そのため,弁護活動としては,被害者との示談交渉とともに公判に向けた準備をすることも考えられます。
例えば,被疑者の家族に,裁判に情状証人として出廷してもらったり,会社が事件を把握しているような場合には会社の社長や上司に裁判が終わってからも雇用を継続すると書面で約束してもらったりすることで,寛大な判決を目指す準備をしていくことが考えられます。
また,前回の罰金刑の時とは本人の反省の度合いが違うことを示すために,例えば,本人が盗撮を繰り返す原因と真摯に向き合っていること,具体的には医療機関に通院し今後も治療を継続すると約束していることなどの事実があればそれを証拠化する等の準備・活動が考えられます。
こうした弁護活動は,刑事事件に強い弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,逮捕等されてしまった捜査段階から起訴されて裁判になってからの公判段階まで,一貫して刑事事件専門の弁護士がサポートを行います。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
万引き事件で微罪処分に
万引き事件で微罪処分に
万引き事件で微罪処分になった事例について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県高島市に住んでいるAは,日々の生活費を少しでも節約しようと考えていた。
ある日,Aは滋賀県高島市にあるスーパーで,節約したい余りに総菜売り場の総菜数百円相当を買い物バッグに隠し,そのまま精算せずにレジを通り抜けた。
しかし,売り場内でのAの挙動に不審を感じた私服警備員がAの行動を逐一監視しており,Aが店を出たところで呼び止めた。
Aは観念して万引きしたことを認め,バックヤードの事務所に連れて行かれた。
スーパーの店長は,滋賀県高島警察署に連絡し,Aは滋賀県高島警察署で取調べを受けることになった。
Aは万引きをしたことが初めてであり,警察沙汰を起こしたこともなかったことから今回の万引きを非常に反省し,弁護士に相談して被害弁償等を含めた弁護活動を依頼した。
その結果,Aは微罪処分となり,事件は検察に送られることなく終了することとなった。
(※フィクションです)
~万引きと微罪処分~
まず,今回の事例でAがしてしまった万引きは窃盗罪に当たります。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
警察は,万引きなどの窃盗罪を含む犯罪の捜査をしたときは速やかに書類及び証拠物と共に事件を検察官に送致しなければなりません。
検察官は,事件の送致を受けた後,被疑者を呼び出して取り調べ,事件を起訴するかしないかを決めるのが通常の手続きです。
しかし,今回のAの万引き事件は,警察で取調べを受け捜査はされているにも関わらず,事件が検察へ送られることもなく,何の処分も受けていないようです。
実は,警察は,特定の事件に限り,検察に送致することなく刑事手続を警察段階で終了させることができます。
これを微罪処分と言います。
微罪処分は,刑事訴訟法第246条但書に根拠があるとされています。
刑事訴訟法第246条
司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,この法律に特別の定のある場合を除いては,速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し,検察官が指定した事件については,この限りでない。
この定めを受けて,犯罪捜査規範第198条は次のように定めています。
犯罪捜査規範第198条
捜査した事件について,犯罪事実が極めて軽微であり,かつ,検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては,送致しないことができる。
Aの万引き行為は,A自身に前科前歴がなく,被害が軽微であり,検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されていた種類のものであったことに加え,弁護士の弁護活動により被害弁償がなされた等の事情があったことで,警察官限りで処理される微罪処分とされたのだと考えられます。
もっとも,どのような事件が「軽微」と判断されるのか,送致の必要がないと予め指定されているかは,一般には公表はされていません。
本件のAは微罪処分で済みましたが,自分のしようとしていることが微罪処分相当だろうと安易に考えるべきではありません。
また,微罪処分は,あくまでそのように処理することもできるというだけのことであって,警察が微罪処分で終わらせなかったとしてもそのことに異議や不服を申し立てることはできません。
更に,微罪処分で処理されても,前歴としては検察庁内に記録が残ります。
被害が軽微であっても同種行為を繰り返したりすると,微罪処分では終わらないでしょう。
~弁護活動~
前述のように,被害が軽いから,前科前歴がないからといって必ずしも微罪処分となるわけではありませんが,迅速に被害弁償等を行っていくことで,微罪処分の獲得や,もしも検察へ事件が送致されたとしてもそこでの不起訴処分の獲得ができる可能性が高まります。
被害弁償等の被害者への対応や,それらを適切に捜査機関に示して処分について交渉していくことを考えれば,早めに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,万引き事件についてお困りの方のご相談も受け付けていますので,まずはお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
路面凍結による交通事故②過失運転致傷罪
路面凍結による交通事故②過失運転致傷罪
路面凍結による交通事故で、特に過失運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、通勤に自動車を使用しています。
ある日、Aさんはニュースで、「今週は今季一番の冷え込みとなるため、路面凍結などが起きる可能性が高い。ドライバーの方は路面凍結による交通事故防止のためにスタッドレスタイヤへの交換やチェーンの取り付けを行うように」という報道がなされているのを見ました。
こうした注意は道路上の電光掲示板や地域の案内メールなどにもみられましたが、Aさんは「わざわざタイヤを変えたりチェーンを付けるのは面倒だ」と思い、特に対策を行わずに路面凍結状態の道路を運転していました。
すると、Aさんが自動車を運転中、ブレーキを踏んだにも関わらず車がスリップしてしまい、Aさんの前を走っていたVさんの車に追突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんはその交通事故で全治3週間の怪我を負ってしまい、Aさんは通報によって駆け付けた滋賀県木之本警察署の警察官に、過失運転致傷罪の容疑で話を聞かれることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・路面凍結と交通事故
前回の記事では、滋賀県では積雪状態の道路や路面凍結状態の道路を運転する時、滑り止めの措置を講じなければ道路交通法違反となりうることに触れました。
今回の事例のAさんは、路面凍結状態の道路をなんのすべり止め対策もせずに運転してしまっています。
こうしたことから、最終的にAさんは路面凍結によるスリップを起こし、Vさんにけがを負わせる交通事故を起こしてしまっています。
交通事故を起こして人に怪我を負わせてしまったケースでは、多くの場合、自動車運転処罰法内に定められている過失運転致傷罪という犯罪が成立します。
自動車運転処罰法5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷罪の「過失」とは、条文上の「自動車の運転上必要な注意を怠り」という部分に当たります。
つまり、自動車を運転するにあたって注意する義務のあるものについて、その義務を怠った、ということです。
今回のAさんの事例で考えてみましょう。
Aさんには、前回の記事でも取り上げたように、路面凍結状態にある道路を走行するためにはすべり止め措置を講じなければいけないという義務がありました。
しかし、Aさんはその義務を怠り、路面凍結によるスリップを起こし、それによって交通事故を起こしてVさんにけがをさせています。
すなわち、Aさんは路面凍結状態の道路をすべり止め措置を講じずに運転するという「過失」によってVさんにけがをさせていることから、この過失運転致傷罪が成立すると考えられるのです。
なお、今回のAさんの事例で考えてみれば、交通事故によってVさんは全治3週間の怪我を負っているため、但し書きにある刑の免除を受けることは難しいと考えられます。
・交通事故と刑事弁護
交通事故を起こして相手に怪我をさせ、過失運転致傷事件として刑事事件となった場合には、まずは被害者の方への謝罪や弁償をしていくことが考えられます。
保険に入っている方については、保険会社が被害者に対して損害賠償をしてくれる場合もありますが、例えば被害者の方からお許しの言葉をいただけないか交渉するといった刑事事件により有効な示談交渉は保険会社とはまた別に行わなければなりません。
さらに、今回のAさんは逮捕されていませんが、もしも逮捕されてしまっているような場合には、釈放を目指して活動することも考えられます。
そして、起訴され裁判となれば、その裁判の場でどういった主張をしていくのかも検討し、活動しなければなりません。
こうした活動を刑事事件に慣れない当事者のみで行うことは非常に難しいでしょう。
ですから、早い段階で弁護士に相談・依頼しておくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故に関連する刑事事件のご相談・ご依頼も承っています。
0120-631-881ではいつでも弊所弁護士によるサービスのご予約・お申込・お問い合わせを受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
路面凍結による交通事故①道路交通法違反
路面凍結による交通事故①道路交通法違反
路面凍結による交通事故で、特に道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、通勤に自動車を使用しています。
ある日、Aさんはニュースで、「今週は今季一番の冷え込みとなるため、路面凍結などが起きる可能性が高い。ドライバーの方は路面凍結による交通事故防止のためにスタッドレスタイヤへの交換やチェーンの取り付けを行うように」という報道がなされているのを見ました。
こうした注意は道路上の電光掲示板や地域の案内メールなどにもみられましたが、Aさんは「わざわざタイヤを変えたりチェーンを付けるのは面倒だ」と思い、特に対策を行わずに路面凍結状態の道路を運転していました。
すると、Aさんが自動車を運転中、ブレーキを踏んだにも関わらず車がスリップしてしまい、Aさんの前を走っていたVさんの車に追突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんはその交通事故で全治3週間の怪我を負ってしまい、Aさんは通報によって駆け付けた滋賀県木之本警察署の警察官に、過失運転致傷罪の容疑で話を聞かれることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・路面凍結と運転
2月に入りましたが、まだまだ寒い日が続いています。
寒い日が続くと、今回の事例のように路面凍結による交通事故も起こりやすくなってしまいます。
この記事を読まれている方の中にも、路面凍結によってブレーキを踏んだのに車がスリップしてしまいヒヤッとしたことのある方がいらっしゃるのではないでしょうか。
路面凍結についてAさんのように簡単に考えてしまっている方もいるかもしれませんが、実は、そもそもこういった路面凍結や積雪した道路を運転する場合について、法律によって注意と対策をしなければいけないということが決められているのです。
まずは道路交通法を見てみましょう。
道路交通法71条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
6号 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
この「…公安委員会が…定めた事項」について、滋賀県では以下のような定めがあります。
滋賀県道路交通法施行細則14条
法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
1号) 積雪または凍結している道路において、自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン等をとりつけ、すべり止めの措置を講ずること。
※注:「法」とは道路交通法のことを指します。
つまり、滋賀県では、積雪状態の道路や路面凍結状態の道路を運転する時には、何らかのすべり止め措置をしなければいけないということなのです。
この道路交通法施行細則は各都道府県ごとに定めらえており、細かく内容も異なってくることから、もしも関連する刑事事件を起こしてしまったら、自分の行為はどの都道府県の細則のどの部分にどのように違反しているのか聞いてみましょう。
この道路交通法に違反した場合、以下のような罰則を受けることになります。
道路交通法120条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
9号 第71条(運転者の遵守事項)第1号、第4号から第5号まで、第5号の3、第5号の4若しくは第6号…(中略)…の規定に違反した者
ですから、タイヤを変えるのが面倒だから、チェーンを付けるのが億劫だからといった理由で路面凍結状態の道路を運転してはいけないのです。
このように、身近な行動1つとっても、道路交通法違反などの犯罪になってしまう可能性があることがわかります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反・交通事故から刑事事件へと発展したケースについてのご相談・ご依頼も承っています。
まずは遠慮なく、初回無料法律相談・初回接見サービスのお申込・お問い合わせ用フリーダイヤルへお電話ください(0120-631-881)。
次回の記事では交通事故について詳しく取り上げていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。