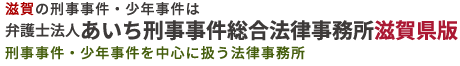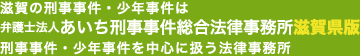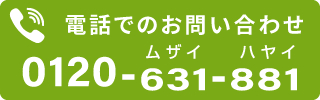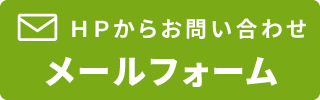Archive for the ‘未分類’ Category
赤信号無視の危険運転致死事件
赤信号無視の危険運転致死事件
赤信号無視の危険運転致死事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは,滋賀県彦根市の路上で自動車を運転している最中,赤信号を意図的に無視して交差点に進入し,歩行者のVさんをはねて死亡させました。
近くにいた人が通報したことで,すぐに滋賀県彦根警察署の警察官が駆け付け,Aさんは,自動車運転処罰法違反(危険運転致死罪)の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんが逮捕されたことを知ると,弁護士に相談すると同時に,弁護士にAさんの接見に向かってもらいました。
弁護士と接見したAさんは,弁護士から自分のしたことが赤信号無視による危険運転致死罪であることを説明されました。
(フィクションです。)
~赤信号無視による危険運転致死罪~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(いわゆる自動車運転処罰法)では,一定の危険な態様で自動車を運転して人を死傷させたような場合について,危険運転致死傷罪という重い犯罪を定めています。
例えば,今回Aさんが容疑をかけられている危険運転致死罪が成立する時の例としては,アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたり,赤信号をあえて無視して運転をしたような場合に,人を死亡させてしまったときが挙げられます。
危険運転致死罪が成立した場合には,1年以上の有期懲役が科せられます(自動車運転処罰法2条1号,5号)。
自動車運転処罰法2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
4 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
5 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
6 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
Aさんは,あえて赤信号を無視して交差点に進入しVさんをはねて死亡させているので,このうち5号の「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」にあたり,危険運転致死罪が成立する可能性があるといえます。
ここで,「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」とは,「殊更」とあるだけに,単純に赤信号無視しただけではこの条文に該当しないことがわかります。
この「殊更に無視」とは,「およそ赤色信号に従う意思のないものをいい,赤色信号であることの確定的な認識がない場合であっても,信号の規制自体に従うつもりがないため,その表示を意に介することなく,たとえ赤色信号であったとしてもこれを無視する意思で進行する行為も,これに含まれると解するべきである。」(最決平成20.10.16)と解されています。
ですから,どのような態様で赤信号無視をしてしまったのかが,危険運転致死罪となるかどうかにかかわってくることになります。
~危険運転致死事件の弁護活動~
交通事故の加害者となり,刑事責任を問われるような場合は,弁護士に相談して示談を試みるなどの対応をすることをお勧めします。
裁判では,情状として,被害者遺族との示談や被害弁償,任意保険や自賠責保険に加入している場合はその支払い状況等を主張していくことが考えられます。
加えて,弁護士は,被害者遺族との示談等以外にも,加害者が交通事故事件を起こしたことと真摯に向き合い反省している情状として,加害者が自ら所有していた車を処分したことや,再犯防止のために交通ルールを学ぶ講習などに参加したことなどの事情があれば,そういった事情も主張していくことになるでしょう。
どういった弁護方針となりそうか,どのような弁護活動が可能かは事件ごとに異なりますので,まずは弁護士に相談されることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,赤信号無視による危険運転致死事件などの交通事故事件のご相談も承っています。
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
器物損壊事件の示談を相談
器物損壊事件の示談を相談
器物損壊事件の示談と弁護士への相談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
滋賀県東近江市在住のAさんは,滋賀県東近江市内のとある駅前に設置されている銅像の左手にあった竿を抜き取って折りました。
目撃者のWさんが滋賀県東近江警察署に通報し,Aさんは器物損壊罪の容疑で滋賀県東近江市を管轄するの滋賀県東近江警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は,逮捕されたAさんのもとへ弁護士を派遣し,Aさんに刑事事件の手続きを説明してもらうと同時に,自分たちも今後可能な弁護活動について相談することにしました。
その場で示談交渉についての相談をしたAさんの家族は,そのまま弁護士に弁護活動を依頼,すぐに示談交渉に取り掛かってもらうことにしました。
(フィクションです。)
~器物損壊罪~
他人の物を損壊した者には,器物損壊罪(刑法261条)が成立し,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
科料というのは,1000円以上1万円未満の財産刑です(刑法17条)。
刑法261条
前三条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪の「損壊」とは,その物の効用を害する一切の行為をいいます。
Aさんは,銅像という他人の物の一部である竿を勝手に抜き取って折っています。
これにより,銅像の効用が害されているといえますから,Aさんの行為には,器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
~器物損壊罪と示談~
器物損害罪の法定刑は前述のとおりです。
器物損壊罪は他の犯罪と比較して軽い部類の犯罪といえます。
しかし,他の犯罪と比較して軽い部類の法定刑であるからといって,逮捕されないというわけではありません。
Aさんのように,器物損壊事件でも逮捕され身体拘束を受けて捜査される人も少なくありません。
ですから,器物損壊事件を起こした場合,なるべく早く弁護士に相談し,できる弁護活動に取り掛かってもらうことがおすすめです。
例えば,弁護士のできる活動の1つに,被害者との示談交渉があります。
器物損壊罪は,被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。
刑法264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
告訴とは,犯罪被害の申告(これのみのものがいわゆる被害届です)に加え,処罰を望む意思を表明するものです。
親告罪の場合,告訴がなくとも被害届が出されたり目撃した人によって通報されたりした時点で捜査が開始されるものもありますが,起訴するためにはこの告訴が必要となってきます。
そのため,器物損壊事件では,示談の成立により告訴を取り下げてもらうか告訴をしないという約束をもらうことができれば,不起訴処分となります。
刑事事件化しても,不起訴処分であれば,前科はつきません。
また,器物損壊罪で起訴され裁判になってしまった場合でも,器物損壊事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで,罰金での終結や執行猶予処分の獲得ができる可能性があります。
略式罰金手続きとなれば,罰金を支払うことで事件を終わらせることができますし,執行猶予となれば執行猶予中に新たな犯罪を犯さないかぎり,刑務所に入らないで済むことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が,器物損壊事件を含む刑事事件の示談交渉についてのご相談・ご依頼もいただいています。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
カラーコピーは文書偽造罪?②
カラーコピーは文書偽造罪?②
前回に引き続き、カラーコピーと文書偽造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県近江八幡市に住んでいるAさんは、医師の診断を受けて睡眠薬を処方されました。
しかしAさんは、「自分の症状にはこれだけの睡眠薬では不足している。もっと睡眠薬をもらわなければならない」と考え、医師からもらった処方箋を自宅で何枚かカラーコピーし、それぞれ別の薬局に提出して睡眠薬を受け取り、代金を支払いました。
その後、全く同じ内容の処方箋がカラーコピーされて提出されていることに近隣の薬局が気づき、滋賀県近江八幡警察署に相談されました。
そして滋賀県近江八幡警察署の捜査の結果、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※令和元年10月23日京都新聞配信記事(24日に更新)を基にしたフィクションです。)
・カラーコピーは文書偽造罪?
前回の記事では、私文書偽造罪・変造罪について詳しく見ていきました。
今回の記事では、Aさんが処方箋をカラーコピーして使用した行為を具体的に照らし合わせて考えていきます。
まずは、前回確認した私文書偽造罪・私文書変造罪についてもう一度条文を確認してみましょう。
刑法159条(私文書偽造等)
1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2項 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3項 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
今回、Aさんがカラーコピーした「処方箋」は、医師等の印章(いわゆるハンコ)が使用されており、その患者に処方箋にある薬が必要であるという医師の診断という事実を証明する文書ですから、「有印私文書」となるでしょう(ただし、公立病院であった場合には公務員が作成する書類となりますので、「私文書」ではなく「公文書」となります。)。
そして、Aさんは睡眠薬を本来よりも多くもらうため=カラーコピーの処方箋を薬局に提出して使用するために処方箋をカラーコピーしているわけですから、「行使の目的」であると考えられます。
ここまでは、Aさんの行為について、有印私文書偽造罪または有印私文書変造罪に当てはまるといえます。
そのため、Aさんが処方箋を「偽造」もしくは「変造」していると考えられれば、Aさんには私文書偽造罪もしくは私文書変造罪が成立する可能性があるということになりますが、Aさんの行為は処方箋を「偽造」もしくは「変造」しているといえるのでしょうか。
前回の記事で確認した通り、有印私文書偽造罪の「偽造」とは、その文書を作成する権限を持たない者が、他人の名義を同意を得ずに使用して文書を作成すること(=有形偽造)をいいます。
今回のAさんが行ったのは、処方箋のカラーコピーです。
すでに処方箋という文書を作成する権限のある医師が作成した処方箋をそのままそっくりコピーしているわけですから、Aさん自身が処方箋を作成したわけではありません。
ですから、Aさんのカラーコピーした処方箋の作成者と名義人は一致していることになります。
そうなると、その文書を作成する権限を持たない者が、他人の名義を同意を得ずに使用して文書を作成していることにはならず、Aさんの行為は「偽造」しているとはいえず、有印私文書偽造罪とはならないと考えられるのです。
ただし、カラーコピーの処方箋について医師名を変更したり薬の種類を変更したりすれば、「偽造」ととらえられ、私文書偽造罪となることも考えられます。
また、日付を変更するなどしていた場合には、私文書変造罪となることも考えられます。
どういった態様で行ったかによって犯罪の成立・不成立が変わってきますので、文書偽造事件で容疑をかけられてしまった場合には、専門家である弁護士に詳しい事情を話して相談してみましょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件や文書偽造事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
24時間いつでも申し込みが可能のフリーダイヤルで、専門スタッフがサービスをご案内しています。
まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
カラーコピーは文書偽造罪?①
カラーコピーは文書偽造罪?①
カラーコピーと文書偽造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県近江八幡市に住んでいるAさんは、医師の診断を受けて睡眠薬を処方されました。
しかしAさんは、「自分の症状にはこれだけの睡眠薬では不足している。もっと睡眠薬をもらわなければならない」と考え、医師からもらった処方箋を自宅で何枚かカラーコピーし、それぞれ別の薬局に提出して睡眠薬を受け取り、代金を支払いました。
その後、全く同じ内容の処方箋がカラーコピーされて提出されていることに近隣の薬局が気づき、滋賀県近江八幡警察署に相談されました。
そして滋賀県近江八幡警察署の捜査の結果、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※令和元年10月23日京都新聞配信記事(24日に更新)を基にしたフィクションです。)
・私文書偽造罪
前回の記事では、同じ事例のAさんについて、詐欺罪が成立することについて触れました。
ここで、Aさんは医師からもらった処方箋をカラーコピーし、それを薬局に提出しています。
Aさんは、いわば偽物の処方箋を利用して詐欺行為をしていたわけですが、このカラーコピーをした偽物の処方箋については、文書偽造罪や偽造文書行使罪に問われることはないのでしょうか。
今回からは、この点について検討していきます。
まず、そもそも文書偽造罪とはどういった犯罪なのでしょうか。
条文を確認してみましょう。
刑法159条(私文書偽造等)
1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2項 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3項 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法159条の1項は有印私文書偽造罪、2項は有印私文書変造罪、3項は無印私文書偽造罪・無印私文書変造罪と呼ばれる犯罪です。
偽造・変造した文書が公文書(公務員や公の機関が作成する文書)である場合には、私文書偽造罪とは別に刑法155条に規定されている公文書偽造罪・公文書変造罪という犯罪になり、公文書以外の文書を偽造・変造した場合に前述した私文書偽造罪・私文書変造罪となるのです。
今回のケースの「処方箋」も、医師等の印章(いわゆるハンコ)が使用されており、その患者に処方箋にある薬が必要であるという医師の診断という事実を証明する文書ですから、「私文書」となるでしょう(ただし、公立病院であった場合には公務員が作成する書類となりますので、「私文書」ではなく「公文書」となります。)。
そのため、もしもAさんが「処方箋」を「偽造」したとされれば、私文書偽造罪に問われることになりそうです。
・私文書偽造罪の「偽造」と「変造」
多くの方のイメージでは、何かの文書の偽物を作れば私文書偽造罪の「偽造」にあたり、私文書偽造罪にあたるのではないかと想像されるのではないでしょうか。
しかし、私文書偽造罪の「偽造」は単に偽物、という定義ではないのです。
さらに、先ほど挙げた刑法159条の中には、私文書偽造罪だけでなく私文書変造罪という犯罪も出てきました。
これらの定義、違いは一体どういったものなのでしょうか。
まず、「偽造」には、「有形偽造」と「無形偽造」と呼ばれる2つの種類の偽造があります。
「有形偽造」とは、その文書を作成する権限を持たない者が、他人の名義を同意を得ずに使用して文書を作成することとされています。
つまり、その文書の名義人と作成した人が異なっている=文書の名義人と作成者の人格の同一性に齟齬がある文書を作成することが「有形偽造」と呼ばれる「偽造」です。
対して、「無形偽造」とは、その文書を作成する権限を持つ者が、虚偽の内容の文書を作成することとされています。
つまり、「無形偽造」の場合、「有形偽造」とは違って名義人と作成者は一致しますが、その文書の内容が偽られているということになります。
このうち、私文書偽造罪のいう「偽造」は、原則的には「有形偽造」を指すとされています。
「無形偽造」については、刑法156条の虚偽公文書作成罪や、刑法160条の虚偽診断書作成罪などで処罰が規定されており、私文書偽造罪や公文書偽造罪では裁かれません。
こうした「偽造」に対して、「変造」とは、すでに作成されている真正な文書の本質的でない部分に、その文書に手を加える権限のない者が不正に手を加えることで新たに別の価値を作り出すことを指します。
文書の本質的な部分を変えてしまった場合には、「変造」ではなく「偽造」とされることもあります。
このように、単に偽物の文書を作るだけでは、私文書偽造罪の「偽造」とはならないことや、態様によっては私文書偽造罪になるのか私文書変造罪となるのかが異なってくることに注意が必要です。
ですが、これらは専門知識や経験に基づいて見通しを立てることができるものであり、逮捕されてしまった本人やその周囲のご家族などの方々が全て自分たちだけで判断することは難しいでしょう。
だからこそ、文書偽造事件にお悩みの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
次回の記事では、Aさんに文書偽造罪は成立しないのかどうか具体的に照らし合わせて検討していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
代金を支払っても詐欺罪?
代金を支払っても詐欺罪?
代金を支払っても詐欺罪となるのかどうか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県近江八幡市に住んでいるAさんは、医師の診断を受けて睡眠薬を処方されました。
しかしAさんは、「自分の症状にはこれだけの睡眠薬では不足している。もっと睡眠薬をもらわなければならない」と考え、医師からもらった処方箋を自宅で何枚かカラーコピーし、それぞれ別の薬局に提出して睡眠薬を受け取り、代金を支払いました。
その後、全く同じ内容の処方箋がカラーコピーされて提出されていることに近隣の薬局が気づき、滋賀県近江八幡警察署に相談されました。
そして滋賀県近江八幡警察署の捜査の結果、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※令和元年10月23日京都新聞配信記事(24日に更新)を基にしたフィクションです。)
・代金を支払っていても詐欺罪?
今回の事例のAさんは、詐欺罪の容疑で逮捕されています。
Aさんは、カラーコピーされた処方箋を別々の薬局に出すことで、本来購入できる以上の睡眠薬を手に入れていたようです。
しかし、Aさんは睡眠薬の代金はきちんと支払っているようです。
それでもAさんに詐欺罪は成立するのでしょうか。
詐欺罪の条文を確認しながら検討してみましょう。
詐欺罪は、刑法246条に規定されています。
刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪が成立するには、
①人をだます行為をする(=「人を欺いて」)
②人をだます行為によって相手がだまされる(=「人を欺いて」)
③だまされたことに基づいて相手が財物を引き渡す行為をする(=「財物を交付させた」)
という流れをたどり、さらにこの①~③の一連の流れに因果関係が存在することが必要とされています。
「①人をだます行為をする」については、一般に「欺罔行為」と呼ばれています。
この欺罔行為については、単純に人に対して嘘をつくだけでは足らず、その財物を引き渡すという判断をする際に基礎となる重要な事項について偽ることをいうとされています。
つまり、その事実が嘘であるなら財物を引き渡さなかったというような事実について嘘をつくことで、詐欺罪成立のための1つの条件が満たされることになるのです。
次に、「②人をだます行為によって相手がだまされる」ですが、これは一般に「錯誤に陥らせる」というような言い方をします。
先ほど触れた①の行為によって相手がだまされ、勘違いに陥らなければ詐欺罪は成立しません。
そして「③だまされたことに基づいて相手が財物を引き渡す行為をする」ということですが、②で触れたように、相手が①の行為によってだまされたことによって、財物が引き渡されなければなりません。
例えば、①の欺罔行為があったものの、相手がその嘘に気が付きながらも相手をかわいそうに思ってその嘘に乗ってあげた、というような場合には、相手はだまされて財物を引き渡したわけではありませんから、詐欺罪は成立しないということになります(この場合詐欺未遂罪は成立する可能性があります。)。
では、今回のAさんについて検討してみましょう。
Aさんは、カラーコピーした処方箋を薬局に提出し、睡眠薬を受け取っています。
まず、処方箋は意思が作成した原本を薬局に提出し、それに基づいて薬を受け取るものですから、本来複製されたものや勝手に作成された物では薬を処方することはできません。
ですが、Aさんはカラーコピーをした処方箋を本物の処方箋のように装って薬局へ提出しています。
処方箋がカラーコピーされたものであると知っていれば、薬局としては睡眠薬をAさんに渡すことはしなかったでしょう。
つまり、Aさんは、薬局が睡眠薬という財物を引き渡す際に基礎となる、処方箋が本物の処方箋なのかどうかという重要な事項について嘘をついていたということになります。
ですから、Aさんは詐欺罪の成立要件のうち、①について満たしていると考えられます。
そして、このAさんのカラーコピーの処方箋の提出によって、薬局は、提出された処方箋が本物であるという勘違いに陥っています。
これが詐欺罪の成立要件のうちの②に該当します。
最後に、薬局は、提出された処方箋が本物であるという勘違いに基づいて、睡眠薬をAさんに引き渡しています。
これによって③の要件も満たされ、さらに①~③の間に因果関係もあると考えられることから、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられるのです。
ここで、Aさんは代金を支払っていますが、ここまで見てきた通り、詐欺罪は、交付の際に基礎となる重要な事項を偽って相手をだまし、それによって財物を交付させる犯罪です。
そのため、交付される財物の対価として代金を支払っていたとしても、交付の際に基礎となる重要な事項を偽って相手をだまし、それによって財物を交付させているのであれば、詐欺罪は成立することになるのです。
つまり、代金を支払っていたのだから詐欺罪は成立しない、ということにはならないのです。
このように、一見詐欺罪は成立しないように見える事例でも、法律と突き合わせてみると詐欺罪が成立する事例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような複雑な詐欺事件についても、刑事事件専門の弁護士がご相談にのります。
0120-631-881では、いつでも弊所弁護士によるサービスのお申し込みを受け付けておりますので、遠慮なくお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
危険ドラッグ所持事件で逮捕
危険ドラッグ所持事件で逮捕
危険ドラッグ所持事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県甲賀市に住んでいる高校3年生のAさんは、受験勉強に疲れ、ストレス発散できるものがないかと悩んでいました。
すると、友人のBさんが「いいバスソルトが買えるサイトがあるよ」といって、疲労回復やリフレッシュの効果があるというバスソルトを取り扱っている雑貨店の販売サイトを教えてくれました。
Aさんはそのサイトを見てみると、たしかにバスソルトが販売されており、ストレス解消に効果がある旨が書いてありました。
Aさんは、「これはもしかしたら話題になっている危険ドラッグなどの違法薬物なのではないか」と思いましたが、「違法薬物であったとしてもそうであったら使わないでいればいいだろう」と思い、バスソルトを購入し、手元に持っていました。
すると、後日、そのバスソルトを使用する前に滋賀県守山警察署の警察官がやってきて、Aさんを薬機法違反の容疑で逮捕してしまいました。
Aさんの所持しているバスソルトはやはり危険ドラッグの一種だったのです。
(※この事例はフィクションです。)
・危険ドラッグ
昨今、危険ドラッグという呼称も一般に浸透してきたところだと思われますが、危険ドラッグは元々「脱法ドラッグ」や「合法ドラッグ」、「脱法ハーブ」などと呼ばれていたものです。
これらの薬物は、大麻や麻薬、覚せい剤などの違法薬物と同様もしくは類似の成分が含まれている危ない薬物であり、現在では薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の「指定薬物」として規制されている違法薬物です。
危険ドラッグの成分は、先ほど触れたように他の違法薬物と同じ又は類似したものが含まれていることが多いですが、危険ドラッグの中にはより危険で人体に危害を加える成分が含まれているものもあります。
危険ドラッグを使用した場合、他の違法薬物同様に高揚感や清涼感などを感じることもあるようですが、危険ドラッグの使用により、幻覚や幻聴、意識障害や嘔吐を引き起こしたり、最悪の場合には死に至ることもあります。
このように危険な危険ドラッグですが、法律の穴を抜けるために、一見して危険ドラッグであると分かるように売られているわけではありません。
今回のAさんが購入してしまったバスソルト状のものから、お香やキャンドルを装ったもの、アロマやハーブを装ったものなど、形状は様々です。
また、パッケージもカラフルなものやポップなものが多く、危険ドラッグのようなリスクの大きいものであるというイメージを持たせず、手が出しやすい見た目となっていることが多いです。
・危険ドラッグ所持と薬機法違反
先ほど触れたように、危険ドラッグは指定薬物として薬機法で規制されています。
Aさんは「使わなければいい」と考えていたようですが、実は危険ドラッグは所持しているだけでも薬機法違反となる犯罪行為です。
薬機法76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
今回のAさんは20歳未満ですので、原則として刑罰を受けることはありませんが、営利目的以外で危険ドラッグの所持をしてしまった場合には「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されることになります(薬機法84条26号)。
・危険ドラッグと少年事件
少年事件では、少年の更生に重きを置いて手続きが進んでいきます。
しかし、少年事件であっても、捜査段階では逮捕や勾留が行われ、警察官や検察官による取調べを受けることになります。
特に危険ドラッグなどの薬物事件では、証拠隠滅のしやすさや関係者の多さから逮捕・勾留が行われることも多いです。
Aさんのように受験の迫る少年などには、長期にわたって身体拘束を受けることになるのかどうかは非常に大きな問題でしょう。
まずは弁護士に相談し、できる活動やその方針を詳しく聞いてみることがおすすめです。
そして、事件が家庭裁判所に行われ、少年事件ならではの手続きに入った際にも、弁護士のサポートが重要となります。
Aさんのような危険ドラッグ所持事件では、今後どのようにして危険ドラッグに手を出さない環境を作っていくのかを少年本人やそのご家族と検討し、さらにその過程や結果を証拠化し、家庭裁判所により適切な処分を求めるための材料としていくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件だけでなく、20歳未満の方の起こしてしまった少年事件も専門に扱っている法律事務所です。
少年による危険ドラッグ所持事件や、逮捕の伴う少年事件について遠慮なくご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
コインランドリーの下着泥棒事件で逮捕②建造物侵入罪
コインランドリーの下着泥棒事件で逮捕②建造物侵入罪
コインランドリーの下着泥棒事件とその逮捕、建造物侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県守山市に住んでいるAさんは、近所のコインランドリーの利用客に女性客が多いことと、利用客は洗濯機を回している間、近くのコンビニやスーパーに買い物に出ていることに気が付きました。
そこでAさんは、コインランドリーの利用客が洗濯機を回している間にコインランドリーへ行き、女性客の下着を盗むことを思いつきました。
Aさんは、コインランドリーで女性客Vさんが洗濯機を回し、スーパーへ出かけていったのを確認するとコインランドリーへ入り、Vさんの利用していた洗濯機からVさんの下着を盗み、立ち去りました。
その後、Vさんが下着を盗まれたことに気づき、滋賀県守山警察署に相談。
捜査の結果、Aさんの犯行が明らかになり、Aさんは窃盗罪と建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・コインランドリーの下着泥棒事件と建造物侵入罪
前回の記事では、Aさんの逮捕容疑の1つである窃盗罪について触れました。
今回の記事では、Aさんのもう1つの逮捕容疑である建造物侵入罪について詳しく見ていきましょう。
刑法130条(建造物侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
マンションのベランダや部屋内に侵入して下着泥棒をしたような下着泥棒事件で建造物侵入罪が成立するのはうなずけるかと思います。
しかし、コインランドリーのような利用する人もしない人も中に入れる施設で、さらに営業時間内に入ったというような場合でも建造物侵入罪が成立することはあるのでしょうか。
建造物侵入罪の「侵入」とは、一般に、その住居に住んでいる人や建造物の管理者の意思に反する立ち入りを指します。
そのため、よくイメージされるような閉店後の店に忍び込むような態様でなかったとしても、建造物侵入罪の「侵入」行為にあたることが考えられます。
今回のコインランドリーの下着泥棒事件では、Aさんはそもそも下着泥棒をするためにコインランドリーに立ち入っています。
コインランドリーを利用しようとする人はともかく、コインランドリーの管理者としては通常、下着泥棒をする目的の人がコインランドリーへ入ることを許さないでしょう。
ですから、今回のAさんはコインランドリーの管理者の意思に反してコインランドリーに立ち入った=「侵入」をしたということになり、建造物侵入罪に問われているのでしょう。
なお、コインランドリーに入った時には下着泥棒の意思はなかったが、コインランドリーに入った後に下着泥棒をしようという意思を生じた場合には、建造物侵入罪は成立しません。
先ほど触れたように、単にコインランドリーを利用しようという人の立ち入りをコインランドリーの管理者が拒むことはないと考えられるからです。
ですから、どの時点で下着泥棒の意思を生じたかは非常に重要なことです。
被疑者自身の供述や犯行の際の詳しい事情を含めて判断されますから、自分の認識に反する供述をして不要な不利益を被らないためにも、弁護士と相談し、きちんと自分の認識通りに主張できるよう準備を整えておくことが大切でしょう。
・コインランドリーの下着泥棒事件と示談
窃盗事件では被害者が存在するため、示談交渉をすることで事件解決を図ることが考えられます。
しかし、今回のような下着泥棒事件の場合、窃盗事件とはいえ性犯罪的な側面もあるため、被害者の被害感情が苛烈であったり、加害者に対する恐怖が大きかったりすることが予想されます。
だからこそ、謝罪をしようと思っても当事者が直接連絡を取ることは難しいでしょう。
ここで、示談交渉の際に弁護士を間に入れることで、被害者の方は加害者と直接連絡を取ることなく謝罪や賠償の話を聞くことができ、要望を伝えることができるようになります。
こうした事情から、弁護士限りでのお話であれば応じてくださる被害者の方も少なくありません。
そのため、示談交渉をしたいのであれば、一度弁護士に相談・依頼をすることがおすすめされます。
また、Aさんのように建造物侵入罪も成立する可能性のある場合には、窃盗罪の被害者(今回であればVさん)への謝罪だけでなく、建造物侵入罪の被害者(今回であればコインランドリーの管理者)への謝罪や弁償も必要となってくるでしょう。
複数の犯罪とその被害者への対応は負担が大きいと考えられますから、弁護士のサポートを受けることでその負担を軽減することが望ましいでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方向けの初回接見サービスから、在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談まで、幅広いサービスを用意しています。
滋賀県の刑事事件にお悩みの際は、お気軽に弊所弁護士によるサービスをご利用ください(お申し込み:0120-631-881)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
コインランドリーの下着泥棒事件で逮捕①窃盗罪
コインランドリーの下着泥棒事件で逮捕①窃盗罪
コインランドリーの下着泥棒事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県守山市に住んでいるAさんは、近所のコインランドリーの利用客に女性客が多いことと、利用客は洗濯機を回している間、近くのコンビニやスーパーに買い物に出ていることに気が付きました。
そこでAさんは、コインランドリーの利用客が洗濯機を回している間にコインランドリーへ行き、女性客の下着を盗むことを思いつきました。
Aさんは、コインランドリーで女性客Vさんが洗濯機を回し、スーパーへ出かけていったのを確認するとコインランドリーへ入り、Vさんの利用していた洗濯機からVさんの下着を盗み、立ち去りました。
その後、Vさんが下着を盗まれたことに気づき、滋賀県守山警察署に相談。
捜査の結果、Aさんの犯行が明らかになり、Aさんは窃盗罪と建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・コインランドリーの下着泥棒事件と窃盗罪
今回のAさんは、コインランドリーで下着泥棒をはたらいていて、窃盗罪と建造物侵入罪の容疑で逮捕されています。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
下着泥棒ですから窃盗罪が成立することが当然だろうと思われるかもしれませんが、ここで、コインランドリーの利用客であったVさんは、洗濯物を洗濯機に入れてその場を離れています。
このように、物をどこかに置いたまま持ち主がその場を離れた時にその物を取った場合にも窃盗罪となるのでしょうか。
刑法には、遺失物横領罪という犯罪が規定されています。
刑法254条(遺失物横領罪)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この遺失物横領罪は、落とし物や忘れ物を盗んでしまったケースで成立することの多い犯罪です。
今回のように持ち主がその場を離れている場合は、こちらの犯罪になるのではないでしょうか。
窃盗罪と遺失物横領罪の違いは、盗まれた物が誰かの占有下であったかどうか、という点の違いによって生じます。
占有とは、その物を支配・管理していることを意味します。
例えば、道端に落ちている落し物は、持ち主の手を離れてしまい、誰の支配・管理のもとにもありませんから、誰の占有もない状態であるといえます。
窃盗罪が他人の占有下にある物をその占有者の意思に反して自分の占有下に移してしまう犯罪であるのに対し、遺失物横領罪は誰の占有下にもない物を自分の占有下に移してしまう犯罪です。
つまり、先ほど例に挙げた道端の落とし物を勝手に自分のものにする、いわゆるネコババをしてしまえば、遺失物横領罪となる可能性が出てくるということになります。
ここで、今回のコインランドリーの下着泥棒はどうでしょうか。
Vさんは洗濯機を回してその場を離れていますが、洗濯物の占有はどうなるのでしょうか。
先ほどの話から見ると、その場に持ち主がいないのであるから洗濯物は誰の占有も受けておらず、Aさんに成立するのは窃盗罪ではなく遺失物横領罪のようにも思えます。
しかし、Vさんは洗濯が終わるころにはコインランドリーに戻って洗濯物を回収するつもりであったでしょうからそれほど遠くへ行ってはいないでしょうし、そもそもコインランドリーではお金を払って洗濯機を利用するため、使用中の洗濯機があれば誰かが使用中でありその中身はその使用している人のものであるということは一目瞭然でしょう。
こうしたことから、今回の場合、たとえVさんがその場を離れていたとしても、洗濯物にVさんの支配・管理は及んだままであるといえるでしょう。
ですから、Aさんに成立が考えられるのはやはり窃盗罪であると考えられるのです。
なお、もしもVさんの洗濯物に対する占有がないとしても、今度はコインランドリー(の管理者)の占有が認められる可能性が高いです。
コインランドリー内の物はもちろん、コインランドリーが支配・管理している物です。
たとえコインランドリー内で落とし物があっても、それを支配・管理するのはコインランドリーとなります。
ですから、もしもVさんの洗濯物に対する占有が認められなかったとしても、やはり今回の被害品である洗濯物には誰かしらの占有が認められ、Aさんには窃盗罪が成立する可能性が高いといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こういった窃盗事件へのご相談・ご依頼も承っています。
滋賀県の窃盗事件にお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
次回の記事では、Aさんのもう1つの逮捕容疑である建造物侵入罪について触れていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
盗撮事件で任意出頭・自首④
盗撮事件で任意出頭・自首④
前回に引き続き、盗撮事件と任意出頭・自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例(前回からの流れ)~
Aさんは、滋賀県草津市にあるXという会社で勤務する会社員です。
Aさんは、女性の下着姿に興味を持ち、会社の女子トイレに忍び込むと、女子トイレの中に盗撮用の小型カメラを設置し、女子トイレの利用者の下着姿を盗撮していました。
しかしある日、女子トイレの利用者の1人がしかけられた小型カメラに気づき、滋賀県草津警察署に通報したことをきっかけに捜査が開始され、会社内で盗撮事件が起こったことが知れ渡りました。
Aさんは、自分が盗撮をしていたことがばれて滋賀県草津警察署に逮捕されてしまうのではないかと不安になり、まずは刑事事件に強い弁護士に、自ら出頭した方がよいのかどうか、自分の盗撮行為はどういった罪にあたるのかといったことを含めて今後の対応を相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・自首とはならないケース
前回の記事で触れたような捜査機関に既に犯人が発覚した後に出頭するようなケースのほかにも、出頭しても自首とはならないケースがあります。
例えば、被疑者として取調べられている最中に自白したような場合は、自首したことにはなりません。
ただし、捜査機関に発覚していない全く別の余罪についての自白をした場合には自首が成立する可能性が出てきます。
さらに、たとえ犯罪の事実の発覚前や犯人発覚前に自ら出頭したとしても、犯罪の事実を隠すような内容の申告であったり、その犯罪に関する自己の責任を否認するような内容の申告であったりした場合にも、自首は成立しません。
簡単にいえば、自分の罪を認めた内容の申告でなければ、自首にはならないということなのです。
例えば、18歳未満の者に対価を支払って性交したという児童買春事件で、相手の児童から「警察に補導された。今までのことがばれるかも」という連絡を受け、不安になって自ら警察署に行ったものの「自分は相手が18歳未満の者だとは知らなかった」と年齢の認識について争う場合、その犯罪に関する自己の責任を否認する内容の申告であるため、自首とはならず任意出頭の扱いとなるでしょう。
・自首・任意出頭のメリットとデメリット
自首が成立した場合のメリットとしてまず考えられるのは、先ほど挙げた条文にあるように「その刑を減軽することができる」ということです。
ここで注意が必要なのは、あくまで「減軽することができる」という決まりであるため、必ず刑が減刑されると決まっているわけではないということです。
しかし、これは任意出頭の場合でも同じですが、自ら罪を認めて出頭してきたという事情は、本人が反省しているということを裏付ける事情でもあるため、処分を決められる際に有利に働くことが予想されます。
なお、自首が成立せずに任意出頭となった場合であっても、条文にこそ規定はありませんが、本人の反省の度合いなどを示す材料にはなりますから、任意出頭の事実をもとに刑罰の減軽や寛大な処分を求めていくことは可能です。
また、自首・任意出頭は、自ら罪を認めて出頭するものですから、被疑者本人に逃亡や罪証隠滅の意思がないことを裏付ける事情の1つにもなります。
こうした事情があることで、逮捕・勾留を回避する可能性を上げることができます。
逮捕・勾留は逃亡や罪証隠滅が疑われれば行われてしまうため、自首・任意出頭の事実はその疑いを晴らすための材料の1つになるのです。
突然の逮捕を回避したいという場合には、自首や任意出頭を選択肢の1つとして検討することも必要となってくるでしょう。
こういったメリットに対して、自首・任意出頭のデメリットとしては、いうなれば「やぶへび」になるかもしれないということが挙げられます。
自首・任意出頭は、自身が犯罪をしたという事実をわざわざ捜査機関に明かす行為ですから、もしかすると特に事件化せずに終息するしたかもしれないことについても自分から刑事事件化することになります。
自首・任意出頭をするのかしないのかの判断は非常に難しいもので、もちろんどちらにもメリット・デメリットが存在します。
自首・任意出頭に悩まれているのであれば、事件の詳細な状況を弁護士に話したうえで、どういったリスクや利益があるのか相談してみることも1つの手でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、こうした自首・任意出頭に関するご相談だけでなく、ご依頼後自首・任意出頭される場合に付き添う活動も行っております。
まずは刑事事件専門の弁護士まで、お気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
盗撮事件で任意出頭・自首③
盗撮事件で任意出頭・自首③
盗撮事件と任意出頭・自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例(前回からの流れ)~
Aさんは、滋賀県草津市にあるXという会社で勤務する会社員です。
Aさんは、女性の下着姿に興味を持ち、会社の女子トイレに忍び込むと、女子トイレの中に盗撮用の小型カメラを設置し、女子トイレの利用者の下着姿を盗撮していました。
しかしある日、女子トイレの利用者の1人がしかけられた小型カメラに気づき、滋賀県草津警察署に通報したことをきっかけに捜査が開始され、会社内で盗撮事件が起こったことが知れ渡りました。
Aさんは、自分が盗撮をしていたことがばれて滋賀県草津警察署に逮捕されてしまうのではないかと不安になり、まずは刑事事件に強い弁護士に、自ら出頭した方がよいのかどうか、自分の盗撮行為はどういった罪にあたるのかといったことを含めて今後の対応を相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮事件で任意出頭・自首をしたい
前回までの記事では、今回のAさんに成立が考えられる可能性のある犯罪について詳しく触れてきましたが、今回の記事ではAさんの今後の対応について触れていきます。
Aさんは、自ら警察に出頭した方がよいのかどうか悩んでいるようですが、自ら出頭する場合のメリットやデメリットはどういったことが考えられるでしょうか。
ここでまず注意しなければならないことの1つとして挙げられるのは、自ら警察署に出頭するということは必ずしも法律に定められている「自首」とはイコールではないということです。
一般的なイメージとしては、自ら警察署に犯人であることや犯行をを申し出る=自首であるというイメージが強いのではないでしょうか。
しかし、刑法で定められている自首の定義は、以下のようなものです。
刑法42条
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
条文にある通り、「自首」は「罪を犯した者」が「捜査機関に発覚する前」に行われなければ「自首」として成立しません。
この「捜査機関に発覚する前」とは、そもそもその犯罪の事実が捜査機関に全く発覚していない時であるか、その犯罪の事実は発覚しているもののその犯人が誰であるか全く分からない時を指します。
つまり、すでに被疑者として指名手配されている場合や、指名手配などはされていなくてもすでに捜査機関から被疑者とされている場合に出頭したとしても、それは自首にはならず、任意出頭したということにとどまるのです。
今回の事例の場合、会社のトイレに盗撮カメラが仕掛けられ盗撮事件が起こったということはすでに滋賀県草津警察署の知るところとなっています。
捜査も開始されているため、犯罪の事実(今回の事例でいえば盗撮という事実)が全く捜査機関に発覚していない時ではありません。
ですから、この状況でAさんが出頭したとして自首が成立するには、盗撮事件は発覚しているが犯人がAさんであるとは全く発覚していないという条件が必要になってきます。
捜査機関側に犯人が発覚しているのかどうかは確かめようがありませんから、この条件が確実に満たされるかどうかははっきり確認することができません。
カメラにAさん自身の姿が映っている可能性があるのかどうか、防犯カメラなどの映像はあるのかどうか、といった様々な事情を考慮して、自首が成立する可能性があるのかどうかを考えることになるでしょう。
そして、自首もしくは任意出頭をするのかどうかを判断することになるでしょう。
自首・任意出頭をする場合はもちろん、しない場合でも、弁護士に相談するなどして刑事事件化した際の対応を整えておくことは重要です。
警察からの呼び出しや逮捕などは唐突に行われることがほとんどですから、そうした事態に備える意味も込めて、早めに弁護士に相談してみることが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件にお悩みの方が気軽にご相談いただけるよう、初回無料法律相談を受け付けています。
まずは0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。