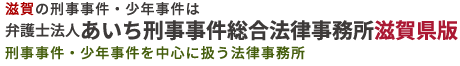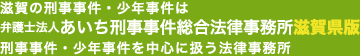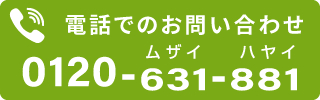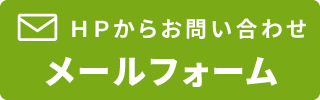Archive for the ‘未分類’ Category
盗撮事件で任意出頭・自首②建造物侵入罪
盗撮事件で任意出頭・自首②建造物侵入罪
盗撮事件と任意出頭・自首、建造物侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例(前回からの流れ)~
Aさんは、滋賀県草津市にあるXという会社で勤務する会社員です。
Aさんは、女性の下着姿に興味を持ち、会社の女子トイレに忍び込むと、女子トイレの中に盗撮用の小型カメラを設置し、女子トイレの利用者の下着姿を盗撮していました。
しかしある日、女子トイレの利用者の1人がしかけられた小型カメラに気づき、滋賀県草津警察署に通報したことをきっかけに捜査が開始され、会社内で盗撮事件が起こったことが知れ渡りました。
Aさんは、自分が盗撮をしていたことがばれて滋賀県草津警察署に逮捕されてしまうのではないかと不安になり、まずは刑事事件に強い弁護士に、自ら出頭した方がよいのかどうか、自分の盗撮行為はどういった罪にあたるのかといったことを含めて今後の対応を相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・トイレでの盗撮と建造物侵入罪
前回の記事で触れたように、滋賀県の場合、会社のトイレで盗撮行為をすれば滋賀県迷惑防止条例違反となる可能性が高いといえます。
しかし、実は今回の事例のAさんには、滋賀県迷惑防止条例違反以外にも、別の犯罪が成立する可能性があるのです。
その中の1つが、刑法にある建造物侵入罪です。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
Aさんはその会社の会社員であるのに建造物侵入罪が成立するのか、と不思議に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、以下の理由から、Aさんには建造物侵入罪が成立する可能性があるのです。
そもそも、建造物侵入罪のいう「人の看守する…建造物」とは、簡単に言えば「人が管理・支配している建造物」という意味です。
会社の建物は、その会社の社長などの役職についている人たちが管理・支配する権限を持った建物です。
テナントのような形でビルに入っている会社であれば、その建物のオーナーが管理・支配しているといえるでしょう。
この管理・支配は当然、その建物全体に及んでいるものですから、今回の盗撮事件が起こった女子トイレも、建物の一部に含まれています。
ですから、たとえ女子トイレだけが独立した建物でなかったとしても「人の看守する…建造物」にあたると考えられるのです。
また、建造物侵入罪が成立するのは、「正当な理由がないのに」前述の建造物に「侵入」した場合です。
「正当な理由」とは、例えば警察官が適法な捜査のために立ち入る場合や職務のために立ち入る場合などが考えられます。
今回のような女子トイレへの立ち入りであれば、通報を受けて駆け付けた警察官が不審者の捜索のために立ち入る場合や清掃員が清掃のために立ち入る場合などが「正当な理由」のある立ち入りだと考えられるでしょう。
そして、「侵入」とは、一般に、その建物の管理者の意思に反する立ち入りを指すといわれています。
今回のような場合であれば、女子トイレに盗撮目的で立ち入るようなことは通常その建物を管理・支配している人は許可しないだろうと考えられることから、建造物侵入罪のいう「侵入」に該当すると考えられるのです。
逆に言えば、盗撮目的で立ち入った人自身が建物の管理者であったような場合や、立ち入った当初は「正当な理由」があったものの立ち入ってから盗撮を思いついて盗撮カメラを仕掛けたような場合には、建造物侵入罪は成立せず、前回触れたような都道府県ごとに定められている迷惑防止条例違反などのその他の犯罪の成立が検討されることになるでしょう。
・盗撮事件の建造物侵入罪と示談
こうした盗撮事件で建造物侵入罪が成立する場合、考えられる弁護活動の1つに示談交渉があります。
建造物侵入罪も被害者の存在する犯罪ですから、被害に遭った方に謝罪や弁償を行い、示談をすることで刑罰の減軽などが期待できます。
しかし、盗撮事件の建造物侵入罪の場合、被害者=盗撮された人とは限らないということに注が必要です。
先ほど触れたように、建造物侵入罪は管理者の意思に反して建造物に立ち入るという犯罪ですから、被害者は勝手に建造物に入られてしまったその建物の管理者となります。
これが例えば個人宅で起こった盗撮事件であれば、盗撮された人もその建物の管理者も同一人物、ということになりそうですが、今回のAさんの事例のように、会社の女子トイレが盗撮現場である場合には、実際に盗撮をされた被害者(今回の場合は滋賀県迷惑防止条例違反の被害者)と建造物侵入行為をされた被害者が全く別ということになりうるのです。
また、今回の事例のように会社のトイレで盗撮したような場合には、盗撮行為の被害者が複数人いる場合も少なくありませんから、謝罪や弁償を行って示談交渉をしようとすれば、一度に複数人の被害者の方に連絡を取り、示談交渉をすることも考えられます。
当事者だけでこうした活動を行うことは非常に負担も大きいですから、早めに弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、起こしてしまった盗撮事件でどういった犯罪が成立しうるのか、どういった活動が可能なのか、といったご相談にももちろん対応しています。
まずはお気軽に、初回接見サービス・初回無料法律相談からご利用ください。
盗撮事件で任意出頭・自首①滋賀県迷惑防止条例違反
盗撮事件で任意出頭・自首①滋賀県迷惑防止条例違反
盗撮事件と任意出頭・自首、滋賀県迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県草津市にあるXという会社で勤務する会社員です。
Aさんは、女性の下着姿に興味を持ち、会社の女子トイレに忍び込むと、女子トイレの中に盗撮用の小型カメラを設置し、女子トイレの利用者の下着姿を盗撮していました。
しかしある日、女子トイレの利用者の1人がしかけられた小型カメラに気づき、滋賀県草津警察署に通報したことをきっかけに捜査が開始され、会社内で盗撮事件が起こったことが知れ渡りました。
Aさんは、自分が盗撮をしていたことがばれて滋賀県草津警察署に逮捕されてしまうのではないかと不安になり、まずは刑事事件に強い弁護士に、自ら出頭した方がよいのかどうか、自分の盗撮行為はどういった罪にあたるのかといったことを含めて今後の対応を相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・トイレでの盗撮と滋賀県迷惑防止条例違反
盗撮事件の場合、成立しうる犯罪が盗撮の行われた事件地がどの都道府県なのか、どういった態様で盗撮行為をしたのか、盗撮の被害者の年齢は何歳なのか、といった様々な事情によって成立する犯罪が異なります。
「盗撮」という言葉は広く知られており、どういった内容の犯罪なのかはなんとなく皆さんご存知でしょうが、どのような場合に何罪になるかは意外にも複雑なのです。
今回のAさんは、滋賀県草津市にある自分の勤務する会社の女子トイレで盗撮を行っていたようです。
このような場合、どういった犯罪が成立するのか、まずはそこを考えていきましょう。
まず成立が考えられるのは、滋賀県の迷惑防止条例違反(正式には「滋賀県迷惑行為等防止条例違反」)です。
各都道府県では、都道府県民に対する迷惑行為を防止するため、それぞれ迷惑防止条例を定めています。
この迷惑防止条例違反は、盗撮事件だけでなく痴漢事件でも目にすることの多い犯罪ですから、聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為に関する規定がありますが、具体的に規制している行為や刑罰の重さは都道府県によってまちまちであるため、とある県では迷惑防止条例違反の盗撮行為であると判断される行為も、別の件では迷惑防止条例違反とはならない場合があります。
だからこそ注意が必要なのですが、今回はAさんの例に沿って考えてみましょう。
まずは滋賀県迷惑防止条例の盗撮に関する条文を確認してみましょう。
滋賀県迷惑防止条例3条
1項 何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
3項 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。
どの都道府県でも、滋賀県迷惑防止条例3条1項にあるような「公共の場所」「公共の乗り物」での盗撮行為は規制されていることが多いです。
しかし、滋賀県迷惑防止条例3条2項や3条3項にあるような、「公共の場所」「公共の乗り物」以外の場所で「特定多数の者」が利用する場所での盗撮行為についての規定については、規定のある県とない県が存在します。
滋賀県の場合はご覧いただいて分かるように、「特定多数の者」が利用する場所での盗撮行為は滋賀県迷惑防止条例で禁止されています。
今回のAさんは、会社内の女子トイレで盗撮をしています。
会社内の女子トイレは、その会社に勤務している人が利用する場所ですから、不特定多数の者が利用する場所=「公共の場所」とは言えませんが、「その会社に勤務している」という特定の人たち=「特定多数の者」が利用する場所だといえそうです。
そうした場所のトイレ=「人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所」で、トイレを利用する人達の姿を盗撮していたのですから、「当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置」したといえるでしょう。
つまり、今回のAさんのケースでは、Aさんの盗撮行為は滋賀県迷惑防止条例違反となることが考えられるのです。
これがもし、例えば盗撮現場が個人宅のトイレであったような場合には、個人宅のトイレは「特定多数の者」ではありませんから、迷惑防止条例違反にはならないということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、盗撮事件のご相談も多くいただいています。
滋賀県の盗撮事件にお困りの際は、弊所弁護士までご相談ください。
次回の記事では、Aさんに成立が考えられる他の犯罪について検討します。
大津市の偽計業務妨害事件で逮捕
大津市の偽計業務妨害事件で逮捕
大津市の偽計業務妨害事件での逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは,滋賀県大津市にある恋人の家に行くたびに,滋賀県大津市にある無人のコインパーキングを利用していました。
Aさんは,駐車料金を支払うのが煩わしくなり,ロック板を踏み越えないように駐車し,恋人の家から帰る際,駐車料金を支払わずにそのまま発車して帰宅しました。
Aさんはこのような行為を繰り返していたところ,コインパーキングの所有者のVさんが防犯カメラの映像などからこの行為に気づき,滋賀県大津市を管轄する滋賀県大津警察署に被害届を提出しました。
捜査の結果,Aさんは,偽計業務妨害罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~偽計業務妨害罪~
無人のコインパーキングでは,駐車してからしばらくすると,駐車スペースの真ん中に設置されたロック板が上がり,自動精算機にお金を入れないと自動車が動かせない仕組みになっています。
ですから,こういった仕組みのコインパーキングでは,Aさんが行っていたようにロック板の手前に駐車すれば,駐車料金を支払わずに発車することができます。
このような行為には,犯罪が成立しないのでしょうか。
以下で検討してみましょう。
まず,窃盗罪は成立しません。
窃盗罪はあくまで財物を盗む犯罪であり,今回の場合は形ある物を盗んでいるわけではないからです(ただし,電気など例外として定められているものも存在することに注意が必要です。)。
次に,詐欺罪も成立しません。
詐欺罪は人を騙した場合に成立するところ,無人のコインパーキングでは人を騙したとはいえないからです。
ではどういった犯罪が成立する可能性があるかというと,Aさんの行為は,偽計業務妨害罪に当たる可能性があります。
偽計を用いて,人の業務を妨害した場合,威力業務妨害罪が成立し,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処せられます(刑法233条)。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「偽計」は,人をだますことや,計略や策略を講じることなどを指し,今回のAさんは料金を。
Aさんの行為により,本来支払われるはずだった駐車料金が支払われず,Vさんの業務が妨害されているとみることができます。
~偽計業務妨害事件の弁護活動~
偽計業務妨害事件では,弁護士に依頼し,被害者との間で示談を成立させたり,被害弁償を行ったりすることで,事件を早期に解決することができる可能性が高まります。
偽計業務妨害罪では,それに該当する行為が非常に広範に捉えられています。
被害が軽微であれば,不起訴処分や略式罰金で処理されることが多いですが,悪質な場合は懲役刑が科されることもあります。
それでも,示談の成立や,真摯な反省を十分に訴えれば,執行猶予判決を得る見込みがある犯罪類型であるともいえます。
刑事事件に強い弁護士に依頼をし,被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが,不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
偽計業務妨害罪に問われてお困りの方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士にご相談下さい。
ストーカー規制法違反で逮捕の少年事件
ストーカー規制法違反で逮捕の少年事件
Bさんは、息子である高校3年生のAさんと、その父親であり夫のCさんの3人で滋賀県大津市に住んでいます。
ある日、Bさんのもとに滋賀県大津北警察署から連絡が来て、「Aさんがとある女性相手にストーカー行為をしている。お母さんにも話を聞きたい」と言われました。
Bさんが滋賀県大津北警察署で話を聞いたところ、Aさんが被害女性に対し、SNSで執拗にメッセージを送ったり、ブログでしつこくコメントを行ったりという行為を繰り返し行っているということが分かりました。
BさんがAさんの監督をきちんと行うことなどを条件に、その日は警告を出されただけで帰宅を許された2人でしたが、しばらく経ったある日、Bさん宅のもとに滋賀県大津北警察署の警察官がやってきて、Aさんをストーカー規制法違反の容疑で逮捕すると告げました。
Aさんは、警告を受けた後もVさんに対するストーカー行為をやめていなかったのです。
Bさんは、自分の力だけでは対処できないのではないかと不安を感じ、少年事件の逮捕から処分が下るまで一貫して事件を任せられる弁護士を探すことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ストーカー規制法違反
ご存知の方も多いと思いますが、平成29年の改正ストーカー規制法施行により、SNSやホームページ上でのメッセージ送信等の行為も、ストーカー規制法の規制対象となることになりました。
ストーカー規制法によると、ストーカー規制法2条に規定されている「つきまとい等」を繰り返すことが「ストーカー行為」となりますが、その「つきまとい等」の中に「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること」(ストーカー規制法2条1項5号)が含まれています。
この「電子メールの送信等」には、メールの送信だけでなく、「特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること」(ストーカー規制法2条2項2号)が含まれます。
これはつまり、コメントやメッセージを送れる機能のついたものについてもストーカー規制法の規制が及ぶということです。
今回のAさんは、SNSでのメッセージ送信やブログ上でのコメント送信を執拗に行っていたということですから、この規定に該当し、ストーカー規制法違反となったのだと考えられます。
ストーカー規制法では、改正に伴いストーカー行為をしただけですぐにストーカー規制法違反として検挙できることとなりました。
しかし、依然としてその前に警告(ストーカー規制法4条)や禁止命令(ストーカー規制法5条)を出されて、警察段階で事件がいったん終了となるケースもあります。
警告や禁止命令を出された場合、それらを守っていけば、刑事事件や少年事件として再び事件化することはありませんし、警告や禁止命令は刑罰ではありませんから、前科もつきません。
ただし、これは警告や禁止命令をきちんと守っていた場合の話です。
警告や禁止命令に従わずにストーカー行為を再び行えば、ストーカー規制法違反として検挙されたり、逮捕されたりすることになります。
今回のAさんは20歳未満のため、原則として刑罰を受けることはありませんが、成人がこうしたストーカー規制法違反となった場合には、
ストーカー行為をした場合:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
禁止命令に反してストーカー行為をした場合:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
となる可能性があります。
・少年によるストーカー規制法違反事件
少年事件で少年が少年院等に入らずとも更生が可能であると主張するためには、少年の生活する環境を更生に適した環境としていくことが大切です。
これがいわゆる環境調整という活動です。
例えば、今回のAさんは、一度母親のBさんと一緒に滋賀県大津北警察署にストーカー規制法違反の容疑で話を聞かれており、そこで警告をされています。
そこで再びストーカー行為をしないように言われ、さらにBさんが監督するということを言っているにも関わらず、再びストーカー行為をするようになってしまっています。
こうした場合、このまま変わらない環境にAさんを置き続けることでAさんの更生は望めないと判断されてしまう可能性があります。
ですから、今までとは違った環境・対策を整え、Aさんの更生を図るのに十分であるということを説得的に主張していく必要があります。
この環境調整の活動こそ、少年事件に強い弁護士にご相談いただきたいのです。
より効果的な環境調整を行うためには、少年事件に関する専門知識や、それをもって第三者的立場から少年事件を見ることが必要とされますし、さらにそれを少年事件の手続きにのっとって適切に主張していかなければなりません。
そうした場では、少年事件に強い弁護士のフルサポートが重要となるでしょう。
少年事件にも対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日、弊所サービスへのお問い合わせやお申込みを受け付けています(0120-631-881)。
滋賀県のストーカー規制法違反事件の逮捕にお困りの際は、遠慮なく上記フリーダイヤルまでお電話ください。
中学生をキャバクラで雇用②風営法違反
中学生をキャバクラで雇用②風営法違反
~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県高島市でキャバクラを経営していました。
ある日、Aさんはキャバクラですでに働いていたBさんという女性からCさんという女性を紹介され、いわゆるキャバ嬢として雇いましたが、Cさんはまだ14歳の中学生でした。
さらに、すでにキャバクラでキャバ嬢として雇っていたBさんも、15歳の中学生でした。
Aさんはそのことを知っていましたが、BさんやCさん自身が働きたいと言っているのだし、BさんやCさんがお酒を飲まなければ問題ないだろうと考えてBさんやCさんをキャバ嬢として働かせていました。
するとある日、滋賀県高島警察署の警察官がAさんのキャバクラを訪れ、Aさんは児童福祉法違反や風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和元年9月26日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)
・中学生をキャバクラで雇用したら風営法違反にも?
前回の記事では、満15歳未満であるCさんをキャバ嬢として酒席に侍らす行為をしたAさんは児童福祉法違反になると考えられるということを取り上げました。
今回の記事では、Aさんのもう1つの逮捕容疑である風営法違反について考えてみましょう。
風営法は、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律で、風俗営業の規制を行い、風俗営業の健全化を図る法律です。
この記事の中では風営法と呼びますが、風適法と略して呼ばれる場合もあります。
風営法における「風俗営業」をする際には、この風営法の中にある決まりを守らなければいけません。
風営法にいう「風俗営業」には、「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」(風営法2条1項1号)が含まれているため、Aさんの経営していたようなキャバクラは「風俗営業」であり、風営法に則って営業させなければならないと考えられます。
そして、この風営法の中には、以下のような規定があります。
風営法22条1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
3号 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。
ここで「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(風営法2条3項)とされています。
こうした定義からすれば、一般にキャバクラでキャバ嬢が客について接客することは、この風営法の「接待」に含まれると考えられます。
ですから、中学生をキャバクラでキャバ嬢として働かせることは、風営法のこの部分に違反することになるのです。
こういった年少者雇用による風営法違反となってしまった場合、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」という法定刑が定められており、この範囲で処罰されることになります(風営法50条1項4号)。
また、仮に風営法の「接待」をしていなかったとしても、風営法では以下のような決まりもあるため、注意が必要です。
風営法22条1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
4号 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
つまり、この禁止されている時間帯に18歳未満の者に「接待」でなくとも客に接する業務に従事させていれば、こちらも未成年者雇用による風営法違反となるのです。
こちらの風営法違反についても先ほど挙げた「接待」についての風営法違反と同様、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」するという法定刑が定められています。
なお、前回の記事で取り上げた児童福祉法にもあったように、風営法にも年齢不知によって処罰を免れることができないという規定があることにも注意が必要です。
風営法50条2項
第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
前回から見てきたように、中学生をキャバクラでキャバ嬢として雇うことは、児童福祉法違反や風営法違反といった犯罪になります。
これは、中学生本人がキャバ嬢として働くことを了承していることや、中学生本人が飲酒しないことといった事情は関係なく成立します。
児童福祉法違反・風営法違反に悩んだら、すぐに弁護士に相談しましょう。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスのご案内をいつでも行っています。
逮捕されてしまった方、捜査を受けて取調べに呼び出されている方、それぞれのニーズに合うサービスをご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
中学生をキャバクラで雇用①児童福祉法違反
中学生をキャバクラで雇用①児童福祉法違反
Aさんは、滋賀県高島市でキャバクラを経営していました。
ある日、Aさんはキャバクラですでに働いていたBさんという女性からCさんという女性を紹介され、いわゆるキャバ嬢として雇いましたが、Cさんはまだ14歳の中学生でした。
さらに、すでにキャバクラでキャバ嬢として雇っていたBさんも、15歳の中学生でした。
Aさんはそのことを知っていましたが、BさんやCさん自身が働きたいと言っているのだし、BさんやCさんがお酒を飲まなければ問題ないだろうと考えてBさんやCさんをキャバ嬢として働かせていました。
するとある日、滋賀県高島警察署の警察官がAさんのキャバクラを訪れ、Aさんは児童福祉法違反や風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和元年9月26日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)
・中学生をキャバクラで雇用したら児童福祉法違反?
今回のAさんは、児童福祉法違反という犯罪と風営法違反という犯罪の容疑で逮捕されているようですが、まずは児童福祉法違反についてみていきましょう。
児童福祉法とは、児童の権利や福祉の保障について定めており、児童福祉に関する機関・団体や施設、事業などについての規定や児童福祉を守るための規定が定められています。
そしてこの児童福祉法には、以下のような規定が存在します。
児童福祉法34条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
5号 満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
キャバクラでは、いわゆるキャバ嬢と呼ばれる従業員が、それぞれの客の席につき、飲酒や飲食の接待をします。
ですから、キャバ嬢としての仕事は「酒席に侍する行為」であり、それを反復継続する仕事ですから「業務として」行うことであるといえます。
つまり、満15歳未満の児童をキャバ嬢として働かせた場合、児童福祉法のこの規定に違反することになるのです。
今回の事例では、Cさんが14歳=満15歳未満ですから、Aさんは児童を酒席に侍らす行為をしたとして児童福祉法違反となることが考えられます。
こうした児童を酒席に侍らす行為による児童福祉法違反となった場合、「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されることになります(児童福祉法60条2項)。
なお、今回のAさんはCさんが満15歳未満であることを知っていたため、児童福祉法違反の行為をしている認識はあったと考えられますが、児童福祉法には、以下のような規定があることにも注意が必要です。
児童福祉法60条4項
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
つまり、今回のような児童福祉法違反では、落ち度なく年齢を確認して雇っていたような場合を除き、「年齢を知らなかった」「児童とは知らなかった」という言い訳は基本的には通用しないということです。
きちんとした手続きや確認を経て雇い入れることはもちろん、もしも児童福祉法違反の容疑をかけられてしまったら、どういった確認方法を取っていたのか等の詳細を弁護士に話し、どういった見通しになるのか検討してもらうことが望ましいでしょう。
・中学生をキャバクラに紹介するのも児童福祉法違反?
実は、今回のケースで児童福祉法違反が問題となるのは、Aさんだけではありません。
Bさんは、14歳であるCさんにキャバクラのキャバ嬢の仕事を紹介してAさんに引き渡していることから、以下の児童福祉法の規定に違反する可能性があります。
児童福祉法34条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
7号 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
※注:「前各号」には、児童福祉法34条5号の満15歳未満を酒席に侍らす行為も含まれています。
この規定には「何人も」とあるため、自身も18歳未満の「児童」であるBさんも、もちろんこの規定に違反してはいけません。
Bさんの場合は児童福祉法違反事件として検挙されたとしても成人の刑事事件と異なる手続きを踏む少年事件として扱われ、その手続きにのっとって進んていくことになると考えられますが、事件の性質上、捜査段階では逮捕などの身体拘束を伴う捜査が行われることも考えられます。
その後の家庭裁判所での調査や審判に早めに備える意味も込めて、早期に少年事件に詳しい弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、逮捕されてしまった方に直接会いに行く初回接見サービスを行っています。
もちろん、在宅捜査を受けている方向けのサービスもご提供していますので、まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
体罰による児童虐待
体罰による児童虐待
滋賀県長浜市に住むAさんには小学校に通う6歳の息子さんがいます。
ある日,いうことをきかなかった息子さんに対し,Aさんは手を上げて叱りました。
翌日,息子さんが学校で殴られたことを話したことから虐待を疑った先生が児童相談所へ相談し,Aさんは児童相談所から事情を聞かれることになりました。
躾のつもりで手を上げたことが虐待に当たり,滋賀県木之本警察署に通報されるのではと不安になったAさんは,弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【躾と虐待】
親などの親権者やその他監護権者が監護する子供の健全な育成のために指導を施すのは当然のことです。
その方法の一つとして子供が不適切な行動をしたり,またはしそうになったときに叱責したり説教したりすることもあるでしょう。
しかし,世の中にはそういったいわゆる躾の一環としてなされた行為が虐待に当たるものとして処罰されたりする場合があることも実情です。
では,どういった場合に躾が虐待と判断されるのでしょうか。
【暴行による虐待】
民法では,親権者は監護や教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができると定めており,懲戒行為が直ちに処罰されるものではないことがわかります。
しかし,懲戒にあたる行為であっても,子どもを殴ったり蹴ったりした場合は刑法上の暴行に当たり暴行罪(刑法第208条)として処罰される可能性が出てきます。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。
今回のAさんの事件ですと,Aさんは息子さんを暴行していますので暴行罪に問われる可能性があります。
実際はその暴行の程度や頻度などを総合的に考慮して逮捕や起訴が差し控えられるケースもあります。
これは,子どもから親を引き離すことや犯罪者の子どもであることのレッテルを周囲から貼られることによって生じる子どもへの不利益を回避するためです。
だからといって,体罰が許されるものではありません。
懲戒権を濫用することによって前科はつかずとも親権を失う場合があります。
どんな理由があろうとも,体罰やそれによる児童虐待を行ってはいけません。
【暴行によらない虐待】
Aさんの場合では直接暴行を加えていますが,他の方法によって「躾」を行うことも考えられます。
例えば,しばらく部屋に閉じ込めたり,人格を否定するような暴言を浴びせたり,一時的に食事を与えなかったりすることなどが挙げられます。
部屋に閉じ込めることは監禁罪(刑法第220条)にあたる可能性が考えられます。
監禁罪の法定刑は3月以上7年以下の懲役です。
著しい暴言を浴びせたり児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食などは,それによって直ちに罪に問われることはないかもしれませんが,これらの行為により子どもの心身に実害が発生した場合は傷害罪(刑法第204条)または過失傷害罪(刑法第209条),あるいは保護責任者不保護罪(刑法第218条)などに問われる可能性があります。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金,過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金または科料で,保護責任者不保護罪の法定刑は3月以上5年以下の懲役です。
暴行による場合とよらない場合とにかかわらず,躾のつもりで行った行為で子どもを死なせてしまった場合にはさらに重い罪に該当する可能性が高くなります。
もし子どもがいいつけに背いたりしても,やはり暴力や心理的圧迫に頼らない方法による懲戒権の行使が望ましいと言えます。
児童虐待を疑われたからといってすぐに逮捕されるとは限りません。
もしそのような疑いが向けられた場合は,早めに弁護士や児童相談所に相談して適切な対応をとることにより,逮捕や起訴の回避を目指すことも考えられます。
親権や監護権をもつ子どもに対する暴行で警察による捜査が開始されてしまった方は,刑事事件に強い弁護士補人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
琵琶湖上で監禁罪・強制わいせつ罪に?②
琵琶湖上で監禁罪・強制わいせつ罪に?②
~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県大津市にある琵琶湖畔で、友人女性のVさんらと遊んでいました。
AさんはVさんに好意を抱いており、Vさんに何度も水上バイクに一緒に乗るよう誘いをかけました。
Vさんは最初嫌がって断っていましたが、Aさんが何度もしつこく誘ったことからその誘いに折れ、「少しだけなら」とAさんと水上バイクに乗りました。
しかしAさんは、水上バイクを発進させると、Vさんが止めるのも聞かずに湖畔から離れた琵琶湖沖まで出て、そこでVさんに抱き着くと無理矢理キスをしました。
その後、Vさんが滋賀県大津北警察署に相談し被害届を出したことがきっかけとなり、Aさんは滋賀県大津北警察署に監禁罪と強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和元年9月24日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・水上で監禁罪に?
前回はAさんの逮捕容疑の1つである強制わいせつ罪について触れましたが、今回の記事ではもう1つの逮捕容疑である監禁罪について触れていきます。
監禁罪は、刑法220条に規定されている犯罪です。
刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
監禁罪は、人の身体・行動の自由を侵害する犯罪で、不法に=正当な行為以外で人を監禁した際に成立します。
正当な行為での逮捕・監禁の例では、刑事事件で逮捕状による逮捕や勾留状による勾留が行われることがよく挙げられます。
一般に監禁罪にいう監禁とは、人の身体を間接的・場所的に拘束してその自由を奪うこと=人を一定の限られた場所から脱出することを不可能又は著しく困難にすることを言います。
例えば、鍵のかかった部屋に誰かを許可なく閉じ込めるようなことをすれば、それは監禁罪にいう監禁行為であると考えられるでしょう。
今回のAさんのケースについて考えてみましょう。
監禁罪や監禁行為という言葉からは、先ほど例に挙げたように、どこかの部屋に誰かを閉じ込めるような態様が想像しやすいでしょう。
しかし、今回のAさんはVさんを水上バイクに乗せて琵琶湖沖に出ているという行為をしているのみで、Vさんを部屋や何か狭いものに閉じ込めたというわけではありません。
これでも監禁罪は成立するのでしょうか。
実は、過去に似たような監禁事件の判例があります。
この事件は、被疑者は被害者を姦淫する目的で、自分の運転する原付自転車の荷台に被害者を乗せ、1,000メートル疾走したという内容でした。
この事件で、最高裁はこの行為を監禁罪に該当するとして監禁罪の成立を認めました(最決昭和38年4月18日)。
それはなぜかというと、先ほど触れた監禁罪の監禁という言葉の意味にあります。
繰り返しますが、監禁罪は人の身体や行動の自由を侵害する犯罪であり、監禁とは人を一定の限られた場所から脱出することを不可能又は著しく困難にすることを言います。
つまり、人の自由を奪う形であれば、何も部屋の中に閉じ込めたり、周囲が何かに囲まれている場所に被害者を置いたりしなくとも、監禁行為となりえるのです。
今回のケースでは、Aさんは水上バイクにVさんを乗せ、Vさんが止めるのも聞かずに琵琶湖沖まで出ています。
Vさんはその行為を止めていたということからも、Vさんの同意なく行われた行為であり、正当な行為であるとはいいがたいでしょう。
そして、水上バイクが走行している間はVさんはそこから脱出することはできませんし、琵琶湖沖に出てしまえば周りは湖ですから、そこでも脱出することは困難であるといえるでしょう。
ですから、AさんはVさんの身体・行動の自由を奪ったと考えられ、監禁罪の容疑がかかることになったのでしょう。
このように、たとえ周りがひらけているような場所であったとしても、状況次第では監禁罪が成立します。
監禁罪が成立しうる状況なのかどうかは、刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでも無料法律相談のご予約を受け付けております。
逮捕されている方向けの初回接見サービスも、同様にいつでもお申し込みいただけます。
まずは遠慮なくお問い合わせください。
琵琶湖上で監禁罪・強制わいせつ罪に?①
琵琶湖上で監禁罪・強制わいせつ罪に?①
Aさんは、滋賀県大津市にある琵琶湖畔で、友人女性のVさんらと遊んでいました。
AさんはVさんに好意を抱いており、Vさんに何度も水上バイクに一緒に乗るよう誘いをかけました。
Vさんは最初嫌がって断っていましたが、Aさんが何度もしつこく誘ったことからその誘いに折れ、「少しだけなら」とAさんと水上バイクに乗りました。
しかしAさんは、水上バイクを発進させると、Vさんが止めるのも聞かずに湖畔から離れた琵琶湖沖まで出て、そこでVさんに抱き着くと無理矢理キスをしました。
その後、Vさんが滋賀県大津北警察署に相談し被害届を出したことがきっかけとなり、Aさんは滋賀県大津北警察署に監禁罪と強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和元年9月24日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・強制わいせつ罪
今回のAさんの逮捕容疑は監禁罪と強制わいせつ罪ですが、まずは強制わいせつ罪に簡単に触れていきましょう。
強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されている犯罪です。
刑法176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪で注意しなければならない点の1つが、被害者が13歳未満であった場合、暴行や脅迫といった行為がなくとも、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立するという点です。
ただし、今回のAさんの事案では、被害者であるVさんはおそらく13歳以上であるため、刑法176条前段にあるように、暴行・脅迫行為を用いてわいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立することになります。
さて、今回のAさんはVさんに抱き着きキスをするという行為をしています。
Aさんの行動を見る限り、目立った暴行・脅迫行為はないように見えるため、本当にこの行為が強制わいせつ罪になるのか、と不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、暴行・脅迫と聞くと、殴って言うことを聞かせたり体を押さえつけたりといったイメージがわきやすいです。
しかし、強制わいせつ罪では、「暴行」は相手の反抗を困難にする程度の不法な有形力の行使であると考えられています。
つまり、簡単に言えば相手が抵抗することが難しいように力を加えることです。
今回のAさんはVさんに抱き着いていることから、VさんがAさんを振り払うなどして抵抗することが難しかったと考えられます。
そこでAさんはキスをしているわけですから、暴行によってわいせつな行為をした=強制わいせつ罪にあたると考えられたのでしょう。
なお、ここで注意すべきなのは、キスがなくとも抱き着く行為だけでも強制わいせつ罪が成立する可能性があるということです。
強制わいせつ罪において、「暴行」と「わいせつ行為」は同じ行為であってもよいとされています。
例えば今回の抱き着く行為では、抱き着くことによって相手の抵抗を難しくするという側面(=「暴行」)と、抱き着くことで「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」(名古屋高裁金沢支判昭和36.5.2)(=「わいせつな行為」)という側面があります。
この場合、抱き着く以外の行為をしていなくとも、「暴行」と「わいせつな行為」という条件を抱き着くという行為1つで満たすことになり、強制わいせつ罪が成立する可能性が出てくるのです。
強制わいせつ事件では、被害者の方への謝罪や弁償を伴う示談交渉や、逮捕されている場合の身柄解放活動など、多くの活動が必要になることが多いです。
こういった活動を全てご自身やそのご家族で行っていくことは非常に難しいことですから、刑事事件のプロである弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ事件を含む刑事事件を多数取り扱っています。
滋賀県の強制わいせつ事件でお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
次回の記事ではAさんのもう1つの逮捕容疑である監禁罪について触れていきます。
原付の2人乗りで道路交通法違反③
原付の2人乗りで道路交通法違反③
~前回からの流れ~
滋賀県長浜市に住むAさん(17歳)は、原付免許を取得し、50ccの原付を運転していました。
ある日、Aさんは友人のVさんを原付の後ろに乗せ、滋賀県長浜市内を通る道路で2人乗りをしていました。
するとその姿を発見したパトカーで巡回中の滋賀県長浜警察署の警察官が、「原付の2人乗りは道路交通法違反になります。そこの原付、停まりなさい」と声をかけてきました。
捕まってはまずいと思ったAさんは、原付を運転してパトカーから逃げましたが、途中で乗用車と衝突してしまいました。
幸いにも死亡した人はいませんでしたが、Aさんは道路交通法違反(定員外乗車)の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(※令和元年9月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・原付2人乗り…少年事件になる?
前回から触れている通り、原付の2人乗りは道路交通法違反となります。
道路交通法57条1項
車両(軽車両を除く。以下この項及び第58条の2から第58条の5までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
(以下略)
道路交通法120条1項10号の2
第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反した者(第118条第1項第2号及び第119条第1項第3号の2に該当する者を除く。)
※注:道路交通法118条・119条は荷物の積載についての罰則。
このように、原付の2人乗りによる道路交通法違反には罰金5万円以下という刑罰が定められていることから、この道路交通法違反で検挙されれば、刑事事件・少年事件となりうることがわかります。
しかし、こうしたいわゆる交通違反事件の場合、反則金制度と呼ばれる制度の適用により、すぐには刑事事件・少年事件とならない可能性があります。
・反則金制度とは
反則金制度とは、正確には「交通反則通告制度」という制度のことで、軽微な交通違反に関して、反則金を納めることで刑事事件・少年事件の手続きに進むことなく終わらせる制度です(道路交通法125条以下参照)。
一般に「青切符」と呼ばれているのはこの反則金制度の適用を受けた場合の交通違反を指します。
今回のAさんがした、原付の2人乗りという道路交通違反は、この反則金制度の対象となる交通違反です。
そのため、Aさんの道路交通法違反事件が反則金制度の適用を受ければ、反則金を払うことによって少年事件となることを避けることができます(なお、反則金を支払わない等をすれば制度の適用はされず、刑事事件・少年事件となります。)。
・原付2人乗りでは少年事件にならない?
では、原付2人乗りでは絶対に少年事件とならないかというと、そうではありません。
少年事件と刑事事件で異なる点の1つとして、少年事件に虞犯(ぐはん)少年という考え方がある点が挙げられます。
虞犯少年とは、簡単に言えば、今は少年事件を起こしているわけではないものの、環境等から将来犯罪をしたり犯罪に触れる行為のおそれのある少年のことを言い、少年法ではこの虞犯少年についても家庭裁判所の調査・審判を行うことができるとされています。
少年法では虞犯少年に該当すると判断する要件を挙げており、その事由の1つに該当し、環境等を考慮したうえで虞犯少年かどうかが判断されます。
今回のAさんでいえば、原付の2人乗りは反則金制度を適用して少年事件とならなかったとしても、頻繁に夜中に原付を乗り回していた、家に帰っていなかった等の他の事情があれば、虞犯少年として少年事件化することも考えられます。
また、今回のAさんのように、パトカーから停止を求められて逃げ、事故を起こしてしまったような場合で、同乗者や衝突した車に乗っていた人に怪我をさせてしまった/死亡させてしまったような場合には、原付の2人乗りによる道路交通法違反だけでなく、自動車運転処罰法にある過失運転致死傷罪が適用されることも考えられます。
そうなれば、過失運転致死傷罪は反則金制度のようなものはありませんから、すぐに少年事件・刑事事件として立件されることになるでしょう。
このように、たとえ軽微な交通違反がきっかけであったとしても、少年事件として事件化する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、滋賀県の少年事件にも刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応しています。
弁護士へのご相談予約は0120-631-881でいつでも受け付けていますので、お悩みの方は遠慮なくお問い合わせください。