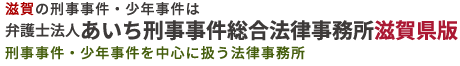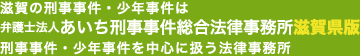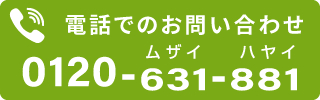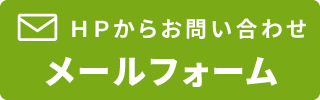Archive for the ‘未分類’ Category
言いがかりをつけて恐喝事件に発展
言いがかりをつけて恐喝事件に発展
言いがかりをつけて恐喝事件に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市に住んでいる20代のAさんは、友人数人と一緒に出掛けた際、通行人のVさんとぶつかったことをきっかけとしてVさんに対して「喧嘩売ってるのか」などと言いがかりをつけました。
言いがかりをつけたことから口論になったAさんらとVさんでしたが、だんだんとエスカレートし、AさんらはVさんを取り囲んで逃げられないようにしたうえで、「俺たちのバックにはヤクザがついている」「今100万円支払えば穏便に済ませてやる」「支払わなければ痛い目に合う」などと脅しました。
VさんはAさんらの言葉や態度に恐怖を感じ、「100万円など持っていないからひとまずこれで許してくれ」と所持していた5万円をAさんらに渡しました。
そしてVさんは、どうにかAさんらの隙を見て逃げ出すと、近くにあった滋賀県長浜警察署の交番に駆け込み、被害を申告しました。
そして、Aさんらは滋賀県長浜警察署に恐喝罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんの両親は、Aさんが恐喝罪の容疑で逮捕されたと聞き、どうすればよいのか弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・恐喝罪
今回のAさんの事例では、AさんらがVさんに言いがかりをつけたことをきっかけとして恐喝事件まで発展しているようです。
言いがかりをきっかけに口論となり、そこからエスカレートして謝罪を要求するうちに金銭などの要求に発展し、恐喝事件となってしまうケースはままあるようです。
では、Aさんの逮捕容疑となっている恐喝罪はどういった犯罪なのでしょうか。
刑法第249条第1項(恐喝罪)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
条文を見ると「人を恐喝して」「財物を交付させ」るというステップを踏むことで恐喝罪が成立することが分かります。
ここで、「恐喝」するとはどういうことか確認しておきましょう。
恐喝罪において、「人を恐喝」するということは、財物の交付に向けて暴行または脅迫を行うことであると考えられています。
つまり、財物を引き渡させるために暴行や脅迫を用いて財物を要求すると「恐喝」をしたということになるのです。
注意しなければいけないのは、恐喝罪が成立するのはこの暴行や脅迫が相手の抵抗を押さえつけない程度のものであった場合であるということです。
用いられた暴行や脅迫が相手の抵抗を押さえつけるほどの強さであった場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。
今回のAさんの事例では、AさんらはVさんに対して自分たちのバックにヤクザがいることや、痛い目に合わせることといった、Vさんの身体に危害を加える旨を伝えることでVさんに脅しをかけ、現金を要求しています。
Aさんらの言動から、これらの脅迫はVさんの抵抗を全く押さえつけるほどの強さのものではないでしょう。
そしてその脅迫行為によってVさんが恐怖を抱き、Aさんらに5万円の現金という「財物」を引き渡していることから、Aさんらには恐喝罪が成立するのだと考えられます。
・恐喝事件で逮捕されたら
恐喝罪は、その法定刑(刑罰)が「10年以下の懲役」となっており、罰金刑の定めがありません。
つまり、恐喝罪で起訴されるということは公開の法廷に立って裁判を受けるということであり、恐喝罪で有罪となるということは、執行猶予が付かない限り刑務所に行くということです。
これだけ重い刑罰の定められている犯罪であることから、恐喝事件では被疑者が逃亡や証拠隠滅をするおそれがあると判断され、逮捕・勾留による身体拘束の上捜査されることも少なくありません。
さらに、今回のAさんの事例のように、複数人が恐喝事件の当事者として存在する=共犯者のいる事件では、口裏合わせなどを防ぐためにも逮捕・勾留による身体拘束の上捜査されることが多いです。
逮捕されてしまえば、当然自由に刑事事件について相談することもできませんし、会社や学校に通うこともできなくなります。
だからこそ、早い段階で弁護士と直接接見することで、刑事事件自体の相談はもちろん、釈放や寛大な処分の獲得のために取り得る活動について詳しく聞いておくことが重要なのです。
これは被疑者本人だけでなく、ご家族などの周りの方にも言えることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後から迅速に弁護士と接見できるよう、初回接見サービスのお申込み・お問い合わせを24時間いつでも受け付けています。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
免停中の運転で無免許運転に
免停中の運転で無免許運転に
免停中の運転で無免許運転に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県米原市に住む会社員のAさんは、通勤に自動車を使用しており、毎日運転していました。
しかし、度重なる交通違反により、Aさんは90日間の免許停止処分を受けることになりました。
免停となったAさんでしたが、通勤に車を使っていたため、「運転できなくなるのは困る。免停と言っても単に停止されただけで運転免許は持っているのだから問題ないだろう」などと考え、免停となった後も運転を続けていました。
そうして免停期間も運転をしていたAさんでしたが、職場からの帰宅途中、交通検問をしていた滋賀県米原警察署の警察官により、免停期間中の運転であることが分かり、無免許運転の容疑で刑事事件の被疑者として捜査されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・免停中の運転は無免許運転
無免許運転という言葉を聞くと、運転免許自体を持っていない人が自動車の運転をすることだとイメージしやすいかもしれません。
ですが、今回のAさんのように、たとえ運転免許を取得していたとしても、その免許が免停となっている最中に運転してしまえば、それも無免許運転ということになります。
免停期間中は道路交通法の以下の条文にもある通り、免許の効力が停止されているわけですから、その期間内については運転免許を持っていない無免許の状態と同じということになるのです。
道路交通法103条1項(免許の取り消し、停止等)
免許(仮免許を除く。以下第106条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
ただし、第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
(略)
5号 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
6号 重大違反唆し等をしたとき。
7号 道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く。)。
8号 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
今回のAさんのように、交通違反をしてしまって免停となった場合には、この道路交通法103条1項5号等に該当するとして免停となっていることが考えられるでしょう。
この免停という処分は、あくまで運転免許に関する行政上の処分であり、刑事罰というわけではありません。
ですから、免停になったからといって前科がつくわけではありません。
交通違反による道路交通法違反では、交通違反の種類にはよるものの、反則金制度という制度があり、反則金を支払うことで刑事手続に移行せずに交通違反を処理する制度があるため、反則金を支払って免停となった、というだけでは刑事事件となって前科が付くということに必ずしも結びつかないのです。
しかし、今回のAさんは無免許運転をしたとして刑事事件の被疑者として捜査されているようです。
実は、無免許運転は前述の反則金制度の対象外となる交通違反で、無免許運転をして検挙されるということは、免停や免許取り消しといった行政上の処分だけでなく、刑事罰を受けるかどうかという刑事事件としての手続きと処分を受けなければならないということになります。
道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
この条文にも、無免許運転について「法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。」と書いてあることからも、今回のAさんの免停中の運転が無免許運転として処罰されることがわかります。
たかが無免許運転、ばれなければ大丈夫と考える人もいるかもしれませんが、無免許運転の刑事罰はこれほど重いものとなっていることもあり、態様によってはその場で逮捕されてしまう可能性もありますから、無免許運転とならないよう注意が必要です。
それでも無免許運転をしてしまった、刑事事件の被疑者となってしまったという場合には、今後の対応について弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、こうした交通違反に関連する刑事事件のご相談も承っています。
まずはお気軽に、0120-631-881までお問い合わせください。
友達を匿って犯人蔵匿罪に?
友達を匿って犯人蔵匿罪に?
友達を匿って犯人蔵匿罪に問われるのかというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
Aさんの住む滋賀県彦根市の閑静な住宅街でお年寄りが狙われる窃盗事件が発生しました。
数日後、Aさんの自宅にAさんの友人であるBさんが慌ててやってくると「この前起きた窃盗事件の容疑をかけられている。やっていないのに警察官が自宅前に張り込んでいるようだ。数時間でいいから匿ってくれ」と言ってきました。
Aさんは、大切な友達を冤罪で困らせるわけにはいかないと思い、Bさんを家に招き入れて自室に隠れているよう言いました。
BさんがAさん宅に来てから数時間後に滋賀県彦根警察署の警察官がAさん宅に訪ねてきましたが、Aさんは居留守を使いその場を切り抜けました。
警察官が帰って行き少し安堵したAさんでしたが、無実と信じていたとはいえ匿うと罪に問われるのではないかと不安に思うようになりました。
そこでAさんは、Bさんを帰宅させた後、弁護士に無料相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・犯人蔵匿罪
今回の事例のAさんは、友達のBさんを匿ったことで何か犯罪になるのではないかと不安に思っているようです。
今回の事例では、AさんがBさんを自宅で隠れさせた行為について、犯人蔵匿罪という犯罪が成立するかどうかということが問題になるでしょう。
刑法第103条(犯人蔵匿罪等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
まず犯人蔵匿罪における「罰金以上の刑に当たる罪」とは、法定刑に罰金以上の刑を含む罪をいいます。
また、犯人蔵匿罪における「罪を犯した者」とは、犯罪の嫌疑を受けて捜査又は訴追されている者をいいます。
すなわち、実際に罪を犯した人、いわゆる真犯人だけでなく、実際には冤罪である無実の人であっても容疑をかけられて捜査されていれば犯人蔵匿罪のいう「罪を犯した者」となり、犯人蔵匿罪の対象となります。
では、なぜ犯人蔵匿罪はその対象を実際に罪を犯した真犯人だけに限定していないのでしょうか。
犯人蔵匿罪が保護している利益(保護法益)は、「国家の刑事司法作用の適正な運用」であると考えられています。
つまり、犯罪を正しく捜査し正しく裁判手続きを進行することを守るために犯人蔵匿罪があるのです。
正しい捜査・正しい裁判手続きを守るためには犯人だけでなく犯罪の嫌疑を受けている者についても支障なく捜査できることが望ましいということなのです。
また、仮に捜査されている人が真犯人ではない場合でも、早期に嫌疑が晴れることで早期真犯人の捜査に移れるため事件解明に近づきます。
そのためにはまずは捜査されている人の捜査がなされなければならないということになります。
このような理由から、犯罪の嫌疑を受けて捜査又は訴追されている者も犯人蔵匿罪の対象にされていると解釈されているのです。
次に、犯人蔵匿罪の「蔵匿」したとは、官憲による発見逮捕を免れるべき隠匿場所を提供することをいいます。
他方、「隠避」とは、蔵匿以外の方法で官憲による発見逮捕を免れしめる一切の行為をいいます。
たとえば、犯人に逃走の為の車を用意することなどは「隠避」に当たると言えます。
今回の事例についてあてはめてみましょう。
窃盗罪で捜査されていることをAさんに伝えており、さらに警察官がBさんを捜索していることからすると、Bさんは窃盗罪の被疑者として嫌疑を受けているということでしょう。
そして、Bさんが嫌疑を受けている窃盗罪は罰金刑以上を含む犯罪です。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
よって、Bさんは犯人蔵匿罪のいう「罰金以上の刑に当たる罪」「を犯した者」といえ、Aさんもそれを認識していたと考えられます。
BさんがBさんの主張通り本当は無実であっても、捜査対象者であれば「罪を犯した者」とされるのは上述の通りです。
そのBさんについて、Aさんは警察官がBさんを捜索している時に、Bさんが警察官から発見されないようにするため、自室を提供しています。
よって、Aさんは「蔵匿」したといえ、Aさんには犯人蔵匿罪が成立すると考えられるのです。
・犯人蔵匿事件と弁護活動
犯人蔵匿事件では、被害者が存在しませんから、示談交渉はできません。
しかし、今回の事例のように、「犯人」が突然押し掛けてきたことや、昔馴染みで断り切れなかったことなど情状事実を主張することで、より有利な処分や判決を得られる可能性があります。
こうした主張のためにも、刑事事件の専門家である弁護士のサポートは重要です。
加えて、取調べの対応を随時相談するためにも、弁護士にサポートを受けることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、犯人蔵匿事件などの刑事事件を専門に扱っています。
耳慣れない犯罪ではどう対応すべきか分からないことも多いですから、まずは遠慮なく弁護士にご相談ください。
弁護士に少年鑑別所での面会を依頼
弁護士に少年鑑別所での面会を依頼
弁護士に少年鑑別所での面会を依頼するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
17歳のAさんは、滋賀県近江八幡市で複数回の盗撮事件を起こしてしまい、滋賀県近江八幡警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕されたその日のうちに釈放されたのですが、事件が大津家庭裁判所に送致されると、観護措置がとられることとなり、大津少年鑑別所に収容されることになりました。
逮捕されたその日のうちに警察署から釈放されていたため、もう身体拘束されることはないだろうと考えていたAさんとその両親は、少年鑑別所に収容となったことに不安を覚え、少年事件にも対応している弁護士に相談し、まずはAさんに面会に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年鑑別所とは
少年鑑別所とは、少年の資質や環境などを専門家が専門的に調査するための施設です。
少年事件を起こした少年が少年鑑別所に収容されるパターンは主に2つあります。
まずは、捜査段階=被疑者として警察や検察に捜査されている段階で行われる「勾留に代わる観護措置」となった場合です。
「勾留に代わる観護措置」となった場合、被疑者である少年の留置場所は、警察署の留置所ではなく少年鑑別所となります。
「勾留に代わる観護措置」とは、逮捕後の10日間、少年鑑別所に身体拘束をして捜査を行うもので、少年事件独特の手続きです。
この「勾留に代わる観護措置」となった場合、成人の刑事事件に見られるような勾留の延長は認められず、最大10日間の身体拘束期間の後は事件はすぐに家庭裁判所に送致されることになります。
そして、「勾留に代わる観護措置」の後、家庭裁判所に事件が送致された場合、次に説明する「観護措置」に自動的に切り替わり、引き続き少年鑑別所に身体拘束されることになります。
次に、事件が捜査機関から家庭裁判所に送致された後、「観護措置」となって、少年鑑別所に入ることになった場合です。
この場合の観護措置とは、通常4週間~8週間程度、少年鑑別所において、少年の性格等を専門的に調査するものを言います。
最初に触れた少年鑑別所の役割は、この「観護措置」の際に発揮されます。
「観護措置」中、少年は少年鑑別所に収容され、家庭裁判所調査官や少年鑑別所の技師等から調査されます。
・少年鑑別所での面会
少年事件を起こした少年が少年鑑別所に収容された場合、警察署で面会するのとは何が異なるのでしょうか。
まず、多くの少年鑑別所では、警察署と違ってアクリル板の仕切りなしで面会することが可能となります(ただし、少年鑑別所によっては、勾留に代わる観護措置の場合はアクリル板のある部屋で面会させる場所もあります。)。
少年本人と遮るものなくコミュニケーションを取ることができるため、ご家族にとっても少年にとっても、ストレスの少ない面会ができます。
また、警察署での一般面会は近親者以外も可能ですが、少年鑑別所での一般面会は、近親者や保護者に限られており、誰でも面会できるというわけではありません。
なお、面会時間が10分~20分と限られていたり、受付が平日の昼間のみであったりすることは、少年鑑別所でも警察署でも変わりません。
しかし、土日祝日の面会については、弁護士であっても予約が必要であったりできなかったりするため、そういった点では警察署などの面会とは異なる部分です。
どちらにせよ、ご家族の面会の際には事前に少年鑑別所にその日・その時間帯の面会が可能かどうか確認されてから面会に向かわれることをおすすめします。
・少年事件と身体拘束
今回のAさんらは、逮捕後に釈放されたことで今後の身体拘束はないと思っていたところへ少年鑑別所への収容措置がとられています。
先ほど挙げた通り、少年事件では家庭裁判所に送致された後に「観護措置」という措置がとられることがあり、そうなると一定期間少年鑑別所への収容が行われることになります。
ですから、少年事件の場合、捜査段階と家庭裁判所での調査段階の2回、身体拘束のリスクがあるということになります。
観護措置はより専門的な調査が行われる機会でもあるため、少年にとってデメリットばかりがあるというわけではありません。
しかし、長期間身体拘束されることによるデメリットが大きいこともまた事実ですから、弁護士に相談・依頼して適切な措置をとってもらえるよう活動してもらうことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の付添人活動はもちろん、少年鑑別所への接見依頼も承っております。
少年鑑別所への接見のご依頼やご相談のご予約は、0120-631-881までお問い合わせください。
飲酒運転を隠すために人身事故後に飲酒で逮捕?
飲酒運転を隠すために人身事故後に飲酒で逮捕?
飲酒運転を隠すために人身事故後に飲酒し逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県甲賀市に住んでいるAさんは、仕事帰りに居酒屋で飲酒しましたが、「自宅は近くにあるのだから問題ないだろう」と飲酒運転をして帰路につきました。
しかしその道中で、Aさんは通行人のVさんと接触してVさんに怪我を負わせる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは、このままでは飲酒運転をして人身事故を起こしたことがばれてしまうと焦り、どうにか飲酒運転をしていなかったことにできないかと通報する前にコンビニへ行くと、そこで酒を購入し、その場で飲酒しました。
そして、Aさんは通報によって駆け付けた滋賀県甲賀警察署の警察官には「人身事故を起こして焦ってしまったので気を保とうと人身事故後に飲酒した」と話しました。
ですが、捜査の結果、Aさんが居酒屋で飲酒してから飲酒運転で帰路についたことや、飲酒運転をごまかすために人身事故後に飲酒をしたことが発覚し、Aさんは滋賀県甲賀警察署に過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪(自動車運転処罰法違反)の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕とAさんにかかっている容疑を警察官から知らされたAさんの家族は、聞きなれない犯罪名に困惑し、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪
Aさんの逮捕容疑は過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪という名前の犯罪です。
長く聞きなれない犯罪であるために、どういった犯罪なのかご存知でない方も少なくないでしょう。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪は、いわゆる「自動車運転処罰法」(正式名称「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)の中で定められている犯罪の1つです。
自動車運転処罰法第4条(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪)
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処する。
条文が長く分かりづらいかもしれませんが、簡単にまとめると、自動車の運転に影響が出る程度の飲酒運転をして人身事故を起こした場合に、飲酒運転の発覚を免れるためにさらに飲酒を重ねたり水を飲むなどしてアルコール数値を減らしたりするなどすることで成立するのが、この過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪です。
今回のAさんのように、飲酒運転をして人身事故を起こし、その後に重ねて飲酒をすることはまさにこの過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪となります。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪は、いわゆる「逃げ得」=飲酒運転をして人身事故を起こした場合、その場から逃げるなどして飲酒運転が発覚しないようにした方が、成立する犯罪によって受ける可能性のある刑罰の重さが軽くなってしまうというケースをなくすために作られた犯罪です。
飲酒運転の度合いによっては、人身事故によって問われる犯罪が危険運転致死傷罪という最長で20年の懲役が科せられる犯罪に問われることになりますが、逃げて飲酒運転の発覚を免れればひき逃げと過失運転致死傷罪が成立するにとどまり、その場合は最長で15年の懲役となることから、「(逃げて)飲酒運転の発覚を免れた方が得」とされてしまいます。
そういったことを防ぐために、人身事故後に飲酒運転の発覚を防ごうとすることも犯罪としたのが過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪なのです。
・事故後に飲酒することが飲酒運転を免れる行為になるのか?
ここで、逃げたり水を飲んだりすることで飲酒運転の発覚を免れようとすることはともかく、事故後にさらに飲酒をすることでどうして飲酒運転を免れることにつながるのか、と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、人身事故を起こした後にお酒を飲んでしまえば、飲酒運転していたと判断するための呼気検査や血液検査をしてアルコールが検出されても、運転前に飲んでいたお酒のアルコールなのか、事故後に飲んだお酒のアルコールなのか見分けがつかなくなってしまいます。
そうなると、飲酒運転をしていたのかどうか(運転をしていた時点でアルコールが検出できる状態にあったのかどうか)が分からなくなってしまうため、事故後に重ねて飲酒をする行為も飲酒運転を免れる行為とされているのです。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、最長で12年の懲役に科せられる非常に重い犯罪です。
今回の事例のAさんは、一度現場を離れているようですから、そこをひき逃げと判断されてさらに重い刑罰が科せられる可能性もあります(ひき逃げと過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が成立した場合、最長で18年の懲役となります。)。
人身事故も刑事事件であり、今回のようになかなか馴染みのない名前の犯罪の容疑がかかることもありますから、まずは迅速に弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が逮捕から刑事手続きの終了までフルサポートしています。
刑事事件にお困りの際は、ご遠慮なくご相談ください。
売春あっせん行為で売春防止法違反・児童福祉法違反事件
売春あっせん行為で売春防止法違反・児童福祉法違反事件
売春あっせん行為で売春防止法違反・児童福祉法違反事件になったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
18歳のAさんは、滋賀県守山市で一人暮らしをしていました。
Aさんは、知人の会社員男性Bさんが「若い子と性行為をやりたい」と言っていることと、知人の高校生Cさん(16歳)が「性行為混みでいいからパパ活をしたい」と言っていることを知り、2人を紹介して引き合わせると、2人が会って性行為をする際に自分の住んでいた部屋を貸すなどしました。
しかし、Cさんが滋賀県守山警察署に補導されたことをきっかけに発覚し、Aさんは売春防止法違反と児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんとは離れて暮らしていたAさんの両親は、滋賀県守山警察署にAさんが逮捕されたという知らせを聞き、とにかく早く何かしらの対応をしなければいけないと考え、滋賀県の逮捕に対応できるという弁護士に接見に行ってもらうことにしました。
(※令和3年3月2日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・売春防止法
売春とは、金銭などの対価のかわりに不特定の相手と性交をすることを指します。
売春については、「売春防止法」という法律で売春をすることも、売春の相手となることも禁止されています。
売春防止法第3条
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
この売春防止法第3条には刑罰の規定がなく、たとえ売春をしたり売春の相手となったりしても、それによって刑罰が科されるということはありません(売春防止法違反という犯罪にはなります。)。
しかし、売春防止法違反という犯罪全てに刑罰がないというわけではなく、売春の周旋行為や売春のための場所を提供する行為によって売春防止法違反となった場合には以下のように刑罰が科せられるほか、売春をさせる行為を業として行った場合や売春の勧誘をしたような場合には刑罰が科せられるように定められています。
売春防止法第6条
売春の周旋をした者は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
売春防止法第11条
第1項 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。
今回のAさんは未成年のため刑罰を受けることは原則としてありませんが、売春の「周旋」(=あっせん)や、売春をすることを知りながら(=「情を知って」)売春を行う場所として自身の部屋を貸している(=「売春を行う場所を提供」)ことから、これらの行為による売春防止法違反という犯罪に問われたと考えられます。
ここで注意が必要なのは、Aさんが売春を周旋した当事者の1人であるCさんが16歳の高校生であり、Aさんもそのことを知っていたということです。
18歳未満の児童が金銭などの対価と引き換えに性交をした場合、それは児童買春と考えられます。
児童買春の周旋も、売春の周旋同様に児童買春禁止法によって規制されている行為ですから、Aさんには売春防止法ではなく児童買春防止法違反という犯罪が成立することになる可能性もあるのです。
逮捕された時点ではAさんの逮捕容疑は売春防止法違反となっていますが、捜査が進むにつれて被疑罪名が変更になる可能性があるのです。
なお、児童買春の周旋による児童買春禁止法違反の刑罰は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」となっています(児童買春禁止法第5条第1項)。
・児童福祉法違反
今回のAさんには、売春防止法違反だけでなく児童福祉法違反という別の犯罪の容疑もかけられているようです。
児童福祉法とは、名前のとおり児童の福祉を保障する法律です。
児童の福祉を守るため、児童福祉法では児童にさせてはいけない行為を定めています。
その中の1つに、以下のようなものがあります。
児童福祉法第34条第1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第6号 児童に淫行をさせる行為
児童福祉法第第60条第1項
第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
児童福祉法における「児童」も、児童買春禁止法同様18歳未満の者を指しています。
今回の事例では、Aさんは「児童」であるCさんにBさんとの性交等をさせた=「淫行をさせ」たと判断されたのでしょう。
注意が必要なのは、児童に淫行させたことによる児童福祉法違反は、今回のAさんが容疑に問われているような児童に第三者に対する淫行をさせた場合だけでなく、児童に自分に対して淫行をさせた場合にも成立するということです。
・弁護活動
今回のAさんは未成年であることから、少年事件の手続によって処分が決められます。
少年の更生に重きをおく少年事件では、示談交渉などの被害者対応や身柄解放活動といった活動だけでなく、Aさん自身が今回のような事件を起こしてしまった原因をつきとめ、再度同じことを繰り返さないようにすることが重要です。
Aさんの周囲の環境を整え改善するためには、少年事件に詳しい専門家のアドバイスが効果的です。
そのためにも、早期に少年事件に対応している弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件も専門的に取り扱っています。
少年事件で必要と考えられる活動はまだまだ一般に浸透していない部分も多いですから、まずはどういった活動が考えられるのかだけでも専門家に聞いておくことが重要です。
お気軽に弊所弁護士までご相談ください(お問い合わせ:0120-631-881)。
無理矢理でなくても強制わいせつ罪に?
無理矢理でなくても強制わいせつ罪に?
無理矢理でなくても強制わいせつ罪に問われたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県草津市で小学生向けの学生塾をしていたAさんは、自身の塾の生徒であるVさん(小学5年生)を指導するうちに、Vさんが性的な行為に興味があるという話を聞きました。
Vさんからキスをしてほしいと言われたAさんは、Vさんへの指導後にVさんに対してキスをするなどするようになりました。
しかし、Vさんの様子がおかしいと感じたVさんの両親がVさんから話を聞いたことでAさんの行為が発覚。
Vさんの両親が滋賀県草津警察署に被害届を提出したことで、Aさんは滋賀県草津警察署に強制わいせつ事件の被疑者として逮捕され、捜査されることとなってしまいました。
Aさんとしては、Vさんに無理矢理わいせつな行為をしたわけではないのに強制わいせつ罪という犯罪に問われていることに疑問を感じています。
Aさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に、なぜ自分が強制わいせつ罪の容疑に問われているのか相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・無理矢理でなくても強制わいせつ罪に
強制わいせつ罪という罪名を聞いて、皆さんはどのような事件を想像するでしょうか。
罪名に「強制」という言葉が入っていることから、文字通り「強制的にわいせつな行為をする」という事件を想像する方が多いのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんは、Vさんにキスを無理強いしたというわけではないのに強制わいせつ罪の容疑をかけられて逮捕されているようです。
このように、無理矢理わいせつな行為をしたわけではないのに強制わいせつ罪に問われることがあるのでしょうか。
まずは強制わいせつ罪の条文を確認してみましょう。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪の条文の前段では、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした者に強制わいせつ罪が成立する旨が定められており、これは世間一般の強制わいせつ罪のイメージに合致するものでしょう。
しかし、ここで注意しなければいけないのは、この「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立するのは「13歳以上の者」への行為と限定されているということです。
これに対して、相手が13歳未満の者であった場合については、強制わいせつ罪の条文の後段に定められています。
13歳未満の者が相手であった場合、強制わいせつ罪は「わいせつな行為をした」だけで成立します。
つまり、被害者の年齢次第では、「暴行又は脅迫」という手段が用いられなくとも、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立することになるのです。
「わいせつな行為をした」だけで成立するのですから、相手がわいせつな行為に同意していたとしても強制わいせつ罪が成立することになります。
当然、13歳未満の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした場合にも強制わいせつ罪は成立しますが、無理矢理していないから強制わいせつ罪にはならないというわけではないのです。
今回の事例のAさんは、小学5年生のVさん相手にキスなどをしているようです。
小学5年生のVさんは「13歳未満の者」であることから、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪が成立することになり、Aさんが無理矢理キスをしたわけではなくとも強制わいせつ罪に問われることになります。
・強制わいせつ事件の弁護活動
被疑者自身が容疑を認めている強制わいせつ事件の弁護活動例としては、被害者との示談交渉が挙げられます。
刑法改正によって親告罪ではなくなったものの、強制わいせつ事件の起訴・不起訴の判断には被害者への謝罪・示談ができているかどうかという部分は重視される事情です。
起訴されたとしても、被害者への謝罪・示談ができているという事情があることで執行猶予の獲得や刑罰の減軽に有利になります。
ただし、強制わいせつ罪のような性犯罪では、被害者の処罰感情や恐怖の感情が大きいと予想されます。
特に、今回のケースのように被害者が未成年である場合には、示談交渉の相手が被害者の保護者(多くの場合ご両親)となることから、その処罰感情が大きいことは当然のことでしょう。
こういったケースで当事者同士で謝罪や示談交渉をしようとしても、そもそも連絡を取ること自体を拒否されてしまったり、連絡を取っても余計にこじれてしまったりというおそれがあります。
弁護士を間にはさむことで、被害者側としては直接加害者である被疑者と連絡を取らずに済むというメリットも出てくることから、謝罪や示談交渉の場についてもらいやすくなるという効果が期待できます。
今回のAさんのように逮捕され身体拘束されているケースでは、示談締結により釈放を求める際にも有利な事情となりますから、早い段階で弁護士に相談・依頼して活動を開始することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が強制わいせつ事件を含む刑事事件に迅速に対応します。
刑事事件では、なぜ自分がその犯罪の容疑をかけられているのか、どのような対応が考えられ、どういった弁護活動が可能なのかといったことを把握した上で手続に対応していくことが重要です。
そのためにも、まずは弁護士から直接アドバイスをもらうことが必要です。
お問い合わせは0120-631-881で24時間受け付けていますので、まずはお気軽にお電話ください。
DV容疑での逮捕に対応
DV容疑での逮捕に対応
DV容疑での逮捕に弁護士に対応してもらうケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県大津市に、妻であるVさんと2人で暮らしています。
ある日、AさんとVさんは激しい口論となり、ヒートアップしたAさんは咄嗟にVさんのことを殴ってしまいました。
Vさんはその際に全治1週間のけがを負ってしまい、さらに、騒ぎを聞いた近所の人が通報したことで滋賀県大津警察署の警察官が現場に駆け付けました。
Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまい、日常的にDVをしていたのではないかと疑われています。
Aさんは、ただの夫婦喧嘩がヒートアップしただけであったのに逮捕される事態となってしまい、非常に混乱しています。
どうやらVさんも、まさか刑事事件になるような大事になるとは思いもよらず、困っているようです。
こうした事態を知ったAさんの両親は、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談し、Aさんのもとに会いにいってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・DV容疑をかけられてしまったら
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、家庭内暴力のことを指します。
家庭内での出来事だから大事にならないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、たとえ夫婦間で起きたことであっても、物理的な暴力をふるってしまえば暴行罪や傷害罪が成立することになりますし、無理矢理性交をすれば強制性交等罪にもなりえます。
さらに、心理的圧迫をすれば脅迫罪や強要罪にもなりえます。
今回のAさんは、Vさんを殴ってしまって怪我をさせてしまったため、傷害罪の容疑をかけられています。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
身内で起こったことだから刑事事件化しないということはありませんから、家庭内で起こったことだからとDVを甘く見てはいけません。
また、DV事件の被害者と加害者は同じ家庭内にいる=同居していることが多いため、DV事件によっては被害者と加害者の接触を避ける意味で逮捕・勾留といった身体拘束がなされる可能性も十分あります。
今回のAさんは、Vさんとの夫婦喧嘩によってDVの容疑をかけられてしまったようです。
しかし、AさんもVさんも、DVは存在せずただの夫婦喧嘩がヒートアップしてしまったという認識のようです。
こうした場合、継続的なDV行為が存在しないことや、被害者の立場であるVさんが処罰を求めていないこと、今後同様のことが起きないようにするための防止策等を主張し、身柄解放や不起訴処分を目指していくことが考えられます。
例えば、今回の事例であれば、Aさんの両親がAさんとVさんの夫婦の様子を定期的に確認するといった第三者がフォロー・監督できる体制を整えることも手段の1つです。
こうした防止策などを考えることはもちろん、その防止策を効果的に主張することで、釈放や刑罰の減軽が期待できます。
そのためには、第三者的立場であり、かつ刑事事件の専門家である弁護士に早い段階で相談・依頼することが重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、DVに関わる刑事事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
DV事件の場合、家庭内のトラブルであるために他人に相談しづらいという面もありますが、弁護士であれば守秘義務もありますから安心してご相談いただけます。
専門家のアドバイスによって見えてくることも多くありますから、まずはお気軽にご相談ください。
他人のペットを傷つけてしまったら
他人のペットを傷つけてしまったら
他人のペットを傷つけてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県大津市に住んでいるAさんは、隣人であるVさんがペットとして飼っている犬が吠えかかってくることに苛立っており、ある日、ついにVさん宅の犬を蹴飛ばして怪我を負わせてしまいました。
ペットの犬が怪我をしていることに気がついたVさんは、防犯カメラの映像などからAさんが暴行を加えて怪我をさせたことを知り、滋賀県大津北警察署に被害を届け出ました。
被害届を受理した滋賀県大津北警察署は、Aさんを逮捕。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、突然の知らせに驚き、ひとまず弁護士に詳しい話を聞いてきてもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・他人のペットに暴行…傷つけてしまったら
今回のAさんは、Vさんのペットである犬に暴行し、怪我を負わせてしまっています。
このケースのように、他人のペットである動物を傷つけたときに成立する可能性のある犯罪としては、まずは刑法の器物損壊罪が挙げられます。
刑法第261条(器物損壊罪)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「前3条に規定するもの」とは、文書や建造物等のことで、それ以外のものが器物損壊罪の対象(客体)となります。
生きている動物を「物」と扱うことに違和感のある方もいらっしゃるかもしれませんが、法律的には動物も「物」として扱われるため、他人にペットとして飼われている動物も器物損壊罪の客体=「他人の物」となります。
器物損壊罪の「他人の物を」「傷害」するという言葉からも、他人が飼っているペットが器物損壊罪の対象として想定されていることが分かります。
なお、「傷害」とは書かれているものの、他人のペットを殺してしまったような場合でも、器物損壊罪の「傷害」に当てはまり、器物損壊罪が成立することにも注意が必要です。
今回の事例では、AさんはVさんの飼っているペットの犬=器物損壊罪でいう「他人の物」に暴行を加え、怪我をさせている=「傷害」しているため、器物損壊罪が成立すると考えられます。
・自分のペットを傷つけたら?
先ほど確認したように、器物損壊罪はあくまで「他人の物」を傷つけた時に成立する犯罪です。
ということは、ペットを傷つけた際、それが他人のペットでなかった場合、自分のペットを傷つけてしまった場合には器物損壊罪とならないのでしょうか。
刑法には、以下のような規定があります。
刑法第262条
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
この条文によると、自分の飼っているペットであっても、差押えを受けていたり、物権を負担していたり、賃貸したりしてているときは、器物損壊罪の対象となることがわかります。
このような場合には、たとえ自分のペットであっても傷つければ器物損壊罪の成立が問題となります。
・ペットを傷つけると器物損壊罪以外の犯罪も
ペットを傷つけることによって、器物損壊罪以外の犯罪も成立の可能性があります。
ある特定の種の動物を傷つけた場合には、動物愛護法違反が成立する可能性が出てくるためです。
動物愛護法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)は、主としてペット販売や取引を行う事業者に対して規制を加える法律です。
しかし、一般の飼い主やさらには飼い主でない人もこの法律による取締りを受けることがあります。
動物愛護法第44条第1項
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
動物愛護法における「愛護動物」とは、牛、馬、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるとその他人が飼育している動物のうち哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものを指します。
刑法に対して動物愛護法の処罰規定は特別法に当たりますので、愛護動物をみだりに殺傷したといえる場合には器物損壊罪ではなく動物愛護法違反が適用されます。
そして、動物愛護法では、動物の種類によっては器物損壊罪のように他人の物か自分の物か区別されていないため、たとえ自分のペットであっても傷つければ動物愛護法違反となる可能性が出てきます。
今回のAさんは、Vさんのペットである犬=「愛護動物」を傷つけていますから、動物愛護法違反となると考えられるのです。
動物愛護法違反は、器物損壊罪と異なり親告罪ではないため、告訴がなくとも起訴される可能性があり、さらにその刑罰も重い物となっています。
迅速に刑事事件に対応できる弁護士に相談することが求められるでしょう。
「人を傷つけるわけではないから」と考える方もいるかもしれませんが、ペットを傷つけることも非常に重い犯罪です。
そういったことをしないよう気をつけることはもちろんですが、もしも当事者となってしまったら、弁護士に相談して対応を練っていくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の初回接見サービスや初回無料法律相談を受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。
自転車を無断使用したら窃盗罪?
自転車を無断使用したら窃盗罪?
自転車を無断使用して窃盗罪に問われてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県高島市に住んでいるAさんは、近所にあるコンビニへ買い物に行くために出かけようと思ったところ、同じマンションに住んでいるVさんの自転車が鍵がかかっていない状態で停められているのを見つけました。
Aさんは、「どうせ1時間かからない程度で帰ってくるのだから借りよう」と思いつき、Vさんの自転車を無断使用しました。
Aさんが40分ほど経ったあとにコンビニから帰ってくると、自転車がないことに気付いたVさんが窃盗罪の被害に遭ったと通報していたようで、通報によって駆け付けた滋賀県高島警察署の警察官がAさんに窃盗罪の容疑で話を聞きたいと言ってきました。
(※この事例はフィクションです。)
・無断使用と窃盗罪
今回のAさんが容疑をかけられている窃盗罪は、刑法の以下の条文に定められています。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回のAさんは、Vさんの自転車を勝手に持ち出して無断使用していることから、この窃盗罪に当てはまりそうに見えます。
しかし、窃盗罪をはじめとする奪取罪(窃盗罪・強盗罪・詐欺罪・恐喝罪)については、条文に書かれた成立要件(刑法では「構成要件」と呼ばれたりします。)のほかにも、成立するための条件があります。
それが「不法領得の意思」という意思です。
つまり、窃盗罪では、条文に書かれている条件+「不法領得の意思」の2つが充たされる場合に窃盗罪が成立することになります。
では、その「不法領得の意思」とはどういった意思のことを指すのでしょうか。
不法領得の意思とは、「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に利用し、または処分する意思」のことをいいます。
なぜ条文に書かれていないのに窃盗罪の成立に不法領得の意思が必要とされるのかというと、刑法が財産犯(窃盗罪など財産に対する犯罪のこと)の処罰対象を毀棄行為(壊すこと)と領得行為(他人の物を自分の物にしてしまうこと)とに分けているというところに理由があります。
「不法領得の意思」で区別しなければ、毀棄行為と領得行為が区別できないのです。
ここで、Aさんのケースに当てはめて考えてみましょう。
AさんはVさんの自転車を無断使用していることから、自転車の占有(支配・管理すること)を勝手に自分に写していると考えられますが、「すぐに返しておこう」と考えていることから不法領得の意思があるとは考えにくいと言えます。
しかし、Aさんが「不法領得の意思はない」と言えばそのようにすんなり判断されるというものではなく、無断使用の時間の長さなどから総合的に判断されることになります。
無断使用のために借りた時間が長ければ長いほど不法領得の意思が認められやすくなると言えますし、無断使用したのが自転車なのか自動車なのかと言ったことも不法領得の意思の有無の判断に考慮されます。
例えば、過去の判例で、夜中に自動車を5時間使用するつもりで運転し約4時間後に逮捕されたという事件で、不法領得の意思を認め、窃盗罪の成立を認定したものがあります(最決昭和55.10.30)。
今回のAさんのケースでは、Aさんが無断使用を開始してから40分しか経っていませんし、無断使用をしたものも自転車であるということから、不法領得の意思がないと主張できる可能性も十分あるでしょう。
無断使用はそもそも避けるべきではありますが、今回のように窃盗事件を疑われてしまったら、弁護士のサポートを仰ぐべきでしょう。
上記のような専門的な分析も必要になるため、取調べ等の対応を弁護士のアドバイスを受けながら対応することが効果的と言えるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談を受け付けています。
無断使用による窃盗事件についてお悩みの際は、お気軽にご相談ください。