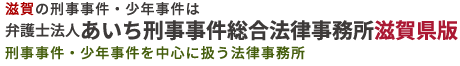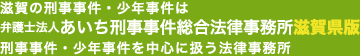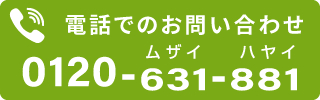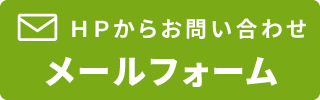Author Archive
逮捕されていない少年事件
逮捕されていない少年事件
逮捕されていない少年事件での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aくん(15歳)は、滋賀県長浜市に住んでいる学生です。
ある日、Aくんは滋賀県長浜市内にある駅の階段で、前を歩いていた女性Vさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮してしまいました。
目撃者が通報したことで、Aくんはすぐに滋賀県長浜警察署の警察官に任意同行されることになりました。
しかし、Aくんは逮捕されることなくその日のうちに帰宅を許され、後日また滋賀県長浜警察署で取調べを受けることになりました。
Aくんの両親は、逮捕されないのであれば大事ではないのだろうから弁護士は不要と考えているようです。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕されなくても弁護士は重要
上記事例のAくんは、盗撮の疑いで滋賀県長浜警察署に任意同行され、逮捕されることなくその日のうちに帰宅を許されたようです。
このような場合、今後は取調べのために何度か警察署に呼び出される、いわゆる在宅事件として捜査が進むことになるでしょう。
Aくんもまた後日滋賀県長浜警察署で取調べを受けることになっているようです。
逮捕されずに手続きが進んでいく在宅事件の場合、たしかに大事になっているという感覚はわきにくいかもしれません。
ですが、本当にAくんの両親が考えているように、弁護士は必要ないのでしょうか。
実は、逮捕されていない在宅事件においても、弁護士の役割は非常に大きいものなのです。
例えば、Aくんの場合、まだ未成年の少年ですから、成人の刑事事件とは異なる少年事件として手続きが進んでいくでしょう。
少年事件の場合、たとえ捜査段階で逮捕されずに在宅事件として進められていたとしても、事件が家庭裁判所に送致された後、観護措置という措置が取られれば、少年は一定期間(平均的には4週間程度)、鑑別所に収容されることとなってしまいます。
そうなれば、学校へ行けなかったり、就業先に行けなかったりといった不都合が出てくることはもちろん、少年本人や家族にも負担がかかってしまうことになりかねません。
さらに、家庭裁判所へ送致されるまでの取調べ等の手続きは、成人の刑事事件とほとんど同様の手続きによって行われます。
たとえ未成年でも、被疑者として1人で取調べに臨まなければならないのです。
未成熟な少年が、捜査官相手にきちんと主張したいことを貫けるかどうか、という問題も出てきます。
かけられている容疑が冤罪であった場合はもちろん、そうでなくとも目的や手段、実際にやったこと等を自分の認識通り話せるかどうかによって、処分にも大きな影響が出てしまう可能性があります。
また、Aくんのような盗撮事件の場合では、被害者の方への謝罪や賠償も考えられるでしょう。
盗撮事件においては、被害者の方は見ず知らずの方であることも多いです。
そうした中で謝罪や賠償を行っていくには、まずは被害者の方と連絡を取るために連絡先を教えてもらわなければなりませんが、通常、捜査機関は盗撮をした当事者に直接被害者の連絡先を教えることはしません。
盗撮された被害者としては、当然加害者側に対して処罰感情や恐怖を感じていることも多いためです。
そうすると、被害者に対して自分たちだけで謝罪や弁償をするということは難しくなってしまいます。
そして、少年事件の場合、終局処分は家庭裁判所が少年の更生にとって適切な処分を判断することで決まります。
少年の更生にとってよい環境を自分たちで作れているかどうかという点は、この判断の際に重視されることの1つです。
そのためには、少年の更生のためにどういったことが必要なのか、現在の環境からどこをどう変えるべきなのか適切に把握し、行動する必要があります。
このように、たとえ逮捕をされていなくとも、刑事事件・少年事件の専門的知識が必要な活動は多く存在します。
特に、少年事件の場合は、前述のように家庭裁判所に事件が送致されてからも身体拘束のリスクがある上に、終局処分での判断が少年の更生に適切かどうかという点で考えられることから、逮捕されていないから軽く済むに決まっている、ということはありません。
滋賀県の少年事件でお困りの際は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、盗撮事件などの性犯罪から、傷害事件などの暴力犯罪、万引きなどの財産犯罪まで、幅広く活動しています。
初回無料法律相談もございますので、逮捕されていないけど少年事件を起こしてしまったという方は、お気軽にご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
公然わいせつ事件と示談
公然わいせつ事件と示談
公然わいせつ事件と示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県米原市に住むAさんは,他人に自分の裸を見せることで興奮する嗜好を持っていました。
ある日,Aさんは自分の欲求を満たすために,滋賀県米原市の路上で,下半身を露出して歩いていました。
それを見た滋賀県米原市在住のWさんは驚き,滋賀県米原警察署に通報しました。
Aさんは,駆け付けた滋賀県米原警察署の警察官に公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は,滋賀県米原警察署から,Aさんを公然わいせつ事件の被疑者として逮捕したことを知らされ,急いで弁護士に相談しました。
Aさんの家族としては,どうにか穏便に解決したいと思っていますが,インターネットで公然わいせつ事件は示談で解決できないという記事を見かけたため,不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然とわいせつな行為をした場合,公然わいせつ罪(刑法174条)が成立します。
公然わいせつ罪が成立する場合,6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料が科せられます。
刑法174条(公然わいせつ罪)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
拘留とは,30日未満の間身体を拘束される刑罰です(刑法16条)。
科料とは,1000円以上1万円未満の財産刑です(刑法17条)。
このように,公然わいせつ罪は比較的軽い刑罰も定めらている犯罪ではありますが,現行犯の場合,Aさんのように逮捕されてしまうことも考えられます。
公然わいせつ罪のいう「公然と」とは,わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態をいいます(最決昭和32年5月22日)。
Aさんは路上で下半身を露出していたのですから,わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態にしたといえます。
さらに,Aさんは自分の下半身を人に見せつけて興奮しようと下半身を露出していたのですから,「わいせつな行為」をしたともいえるでしょう。
こうしたことから,Aさん行為には公然わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。
~公然わいせつ罪と示談~
公然わいせつ罪は,善良な風俗を保護するために定められている犯罪であるとされています。
つまり,法律上,公然わいせつ罪にあたる行為をするということは,特定の誰かの権利を侵害するということではなく,社会の善良な風俗を侵害したという考えになるのです。
こういったことから,公然わいせつ罪では,法律上被害者は存在しない(被害を受けたのは社会全体であるため)と考えられています。
そのため,公然わいせつ事件で示談はできない,ということになるのです。
しかし,公然わいせつ事件では,今回の事例のWさんのように,公然わいせつ行為を目撃してしまった人がいることも多いです。
こうした目撃者の人たちは,公然わいせつ行為によって実質的に被害を受けたとも考えられるため,目撃者に対して謝罪をしたり苦痛を受けたことによる被害弁償をしたりして示談することで有利な処分を目指していくことも考えられます。
法律上被害者が存在しない犯罪であるため,被害者の存在する犯罪に比べて示談したからといって効果が劇的にあるというほどではないかもしれませんが,不起訴処分等を目指すうえで有利な事情にはなりえます。
そのほか,贖罪寄付をしたり,再犯防止策を示すことで,より有利な処分を目指すことが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,公然わいせつ事件のご相談も承っています。
まずはお気軽に,お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
転売目的の窃盗事件で逮捕
転売目的の窃盗事件で逮捕
転売目的の窃盗事件で逮捕されたケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県東近江市在住のAさんは,交際しているVさんがコレクションしていたアニメのDVDを,滋賀県東近江市内にあるVさん宅からVさんに無断で持ち出し,すぐに滋賀県東近江市にある内のリサイクルショップに売りました。
DVDのコレクションがなくなったことに気が付いたVさんがAさんを問い詰めると,AさんがVさんに無断でDVDを持ち出し転売していたことが発覚。
Vさんは滋賀県東近江警察署に相談し,その結果,Aさんは窃盗罪の容疑で滋賀県東近江警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は,滋賀県の刑事事件に対応している弁護士事務所に問い合わせ,弁護士に,逮捕されているAさんのもとに行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
~転売目的の窃盗事件~
他人の財物を盗んだ(窃取した)者には,窃盗罪(刑法235条)が成立し,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回の事例で見てみると,VさんのアニメDVDはAさんから見て「他人の財物」に当たります。
窃盗罪のいう「窃取」とは,その物の持ち主の意思に反してその物の支配・管理する権限を自分のもとに置き,その物を自分の物としてしまうことを指しています。
今回の事例のDVDは,Vさんの持ち物であり,Vさんの家にあったものですから,客観的にも主観的にもDVDはVさんが支配・管理していたものと考えられるでしょう。
AさんがVさんに無断で当該DVDを持ち出す行為は,DVDを支配・管理している権限をVさんの意思に反して移転する行為であるといえるでしょう。
つまり,AさんがDVDを持ち出した行為は窃盗罪の「窃取」に当たると考えられるのです。
さらにAさんは,当該DVDをすぐリサイクルショップに転売しており,DVDを持ち出す時点で転売目的であったことが推認されます。
DVDを転売するということは,DVDを自分の物として扱い処分しているということですから,窃盗罪の成立に必要とされている「不法領得の意思」=権利者(今回の事例で言えばDVDの持ち主であるVさん)を排除して他人の物を自己の所有物としてふるまい,その経済的用法に従い利用または処分する意思もあつと考えられます。
これらのことから,Aさんの行為は窃盗罪に当たると考えられるのです。
窃盗罪は,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と条文にある通り,その刑罰には幅があります。
つまり,窃盗事件と一口に言っても,どういった態様で被害金額がどれほどで何件の窃盗事件を起こしたのかといった個々の事情が考慮され,この幅広い法定刑の範囲で刑罰が決められるのです。
今回のAさんの事例のような転売目的の窃盗事件では,転売目的という部分が悪質であると判断され,厳しい判断が下されることも少なくありません。
だからこそ,転売目的の窃盗事件を起こしてしまったら,早い段階で弁護士に相談してみることが重要でしょう。
~転売目的の窃盗事件で他に成立しうる犯罪は?~
実は,今回のAさんの事例のような転売目的の窃盗事件では,窃盗罪以外にも犯罪が成立している可能性があります。
それは,リサイクルショップに対する詐欺罪です。
刑法246条1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
リサイクルショップに物を売る際には,多くの場合,その物が盗品等ではないかという確認を取られます。
盗品を盗品であると知って譲り受けてしまうと,盗品関与罪という別の犯罪が成立してしまうことから,Aさんのように転売目的で窃盗行為をしている人から盗品を買わないようにするために確認を取っているのです。
Aさんのように転売目的で窃盗事件を起こし,さらにリサイクルショップに転売までしている場合,この確認で嘘をついて転売し,代金を受け取っている可能性があるのです。
そうなると,リサイクルショップの店員を騙して=「人を欺いて」,代金を引き渡させている=「財物を交付させた」ということになり,詐欺罪が成立することになってしまう可能性があるのです。
転売目的の窃盗事件では,転売目的の窃盗行為に成立する窃盗罪だけでなく,転売行為で詐欺罪も成立する可能性があるため,被害者が複数に渡ったり,対応しなければいけない被疑事実が複数あったりするため,刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が複数の被疑事実・被害者の存在する刑事事件のサポートも丁寧に対応いたします。
滋賀県の転売目的の窃盗事件など,刑事事件にお困りの際は弊所弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
スクールセクハラで刑事事件に
スクールセクハラで刑事事件に
スクールセクハラが刑事事件に発展したケース委について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県近江八幡市にある中学校で教師として勤務していました。
ある日、Aさんは校長に呼び出されると、「Aさんの担任しているクラスのVさん(12歳)の両親が、自分の娘がAさんからスクールセクハラを受けた、滋賀県近江八幡警察署に通報すると言っている」と伝えられました。
その話はAさんにとって全く身に覚えのない話であったのですが、その後、Aさんは滋賀県近江八幡警察署に強制わいせつ罪の容疑で話を聞かれることになってしまいました。
身に覚えのないことで刑事事件の被疑者となってしまい困ったAさんは、滋賀県近江八幡警察署での取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に対応を相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・スクールセクハラ
スクールセクハラとは、スクール・セクシュアル・ハラスメントの略称であり、学校など教育現場におけるセクハラ=性的な嫌がらせのことを指します。
スクールセクハラは、教師対生徒で起こるケースがよく取り上げられますが、教師対教師、生徒対生徒の場合でも学校などの教育現場で起こればスクールセクハラと呼ばれるようです。
・スクールセクハラは犯罪になる?
通常のセクハラでも犯罪に該当する行為であれば刑事事件となり問題になります。
当然、スクールセクハラという呼ばれ方をしていても、それが法律に触れる行為であれば刑事事件になります。
例えば、今回のAさんは強制わいせつ罪の容疑をかけられ取調べに呼ばれているようです。
刑法176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
スクールセクハラで暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をしていたような場合には、この条文に該当し、強制わいせつ罪に問われることになります。
また、スクールセクハラの相手が13歳未満であれば、暴行・脅迫がなくともわいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となることになります。
スクールセクハラの起こった場所が中学校や小学校であった場合には、特にこの刑法176条後段に該当して強制わいせつ罪となりうることにも注意が必要です。
他にも、強制性交等罪や各都道府県の迷惑防止条例違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反など、スクールセクハラによって成立する可能性のある犯罪は多く存在します。
繰り返しになりますが、たとえ学校内で起こったことであっても法律に違反すれば犯罪であり、刑事事件・少年事件となります。
スクールセクハラといえば聞こえは軽いかもしれませんが、捜査や逮捕の可能性が出てくるのです。
・スクールセクハラで冤罪を主張したい
上記事例のAさんは、スクールセクハラによる強制わいせつ罪の容疑をかけられ取調べに呼ばれています。
しかし、Aさんはスクールセクハラの事実について見に覚えがないと困っているようです。
Aさんの認識が正しいものであるなら、この強制わいせつ罪についてはAさんは冤罪の容疑をかけられているということになります。
今現在、Aさんは逮捕等の身体拘束はされていませんが、特にAさんのように否認をしている刑事事件では、証拠隠滅や逃亡の可能性を考慮され、逮捕による身体拘束がなされやすいと言われています。
最初は逮捕されずに取調べられていた刑事事件でも、取調べを経た後に逮捕されることもあります。
逮捕されてしまえば、周囲の人と自由に連絡を取ることもできず、Aさん本人からすれば、やっていないことを疑われ続ける環境に1人で耐え続けなければならない環境は非常に負担の大きいものです。
そうでなくともプロの捜査官相手に1人で冤罪を主張することは非常に負担の大きいことであるといえるでしょう。
こうした場合にこそ活用していただきたいのが、刑事事件に強い弁護士の存在です。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも初回無料法律相談や初回接見サービスのご依頼を受け付けています。
法律のプロから直接アドバイスをもらうことができるのは、取調べに対応していかなければならない被疑者本人にとって非常にメリットの大きいことです。
特に否認の刑事事件では、取調べの対応の仕方1つで冤罪を回避できることもありますから、冤罪に困ったらすぐにでも弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスは0120-631-881でいつでもお問い合わせいただけます。
まずはお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
少年の強盗致傷事件で逮捕②試験観察
少年の強盗致傷事件で逮捕②試験観察
少年の強盗致傷事件で逮捕されてしまったケースで、特に試験観察処分を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県甲賀市に住んでいるAさん(15歳)は、普段からあまり素行がよくなく、仲良くしている友人たちと一緒に学校をさぼったり、夜遅くまで帰宅せずにうろついたりといったことを繰り返していました。
ある日、Aさんは自由に使えるお小遣いが少ないことに困り友人たちと話したところ、一緒に夜道を1人で歩いている人から財布を奪おうという話になりました。
そこでAさんらは、滋賀県甲賀市の道路を1人で歩いていたVさん(56歳)に集団で殴りかかるなどして襲い、無理矢理財布を奪いました。
財布から現金を奪ったAさんらは、これに味をしめ、付近でもう何件か同様の事件を起こしました。
しかし、Vさん等被害者から被害の申告を受けた滋賀県甲賀警察署が捜査をした結果、Aさんらの犯行であることが発覚し、Aさんは自宅を訪れた滋賀県甲賀警察署の警察官に強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、普段から素行はよくなかったものの、まさかAさんが警察沙汰になるような事件を起こし逮捕までされてしまうとは思ってもいなかったため、慌てて弁護士に相談し、今後について詳しい話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・捜査段階での弁護活動
今回のAさんの事例では、強盗致傷罪という重い犯罪をして逮捕されていることももちろん気を付けなければならない点の1つなのですが、Aさんが友人たちと起こした強盗致傷事件(または強盗事件)が1件ではないということにも注意が必要です。
このように現在捜査されている事件以外にも事件を起こしている場合、つまり、いわゆる「余罪」がある場合には、理論上その余罪の数だけ逮捕や勾留が繰り返され、身体拘束が長期化することも考えられるからです。
そうなれば、捜査段階だけでも1か月以上の身体拘束をされてしまうおそれもあります。
そこで、弁護士に釈放のための活動をしてもらったり、再逮捕・再勾留を防ぐための交渉をしてもらうことが重要となってくるでしょう。
今回のAさんの事例では、Aさん本人の反省やご家族がAさんの監督に協力すること、被害者の方との示談交渉等、釈放のための環境を弁護士とともに作り上げること、それを弁護士に適切に主張してもらうことによって、釈放を求めていくことが考えられます。
・家庭裁判所送致後の付添人活動~試験観察を目指す
今回のAさんのような強盗致傷事件や強盗事件を何件も起こしてしまっているケースでは、最終的に少年院送致という処分が取られる可能性が考えられます。
少年事件で原則として最終的に取られる処分は、少年の更生を実現させるために適切であると考えられる処分です。
今回のAさんは、普段の素行も悪く、友人たちと一緒になって強盗事件や強盗致傷事件を起こしてしまっています。
Aさんの更生のためには一度その環境からAさん自身を切り離し、再犯をしないために教育をしていく必要がある=少年院に収容して規律のある生活を送ってもらう必要があると判断される可能性があるのです。
少年院は成人の刑事事件でいう刑務所とは異なり、少年事件を起こしてしまった少年が更生するための矯正教育のための施設です。
ですから、少年院に行くことが少年事件を起こしてしまった少年にとって全くメリットのないことであるというわけではありません。
少年院で規則正しい生活を送り、生活指導や勉強についての指導、職業訓練等を受けることで立ち直っていく少年もいます。
しかし、少年院に行くということは良くも悪くも前述したように少年事件を起こすまで生活してきた環境から切り離されてしまうことになります。
ですから、それまで通り学校や職場に通うことはできなくなりますし、家族とも自由に会うことができなくなります。
一定程度の期間社会から離れて過ごすことが少年へのデメリットとなってしまうことも十分考えられるのです。
では、その少年院送致を回避するにはどういった活動が考えられるでしょうか。
今回のAさんのような事例では、まずは試験観察という処分を獲得することを目標として活動していくことが考えられます。
試験観察とは、文字通り、最終的な処分を決める前に、試験的に少年を一定期間家庭裁判所調査官の観察に付すことを指します。
例えば、少年を一定期間民間の篤志家の元に預けて生活環境を変え規則正しい生活を送らせる等し、その間家庭裁判所調査官が少年にアドバイスや面接等を重ねるといった例が挙げられます。
こうした試験観察期間中、家庭裁判所調査官は少年が自分自身の問題と向き合えているか、改善しようとできているか等を観察し、その観察結果も踏まえて少年に対する最終的な処分を決定するのです。
試験観察は、少年事件で少年に対する最終処分を直ちに決めることが難しいと判断された場合に付されます。
つまり、少年院送致が見込まれるような少年事件であっても、少年が更生できる環境を整え、まずは様子を見てほしいと試験観察を目指し、試験観察期間中に少年の更生が社会内でも可能であることを示すことができれば、少年院送致を回避できる可能性もあるということなのです。
仮に少年院送致となってしまった場合であっても、少年が戻ってくる環境を整えておくことは今後のためにも重要ですから、試験観察の獲得を目指すことも兼ねて、弁護士と協力しながら少年の更生に適切な環境を作っていくことが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も専門的に扱う法律事務所です。
強盗致傷事件などの重大な少年事件にお困りの際や、少年事件で試験観察を目指したいとお悩みの際は、一度弊所弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
少年の強盗致傷事件で逮捕①強盗致傷罪
少年の強盗致傷事件で逮捕①強盗致傷罪
少年の強盗致傷事件で逮捕されてしまったケースの、特に強盗致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県甲賀市に住んでいるAさん(15歳)は、普段からあまり素行がよくなく、仲良くしている友人たちと一緒に学校をさぼったり、夜遅くまで帰宅せずにうろついたりといったことを繰り返していました。
ある日、Aさんは自由に使えるお小遣いが少ないことに困り友人たちと話したところ、一緒に夜道を1人で歩いている人から財布を奪おうという話になりました。
そこでAさんらは、滋賀県甲賀市の道路を1人で歩いていたVさん(56歳)に集団で殴りかかるなどして襲い、無理矢理財布を奪いました。
財布から現金を奪ったAさんらは、これに味をしめ、付近でもう何件か同様の事件を起こしました。
しかし、Vさん等被害者から被害の申告を受けた滋賀県甲賀警察署が捜査をした結果、Aさんらの犯行であることが発覚し、Aさんは自宅を訪れた滋賀県甲賀警察署の警察官に強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、普段から素行はよくなかったものの、まさかAさんが警察沙汰になるような事件を起こし逮捕までされてしまうとは思ってもいなかったため、慌てて弁護士に相談し、今後について詳しい話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強盗致傷罪
今回のAさんは強盗致傷罪の容疑で逮捕されていますが、人に暴行して財布などの金品を奪えば強盗罪が、さらにその強盗行為の際に人に怪我をさせてしまえば強盗致傷罪が成立することが考えられます。
刑法236条1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
刑法240条(強盗致傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗罪が成立するには、相手の抵抗を押さえつける程度の強さの「暴行又は脅迫」を用いて他人の財物をその人の意思に反して奪うことが必要です。
「暴行」は有形力の行使のことを指していますから、今回のAさんらのように通行人に対して殴りかかるといった行為はまさに「暴行」であるといえるでしょう。
なお、こうした直接人に向けた「暴行」以外にも、物に対して向けた「暴行」(=間接的な人に対する「暴行」)でも強盗罪の「暴行」にあたることにも注意が必要です。
今回のAさんらは、数人で通行人に襲い掛かっていますから、通行人の抵抗を押さえつけるほどの強さの「暴行」を用いてその財物=財布等の金品を奪っていると考えることができます。
ですから、まずAさんらには強盗罪の成立が考えられるところです。
しかし、今回のAさんらの逮捕容疑は強盗致傷罪です。
条文を見て分かるように、強盗致傷罪は「強盗が」「人を負傷させたとき」に成立する罪です。
「強盗が」とは、「強盗犯人が」という意味です。
つまり、強盗犯人ではない人が誰かを怪我させてしまったとしても強盗致傷罪が成立することにはなりません。
ですが、先ほどまで見てきた通り今回の事例のAさんらには強盗罪が成立すると考えられますので、Aさんらはこの「強盗が」という条文に該当することになります。
そして強盗致傷罪の「人を負傷させたとき」とは、そのまま他人に傷害を加えてしまった時ということを指します。
今回の事例の中では、Vさんら被害者が怪我をしてしまったという詳しい描写はありませんが、おそらく事件後に被害者から診断書等が出され、被害者が怪我をしていることが分かったために強盗致傷罪の容疑となったのでしょう。
ただし、強盗犯人がいつ人に怪我をさせてしまっても強盗致傷罪が成立するのだということではありません。
強盗致傷罪が成立するためには、傷害の結果は強盗の機会に行われた行為から生じたものでなければならないとされています。
すなわち、例えばAさんらが強盗事件を起こし、その後に全く関係のないところで喧嘩となり相手に傷害を負わせたとしてもそれは強盗致傷罪とはならないのです。
・強盗致傷罪は重い犯罪?
強盗致傷罪は、その法定刑が「無期又は6年以上の懲役」となっていることからも、非常に重い犯罪であることがわかります。
法定刑に無期懲役が含まれていることから、強盗致傷罪で起訴されれば裁判員裁判を受けることにもなります。
Aさんのような少年事件では原則として起訴されることも刑罰を受けることはありませんが、それでもこれだけの重い犯罪を行ってしまったことから、それまでの環境に大きな問題があると考えられる可能性は高いでしょう。
なお、少年事件であっても「逆送」されて強盗致傷罪で起訴されれば裁判員裁判を受けることになります。
だからこそ、子どもが強盗致傷事件で逮捕されてしまったら、早めに弁護士に相談し、早い段階からできる活動と準備を重ねていくことが大切なのです。
では、こういった少年事件ではどういった活動が考えられ、どういった処分を目指していくことになるのでしょうか。
次回の記事で詳しく取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強盗致傷事件のような重大犯罪の少年事件・刑事事件のご相談・ご依頼も承っています。
強盗致傷事件で子どもが逮捕されてしまったら、まずは弊所弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
恋人に連絡先を消させるデートDVで強要事件に?
恋人に連絡先を消させるデートDVで強要事件に?
恋人に連絡先を消させるデートDVで強要事件に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
高校生のAくん(17歳)は、Aくんと同じ滋賀県守山市にある高校に通う同級生のVさん(17歳)と交際しています。
Aくんは、恋人であるVさんのことを好意的に思うあまり、Vさんに自分以外の異性と接してほしくないと思うようになりました。
そこで、AくんはVさんのスマートフォンや、入っている無料通話アプリやSNSアプリに登録されているAくん以外の男性の連絡先をAくんの目の前で消すように言いました。
しかし、Vさんは「そんなことする必要はないだろう」とAくんの要求に全く取り合わない様子でした。
VさんがAくんの要求を拒否したことでAくんはかっとなり、近くにあった机を蹴りつけ、再度Vさんに連絡先を目の前で消すよう言いました。
VさんはAくんの様子に怖くなり、Aくんの要求通り連絡先を消しました。
その後、Vさんはもしかしら今後はもっとひどいことをAくんに要求されるのではないか、と不安になって滋賀県守山警察署に相談に行きました。
そしてそのVさんの相談がきっかけで、Aくんは強要罪の容疑で滋賀県守山警察署で取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・恋人に連絡先を消させて強要事件に?
今回のAくんは、Vさんに好意を寄せるあまり、Vさんに自分以外の異性の連絡先を消すよう要求し、実行させています。
単なる恋人同士のすれ違いやトラブルのようにも見える今回の事例ですが、実はこういった行為は「デートDV」とも呼ばれており、軽く考えてはいけない問題なのです。
単純にDV(ドメスティックバイオレンス)といった場合には家庭内暴力のことを指すのに対し、デートDVとは結婚前の恋人同士での間で起こる暴力のこと、つまり、交際中の相手に身体的・精神的・性的に暴力を与える又は受けることを指します。
DVというと、先ほど挙げた家庭内暴力、すなわち夫婦の間や親子の間、兄弟間での暴力というイメージがありますが、デートDVは若い恋人たちなどの中で起こってしまうDVの話なのです。
今回の事例のAくんは、Vさんに無理矢理自分以外の男性の連絡先を消させていますが、これはつまり、Vさんがしたくないことを無理矢理実行させているということです。
こうした行為によって、Aくんが容疑をかけられている強要罪が成立する可能性が出てきます。
刑法223条(強要罪)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪の条文にある「暴行」は、直接相手に振るわれるものでなくとも「暴行」であると認められます。
例えばAくんの事例では、近くにあった机を蹴りつけることでVさんを畏怖させています。
こうした間接的な暴行でも、「暴行を用いて」いると判断される可能性があるのです。
加えて、VさんがAくんの言う通りに連絡先を消すことは、もちろんVさんにとって義務のあることではありません。
誰の連絡先を登録して誰と連絡を取るかは、基本的には個人の自由であるはずです。
こうしたことから、今回のAくんの行為は強要罪にあたる可能性があるといえるのです。
このように、デートDVは通常のDV同様、相手に直接暴力をふるうことだけではありません。
そして、こちらも通常のDVと同様、法律に「デートDV」という言葉が使われ、行為が禁止されたり犯罪とされているわけではありません。
Aさんの行為が強要罪に当たりうるように、デートDVの態様によって刑法やその他の法律に定められている犯罪がそれぞれ適用されうるということになります。
デートDVの場合、一見DVという言葉とは関わりのないようにも思えるAさんとVさんのような若い恋人たちが少年事件の当事者になってしまうことも考えられます。
デートDVをしないように気を付けたり見守ったりすることはもちろん、もしもデートDVに関わる少年事件を起こしてしまったら、少年事件に強い弁護士に相談し、少年事件自体への対応はもちろん、今後どのようにして同じことを繰り返さないようにしていくかという活動にも取り組んでいくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が初回無料の法律相談を行っています。
まずは話だけしてみたいという方も、初回無料でご利用いただけますから、お気軽にご相談いただけます。
お問い合わせは0120-631-881で24時間いつでも受け付けておりますので、遠慮なくお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
SNSでの名誉毀損事件③
SNSでの名誉毀損事件③
SNSでの名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、滋賀県草津市にある勤め先の同僚Vさんとその上司が不倫関係にあることを知りました。
日頃からVさんのことをよく思っていなかったAさんは、Vさんが上司と不倫している旨の書き込みをSNS上にて公開しました。
Vさんはその書き込みに気が付くと、滋賀県草津警察署へ被害届を提出しました。
そして、被害届を受けた滋賀県草津警察署はVさんに対する名誉毀損事件として捜査を開始しました。
滋賀県草津警察署の捜査により、書き込みを行った人物がAさんであることが判明し、滋賀県草津警察署はAさんについて名誉毀損罪の容疑で在宅での捜査を行うこととしました。
(※事例はフィクションです。)
・名誉棄損事件と在宅捜査
本件では、Aさんは逮捕・勾留による身柄拘束を伴わない在宅捜査を受けています。
身柄を拘束されていない以上、以前と同じように社会生活を送ることができることが多いですが、その一方で身柄事件と比較して捜査が長引く傾向にあります。
逮捕・勾留による身体拘束は、被疑者を強制的に拘束するものですから、被疑者の人権を侵害している手続です。
そのため、逮捕・勾留がむやみやたらに長くなることのないよう、逮捕・勾留には厳格な時間制限が設けられているのです。
ですから、逮捕・勾留が伴う捜査を受けている場合には弁護士に釈放を求める活動を依頼していくなど迅速に対応していく必要がある反面、捜査をする側にも時間制限があるため、起訴・不起訴等の判断が下される時期のめどが立てやすいといえます。
一方、今回のAさんの名誉毀損事件のように、在宅捜査の場合には、特に捜査について時間制限があるわけではありません。
ですから、捜査の進みが逮捕・勾留されている刑事事件と比べてゆっくり進んでいく傾向があるのです。
しかし、だからといって楽観視してよいというわけではもちろんありません。
在宅捜査されている刑事事件であっても、起訴されれば裁判を受けることになりますし、罰金刑であっても受ければ前科となります。
在宅捜査の場合、時間の制約がない分、自分の刑事事件の手続きが今どういった段階なのか分かりづらいこともあります。
逮捕されていないからといって放置するのではなく、まずは弁護士に相談してみましょう。
・名誉棄損事件と示談
名誉毀損事件の弁護活動で重要なものの1つとしては、示談交渉が挙げられます。
今回のように、名誉毀損行為の被害者が知人である場合、Aさん自身でVさんとの示談交渉に臨むことも可能ではありますが、名誉毀損事件の当事者同士が直接交渉を行う場合は、却って紛糾してしまう場合もあります。
特に名誉棄損事件では、名誉毀損行為によって被害者のデリケートな事情に踏み入ってしまっているケースもあり、なかなかお互い冷静な話し合いをすることは難しいと考えられます。
弁護士に依頼するということは、そうした当事者間のクッションを設けることで、よりスピーディーで適切な交渉を行うことが期待できるのです。
名誉毀損罪は、被害者が「告訴」をしなければ起訴されない親告罪です。
起訴される前に示談締結によって告訴をしないことを約束してもらったり、告訴を取り下げてもらったりできれば、不起訴処分を獲得することもできます。
起訴後の示談締結であっても刑罰の重さを判断する際には有利にはたらくと考えられますが、有罪判決を受けて刑罰を受けてしまえば前科もついてしまいますから、やはり早い段階で弁護士に相談し、起訴前の示談締結を目指すことが望ましいといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しております。
SNSの普及により、気軽にしてしまった行為が簡単に名誉毀損罪となってしまうことも考えられる環境となりました。
少しでもお心当たりの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
24時間体制の電話受付にて、無料相談のご予約のお電話を承っております(0120-631-881)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
SNSでの名誉毀損事件②
SNSでの名誉毀損事件②
SNSでの名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、滋賀県草津市にある勤め先の同僚Vさんとその上司が不倫関係にあることを知りました。
日頃からVさんのことをよく思っていなかったAさんは、Vさんが上司と不倫している旨の書き込みをSNS上にて公開しました。
Vさんはその書き込みに気が付くと、滋賀県草津警察署へ被害届を提出しました。
そして、被害届を受けた滋賀県草津警察署はVさんに対する名誉毀損事件として捜査を開始しました。
滋賀県草津警察署の捜査により、書き込みを行った人物がAさんであることが判明し、滋賀県草津警察署はAさんについて名誉毀損罪の容疑で在宅での捜査を行うこととしました。
(※事例はフィクションです。)
・名誉毀損罪で罰せられないこともある?
前回の記事では、Aさんが容疑をかけられている名誉毀損罪について詳しく触れていきました。
刑法230条1項(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
しかし、実は前回までの記事で見てきた名誉毀損罪成立の条件に当てはまる行為であっても、全て罰せられるという訳ではありません。
次の条文に該当した場合には名誉毀損罪で処罰されないことになります。
刑法第230条の2
1項 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2項 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3項 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(※注:「前条第1項」とは、名誉毀損罪が定められている刑法230条1項のことを指します。)
刑法230条の2の1項にある「公共の利害に関する事実」(事実の公共性)とは、多数一般の利害に関する事実、つまり、公共の利益に役立つ事実をいいます。
もっとも、「公共」といっても社会全体のことに関する事実のみ指しているわけではなく、一定のグループのみの利益に関する事実は当該グループ内において公表する場合にのみ公共性を肯定できるとして、「公共」概念の相対性を認められています。
刑法230条の2の2項でいう「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」は、先ほど取り上げた「公共の利害に関する事実」=多数一般の利害に関する事実、つまり、公共の利益に役立つ事実であるとみなされるということになります。
一方、刑法230条の2の3項では、名誉毀損罪にあたる行為が公務員や公選による公務員の候補者(例えば市議会議員候補者等)に関する事実に関わるものである場合について定めています。
この場合、刑法230条の2の1項で取り上げた「公共の利害に関する事実」であるかどうか=「事実の公共性」があるかどうかに加えて、「目的の公共性」も存在するものとみなされる結果、名誉毀損行為によって摘示された「事実」が真実かどうかの判断のみで名誉毀損罪として罰せられるかどうかが判断されます。
なお、刑法230条の2の1項にある「その目的が専ら公益を図る」とは、公益を図ることが主たる動機であればよいとされています。
真実性の証明ができた場合には、刑法第230条の2第1項により、名誉毀損罪によって罰せられることはありません。
・真実だと思って名誉毀損行為をしていた場合
では、名誉毀損行為をした人が、本当は嘘の「事実」であったにもかかわらず、摘示した「事実」は真実であると信じて名誉毀損行為をしていた場合はどのような結果になるのでしょうか。
この場合、「事実」についての裏付けもしていない軽率な言論行為についてまで、「名誉毀損行為をした人が真実であると思っていた」という点のみで名誉毀損罪として処罰しないとすれば、名誉保護の観点から妥当ではありません。
そのため、証明可能な程度の資料・根拠をもってその「事実」を真実であると誤信していた場合にのみ、名誉毀損罪によって処罰しないこととされています。
なお、今回のAさんは、あくまでVさんを快く思っていなかったことから不倫の事実をSNSに書き込んでいます。
これは公益を図ることが主な動機であるとは言えませんし、Vさんもその上司も公務員や公選による公務員の候補者というわけではなさそうです。
ですから、Aさんの名誉毀損事件では、刑法230条の2は適用されないと考えられます。
名誉毀損事件では、刑法230条の2が適用されるかどうかを争う複雑な事案も存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士がそういった複雑な刑事事件のご相談にも丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください(フリーダイヤル:0120-631-881)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
SNSでの名誉毀損事件①
SNSでの名誉毀損事件①
SNSでの名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、滋賀県草津市にある勤め先の同僚Vさんとその上司が不倫関係にあることを知りました。
日頃からVさんのことをよく思っていなかったAさんは、Vさんが上司と不倫している旨の書き込みをSNS上にて公開しました。
Vさんはその書き込みに気が付くと、滋賀県草津警察署へ被害届を提出しました。
そして、被害届を受けた滋賀県草津警察署はVさんに対する名誉毀損事件として捜査を開始しました。
滋賀県草津警察署の捜査により、書き込みを行った人物がAさんであることが判明し、滋賀県草津警察署はAさんについて名誉毀損罪の容疑で在宅での捜査を行うこととしました。
(※事例はフィクションです。)
そもそも、今回のAさんが容疑をかけられている名誉毀損罪とはどのような犯罪なのでしょうか。
名誉毀損罪の条文を見てみましょう。
刑法230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
・名誉毀損罪と「公然と」の意味
名誉毀損罪の条文にある「公然と」とは、不特定又は多数人が認識し得る状態のことをいいます。
このうち、「不特定」の人とは、相手方が特殊の関係によって限定された範囲に属する者でないことをいいます。
例えば、公開の場所や公道における演説会、雑誌やインターネットで事実を摘示すれば、無関係の人たちがその事実を認識することになるわけですから、「不特定」の人が見るものだといえるでしょう。
一方、「多数人」とは、単なる複数ではなく、相当の多数を意味するものとされています。
つまり、名誉毀損罪においては、特定されていても多数であれば「公然と」という状況であり、不特定であれば少数でも「公然と」という状況となることになります。
もっとも、形式上は公然には当たらない場合、つまり特定かつ少数の場合であっても、それが不特定又は多数人へと伝播する可能性があるときには、「公然と」に当たると判例は解していますから、名誉毀損罪の「公然と」という条件に当てはまるのかどうかの判断にも、専門的な知識や経験が必要となってくるでしょう。
今回のAさんはSNSに書き込みをしていますが、SNSはまさにインターネットがつながっていれば誰でもアクセスできるツールですから、「不特定」又は「多数人」にその書き込みを認識し得る状態にしているといえるでしょう。
すなわち、Aさんは名誉毀損罪の「公然と」という条件を満たしていることになります。
・名誉毀損罪と「事実を適示し」の意味
名誉毀損罪の条文に戻り、次は「事実を摘示」するという言葉に注目してみましょう。
これは、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的な事実を表示することをいいます。
名誉毀損罪における「事実」とは、人格的価値にかかわる事実のみならず、プライバシーに属する事実も含みます。
さらに、摘示された「事実」は、必ずしも非公知のものであることは必要ではなく、公知の事実であっても構いません。
公知といっても、まだ知らない人がいないとはいえず、また、公知によって低下した社会的評価のさらなる悪化の可能性もあるからです。
また、「事実の有無にかかわらず」とあるため、「事実」は真実である必要ではなく、嘘や虚偽の「事実」であっても名誉毀損罪の処罰対象になりますし、逆に言えば本当のことであっても社会的評価を落とす「事実」であれば名誉毀損罪として処罰される可能性があるのです。
「嘘を広められた」「嘘によって誹謗中傷された」ということで名誉毀損罪が成立するイメージのある方もいるかもしれませんが、名誉毀損罪の成立には、基本的には「事実」が本当かどうかは関係ないのです(例外として次回の記事で取り上げる刑法230条の2があります。)。
今回のAさんの事例で考えてみましょう。
不倫をするということは、一般的に倫理に反することであると思われています。
さらに、AさんはVさんが誰と不倫をしているのかも具体的に示しています。
こうしたことから、AさんがSNSで示したVさんの不倫の事実は、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的な事実であると考えられそうです。
・名誉毀損罪と「毀損」の意味
それでは、名誉毀損罪の条文にある「名誉を毀損した」とはどういったことを指すのでしょうか。
一般的には、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることであるとされています。
そして、ここで注意すべきなのは、名誉毀損罪が成立するには、あくまで人の社会的評価が害される危険が生じればよく、実際に社会的評価が下がったということは必要ないということです。
今回のAさんの事例では、Aさんは不倫という一般的に許されていないことをVさんがしているという事実をSNS上で摘示しています。
一般的に倫理に反すると考えられている不倫をしていると知られれば、Vさんの社会的評価が下がる可能性はあるでしょう。
先述したように、名誉毀損罪では人の社会的評価が下がる危険が生じていれば「毀損」にあたるため、Aさんの行為は名誉毀損行為であると考えられるのです。
このように、名誉毀損罪1つとっても、該当する条文に明記されていない解釈があり、自分の関わっている刑事事件と1つ1つ照らし合わせながら考えていく必要があります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、わかりにくい刑事事件についても弁護士が丁寧にご説明いたしますので、まずは遠慮なくご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。